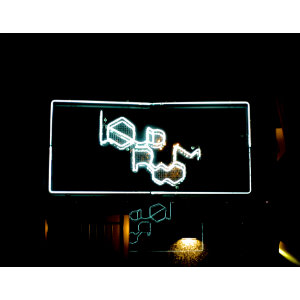2ndアルバム『FASHION』リリースインタビュー
I Don’t Like Mondays.が考える、“世界基準”と“日本らしさ”の両立「ビルボードチャートでも勝負できるものを」


I Don’t Like Mondays.とThe 1975は精神性が似ている?
――曲単体のキャッチーさを追究していた前作に対して、今回はアルバムの全体像の中でどう聞こえるかを重視していった、ということですね。その結果、サウンドの振り幅も一気に広がっています。
悠:僕ら自身、自分たちが飽き症だということはよく分かってるんで(笑)。それに「僕らは『Crazy』のような曲ばっかり作るバンドです」ということになると、やっている自分自身が白けてしまう。当然、僕にはシリアスな面だってあるわけですから。アルバム全体の流れとしても、映画と同じように何か途中で事件があって、気持ちが落ちて、でも最後に向けて上がっていく――。そういう雰囲気を一番意識したかもしれないです。ただ上がっていくだけだと飽きちゃうし、奇をてらい過ぎても伝わらないし。
――I Don’t Like Mondays.はリスナーとしても様々な音楽を聴いているバンドですし、ミュージシャンとしての素顔は、実はこだわりが強い職人気質な人たちだと思います。たとえば最近好きな音楽や、今回特に影響を受けた音楽を挙げるなら?
悠:好きな音楽で言うと、僕の場合、最近は特にヒップホップやクラシック、あとヒーリング・ミュージックですね。イルカの声とか(笑)。まぁ、中心はヒップホップです。カニエ・ウェストもエイサップ・ロッキーも、結構ゴリゴリのビッグ・ショーンとかも聴いていて。
秋気:たとえば、「Fashion」はポリスを意識しているし、(トロピカル・ハウス的な要素が入った)「Tonight」や(バンド・サウンドとエレクトロとが融合した)「Game over」は逆に最近の音楽に影響を受けていて。時代的にも色んな音楽の要素が入っていると思います。「Freaky boy」はハウスやテクノに影響を受けた曲ですね。
悠:「Stranger」はプリンスを意識した曲ですね。実験として成功したのは「Crazy」や「Freaky boy」。「Crazy」の元のアイディアは80sのファンク・ミュージックで、今までの僕らのシングルらしい曲ではありますけど、その中でもちょっと違うことをやろうとして作った曲なんですよ。
謙二(Ba.):80s感を出すためにベースも打ち込みでやりました。そこに最近のビルボード・チャートに入っているような新しい要素も入れて、結果としていいバランスに落ち着きましたね。
悠:80sっぽいという意味ではクローメオとかも好きだし、ロビン・シックとかも好きだし、バンドだとThe 1975も好きなんですよ。

――The 1975は、精神性も含めてI Don’t Like Mondays.に似ている気がしますね。
悠:バンドという形式にとらわれないところなんかも、そうかもしれないですね。
謙二:あとは、ジャスティン・ビーバーがエド・シーランとやっている「Love Yourself」(15年の『Purpose』に収録)みたいなアコースティックの曲がほしいと思い、「Marry me」を作ってみたりとか。
悠:結局、僕らは昔のものも最新のものも好きなんで、「それを掛け合わせたらどうなるんだろう?」とか、その結果「自分が聴いてみたいものを作りたい」と思って曲を作っているんです。「ジャスティン・ビーバーとあれを掛け合わせてみたらどうなるんだろう?」って。
兆志:僕だと「Freaky boy」のギター・ソロもそうですね。これはダフト・パンク(の新作でギター・ソロを弾いていたナイル・ロジャース)とジェフ・ベックがエレクトロっぽいことをやってる時期に影響を受けてる部分があるのかな、と今思いました。

――ちなみに、今回一番苦労した楽曲はどれだったんですか?
謙二:最後の「Life」は一番苦しかったですね。この曲は一歩間違えると普通のバラードになってしまうというか。
兆志:何かしらの違和感がないとダメだと思うんで、ミックスの時にも知恵を絞りました。
悠:歌詞も大変でしたね。今までの流れを考えた時に、ここでまた<Hey, baby>みたいなノリになるのは違うというか。もう一皮めくらないと通用しないと思ったんですよ。それで今までになかった、人生のような大きなテーマを落とし込むには「どうすればいいんだろう?」って色々考えて。
――この曲はいわゆる「一日のデート」ではない、もっと大きなテーマを扱った曲ですね。この曲が最後にあることは、全体の構成にとっても意味のあることのように思えます。
悠:そうですね。かといって、これまでと違い過ぎるのもどうかと思って、全体に溶け込むようにバランスを取るのが大変でした。あとは「Crazy」も苦労しましたね。完成版は曲の頭がいきなりサビですけど、最初はAメロからスタートする曲だったんです。でも、「何か足りない」と思って。それで頭をサビに変えて、AメロもBメロも録り直して、メロディを変えて歌詞を直して。最終的にはいい形になって本当によかったです。
――海外と日本との距離という意味では、どんな風に感じているんですか?
悠:僕らはJ-POPという枠組みの中で音楽をやらせてもらっていますが、同時に「ここはJ-POP過ぎるぞ」というところは、改良したりすることもあるんです。ワールドワイドの人に聴いてもらいたいという気持ちもあるので。でも、かといってアルバム全部を英詞にして、日本の人たちに受け入れられないものを作りたいわけではないというか。僕らの世代ってYouTubeもあるし、普通の小学生がワン・ダイレクションやジャスティン・ビーバーを聴いているように、垣根がなくなってきている部分は確実にあるはずで。ただ、それを変に「海外に憧れる」という感じにするんじゃなくて、ただ「ビルボード・チャートでも勝負できるもの」を追究したいと思うんです。ワールドワイドでいいとされているものが好きなので、それをたまたま自分たちがいるこの地域で消化して、それを越えたものを作りたいという気持ちなんです。僕は宇多田ヒカルさんの新作もRADWIMPSも好きですし。それをバンドにエッセンスとして落とし込むかというと別ですけど、みんなそれぞれに好きな人は沢山いて。みんながいいと思うものは、やっぱり何かいい部分があるじゃないですか。だから、Mr.Childrenも聴くし、エイサップ・ロッキーも、イルカの鳴き声も聴く、みたいな(笑)。