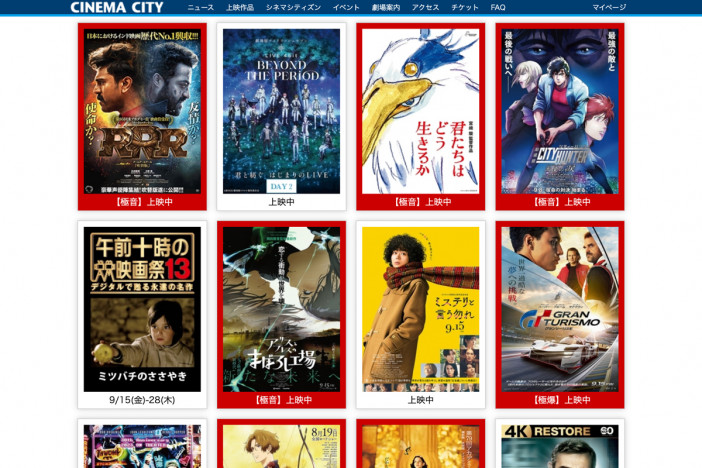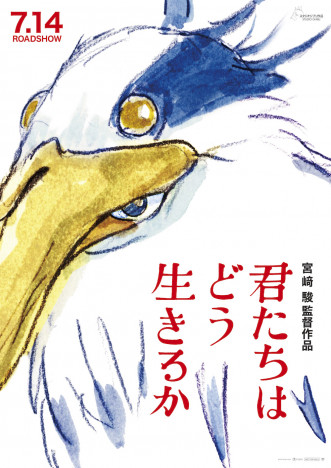立川シネマシティ・遠山武志の“娯楽の設計”第48回
映画の長さは何時間が“正解”? 現代のライフスタイルや娯楽を基に考える

東京は立川にある独立系シネコン、【極上爆音上映】等で知られる“シネマシティ”の企画担当遠山がシネコンの仕事を紹介したり、映画館の未来を提案するこのコラム、第48回は「第47回“映画の長尺化が映画館にもたらすもの”」に続いて、映画の尺(上映分数)についての考察“映画の長さは何時間が正解か?”というテーマで。
3時間超え/90分未満の映画は特別料金が必要? シネコンのタイムテーブルを作って検証
東京は立川にある独立系シネコン、【極上爆音上映】等で知られる“シネマシティ”の企画担当遠山がシネコンの仕事を紹介したり、映画館の…
かなり前になりますが、僕はレンタルビデオ店でアルバイトをしていました。すでにシネマシティでもバイトしていましたので、かけもちというヤツです。
ここで僕は呆然としました。店のメインの棚のほとんどが海外のテレビドラマに占められていたからです。人気作になるとすでに何シーズンも続いていて、1タイトルだけで20本30本とならんでいるわけです。新しい続きの巻のレンタル開始日だと開店前から何名か並んでいたくらいでした。今ならアニメシリーズがその位置になっているのでしょうか。
映画を生涯の仕事にしようと決めていた僕は愕然としたわけです。これが現実か、と。
動画という括りの中で、一番ポピュラーなのはテレビの連続ドラマやアニメシリーズなのだと、もちろん頭ではわかってはいましたが、眼前に見せつけられるとインパクトが違います。
内容はさておき、この時気づいたのは、この人気の理由のひとつは1話の短さにあるのだということでした。1話1時間、あるいは30分。この短尺は日常生活に組み込みやすい。
現在の映画の基準としている尺は、だいたい2時間。食事だの風呂だの諸々のタスクを終えて、例えば21時から見始めたら、23時を越えるわけです。これはまず観はじめるハードルがなかなか高いわけです。
30分とか1時間なら、ぱっと観ではじめられ、でも結局2時間、3時間観続けてしまうなんてことはよくあることですが、最初から2時間は躊躇してしまいます。この時間フォーマットの差でもアニメやドラマに勝ちにくいな、と。
自宅から映画館の話に変えましょう。映画館はお一人様にもやさしいエンタメ施設ですけれども、友達や家族で楽しんだり、ポピュラーなデートの場所でもあります。つまり休日利用が多いわけですが、2時間、これ休日を過ごすというには短すぎません?
デートの時に特に顕著になると思うのですが、例えば12時にランチからスタートして13時30分スタートの映画を観るとします。終わるのは15時40分くらい。何この中途半端な時間。ディナーにはまだ遠すぎる。
かと言って、社会人であれば平日デートには2時間は長いわけです。仕事終わり19時スタートなら間に合うけど、終了は21時20分とか。そのあと居酒屋なら間に合うけど、レストランにはちょっと厳しい時間です。
いっそ先に食事して、そこからレイトショー観るのもありだけど、やっぱり映画を観終わってからあれこれ話し合うのが楽しいわけで。
これらを踏まえて考えると、映画館のエンタメ施設としての使い勝手から逆算して、映画は休日を過ごせる3~4時間の「ロング」と、平日夜にも行きやすい1時間程度の「ショート」をフォーマットとして用意したほうが良いのではないかと思うのです。
今までの2時間程度の作品も「ミドル」として残してもいいでしょう。これで前回のコラムの「映画館側からのビジネスとしての視点」からも、「利用者側からの使い勝手の視点」からも、映画の尺について同じ結論にたどり着くわけです。
「ロング」の創作側のメリットもあるかと思います。現在作られる映画の多くが、小説や漫画が原作になっているので「あのエピソードが削られている」ということが多くあります。長くすることで、これを減らせます。
前後編2本にする、という例も少なくありませんが、これは実はリスクも高いわけです。前編がヒットしなかったら、後編の成績はそれを大きく下回ってしまうからです。1本にまとめてしまえば、続編リスクはなくなります。
「ロング」作品にはかつての長尺映画がそうしてきたように「インターミッション(途中休憩)」を設けるべきです。長時間拘束による肉体疲労や、避けがたい集中力の低下、なにより尿意によって、鑑賞の質は大きく低下していきます。それは制作者も望まないのではないでしょうか。途中休憩は完全とまでは言わなくても、それらをリセットできます。
映画を観るしばらく前から水分を断って、上映中もなにも飲まないようにしよう、そんな風にお客様に考えさせること自体、エンターテインメントとしてどうなのか、とも思ってしまいます。
途中休憩は、ギリギリトイレに行けるだけの5分10分ではなく、20分から30分にして、軽食を売れば利益も上がります。演劇では20分程度休憩を取ることが多いです。
もちろんインターミッションは映画館としては、無いほうがありがたいです。例えば大ヒット上映中のインド映画『RRR』は本来途中休憩があり、シネマシティからお願いして途中休憩ありの上映データを配給会社に作ってもらいましたが、データはあってもシネマシティ以外のシネコンで途中休憩を設けるところはほぼありませんでした。
しかしそれは、現状のままだと単に「実質人的コストは2本上映しているのとほぼ変わらないのに料金は1本分」だからです。長時間化で上映可能回数も減るからです。しかし入場料金を上げ、コンセッションでドリンク&フードの売り上げも上がるとなれば、話は変わるのではないでしょうか?
こういう実験も兼ねて、シネマシティでは《月イチ アニオール》という土曜の深夜にテレビアニメシリーズの全話上映する企画をやっているのですが、ここで「スペシャルメニュー」として毎回その作品にちなんだフードを作って提供しております。長時間になるので、途中に長めの休憩を入れているからです。
コロッケやとんかつを150食分も揚げたり、ご飯を炊いて大鍋でルーを煮込んでカレーを出したり、治部煮を作ったり、シネコンフードの枠からは考えられないレベルの食事を提供して、好評をいただいています。売り上げも上々です。
30分ほどの途中休憩をもうければ、こういう展開もできるはずです。お客様にも楽しんでもらえて、売店の客単価も跳ね上がります。自前で作るとなると簡単ではありませんが、仕出し弁当だっていいわけです。
「ショート」のメリットは平日夜でも行きやすい気軽さと、休日なら何本かはしごする楽しみがあること、そして上映が終わってからレンタルや配信になったときに日常使いが良いということでしょう。シリーズ化もしやすいはずです。