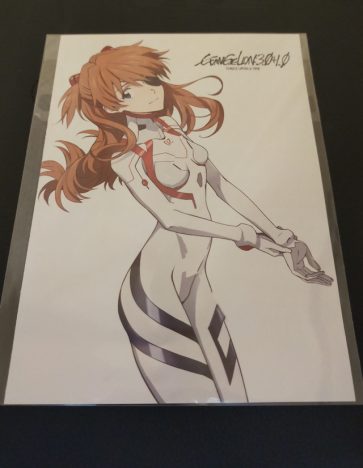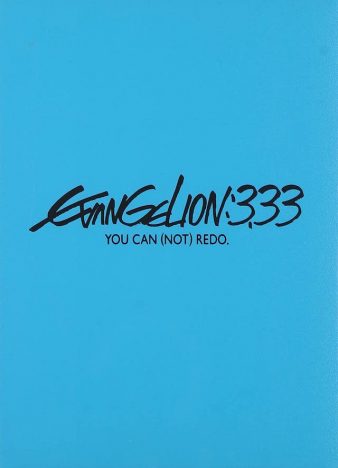【ネタバレ】『エヴァ』は本当に終わったのか 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』徹底考察

世界のかたちと幸せのかたち
TV版や旧劇場版では、カヲルやアスカを助けられなかった罪悪感に苛まれるシンジの“デストルドー(死への衝動)”が利用され、人類補完の儀式が始まった。だが内面世界のなかで、シンジは自分を取り戻し、計画を未然に止めるという結末を迎える。それに比べて本作が特徴的なのは、すでにシンジは第3村において、この葛藤から脱出することができているという点である。ここで、彼の心に何が起こったのだろうか。
最も大きかったのは、ともに村での生活を経験したアヤナミレイ(仮称)とのコミュニケーションである。彼女は自分の植えた稲を刈り取ることもできない、短い数日間の中で、第一次産業に従事したり、子どもと触れ合ったり、他人と語りものを食べるという、人間生活の基本となる体験を通して、“人生”を過ごすことになる。ほぼ全ての人間は、歴史の途中に生まれ、歴史の途中に死んでいく。それぞれに残された時間の差こそあれ、この前提は変わらない。
そんな人生の中で、彼女は「好き」という感情をシンジに伝えることになる。好意を伝えることや、手を繋ぐこと。それは、シンジが渚カヲルに与えられた、孤独な人生を照らす光のように感じた、束の間の喜びでもある。だが生きている限り、その感情をまた誰かから与えられることもある。そして、トウジやケンスケ、アスカが優しくしてくれたように、シンジもまた、表面的な演技などではなく、誰かに好意を伝え、手を繋ぎ、優しさを与えることで、他者と生きることの意義を学んでいくのである。
この後、ミサトと最後に束の間の時を過ごすシンジは、ミサトの息子と村で出会ったことを伝え、「僕は好きだよ」と声をかける。何よりも息子の未来のために、自分の命を賭して最後の戦いに臨もうとするミサトにとって、その言葉は最も嬉しく心に響いたのではないだろうか。良くも悪くも、言葉はときに個人の中の世界に影響を与え、変えてしまうことがある。シンジが渚カヲルやアヤナミレイ(仮称)に出会い、世界のかたちを変化させたように。だからこそ、シンジはミサトの身になって考えることで、自分の願望や体裁とは関係なく、ミサトの心を晴れやかにする言葉が出てきたのではないか。
「何かいいことあるかもと思って、ここに来たんだ。嫌な思いをするためじゃない」
自分の幸せだけを求めて、シンジはエヴァに乗っていた。ミサトやゲンドウからの評価や他人の言葉を求めるのも、自分の価値を実感するための行為に過ぎなかった。どこまでいっても自分、自分、自分……。そんな人間だったシンジは、他人を幸せにすることにも意味があるということを、第3村での共同生活から学んだように見える。自分と他人が生きる世界の幸せは、「相補性」によって支えられている。
それはまた、全ての人々の欠けた心の補完を人為的なインパクトによって達成しようとする、「人類補完計画」にもリンクする考え方でもある。しかし、その方法やタイミングを勝手に決め、強制的に個人の意志を奪ってしまうのが、補完計画の独善的な部分だった。アヤナミレイ(仮称)が“人間”として、様々な経験や思いやりの気持ちを学ぶことで自分の幸せを見つけたように、人間には試行錯誤しながら自分の幸せのかたちを探す権利がある。
すでに第3村で幸せのかたちと世界のかたちをつかんでいるシンジは、その時点ですでに父・ゲンドウを乗り越えている。よって、虚構と現実が混じり合うという「ゴルゴダオブジェクト」が生み出した世界の中においても、シンジはゲンドウの心を救うことで、父の目論見を断念させることに成功するのである。
この父と息子の対話・対決シーンは、半ばギャグとして表現されているところがある。彼らが対峙する記憶のフィールドは、撮影所のセットや特撮のジオラマとして描かれる。初号機が倒れ込んでセットのハリボテを突き破ってしまう描写は、押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフル ドリーマー』(1984年)においても使用された演出であり、エヴァ同士の室内での戦いは、実相寺昭雄監督が『ウルトラセブン』のエピソードの中で描いた、地球を支配しようとするメトロン星人と、地球を救おうとするモロボシ・ダンが、アパートの一室でちゃぶ台を囲んで議論した、前衛的かつユーモア漂う演出のパロディだと思える。
ちなみに『ウルトラマンA』では、キリストが磔刑に遭ったという「ゴルゴダの丘」を模した、「マイナス宇宙」に存在する「ゴルゴダ星」という場所で十字架にかけられるウルトラ兄弟たちの受難を描いている。これをパロディ化したものが、本作や新劇場版全体の設定の基になっていることは明白であろう。名作SFアニメーションを想起させる「ヤマト作戦」、「裏コード999」というワード、さらに本作の劇中では、宇宙防衛艦・轟天号が活躍する特撮SF映画『惑星大戦争』(1977年)の劇伴や、日本を代表するSF作家・小松左京が総監督を務めた『さよならジュピター』の主題歌を使用しているなど、SFアニメ、特撮オタクとして、本作ではこれまで以上に庵野監督が、やりたい放題の限りを尽くしている。
ことここに至って、もはや『エヴァ』の設定や、散りばめられた謎のキーワードから、物語上の様々な仮説を立てること自体が、もはや陳腐化してしまったといえる。これは監督自身が本シリーズ全体で狙っていた試みでもあったのだろう。旧シリーズが話題になっていた当時、『エヴァ』の謎を追った書籍はブームに乗っていくつも出版されたが、衒学的な要素を追求した先に『エヴァ』の本質は存在しないということを作家自身が述べている、一種のネタバラしにも思えるのである。
とはいえ、「ゴルゴダオブジェクト」と「マイナス宇宙」には、テーマに関係する興味深い点も存在する。それが、この仕組みが到達させる「エヴァンゲリオンイマジナリー」というものである。虚構の中のエヴァ、それぞれの人々の記憶の中のエヴァが、そこにいたのだ。ゲンドウの思うエヴァ、シンジの思うエヴァ、庵野監督の思う『エヴァ』、観客一人ひとりの中に存在する『エヴァ』が、そこでは変幻自在のかたちで存在している。
そんな不思議な世界の中において、シンジは新しい槍を手にする。希望の船・ヴンダーのクルーたちの頑張りや、ミサトの体を張った突入、マリの奮闘によって、シンジの手に託された槍は、人の意志が込められている「ヴィレの槍」だという。この描写は、庵野監督が新劇場版をこれまで手がけてきたスタッフ、キャストたち全員への感謝を示しているように感じられる。劇場アニメーションは、一人だけの努力では作ることができない。庵野監督がもう一度『エヴァ』の終局を表現するために、多くの人々が背後で尽力を重ねたことが、このシーンで描かれているのだ。だが、作品が大勢の頑張りによってかたちになっているのは、他の映画やアニメーション作品でも同じことだ。ここで感傷に溺れているような描写があることで『エヴァ』がやはり監督個人のプライベートフィルムであったということが思い出されるのである。
本作のシンジと庵野監督は、他者への思いやりを持つことで、ゲンドウも含めた登場人物たちそれぞれの“心の補完”を手助けする。個人としての心の充足によって、ヒトたちは再び自分の体を取り戻していく。そしてシンジは、新劇場版でゲンドウが狙った「絶望のリセット」ではなく、ヴィレが目指し、旧シリーズでシンジが選び取った「希望のコンティニュー」でもない、第3の槍を使う。世界の改変による再出発「NEON GENESIS」、つまり新たな世紀創生の儀式に挑む。
神話と福音に導かれた主人公
シンジが虚構と現実が混ざり合う場所で、人々の想いを乗せて槍を突き立てる。初号機をはじめ、残存する全てのエヴァが、次々にその槍に刺し貫かれていく。碇シンジの持つ、「無限大のシンクロ率」によって、われわれ観客一人ひとりに見えている全ての虚構の中の『エヴァ』もまた、そこで刺し貫かれているのだろう。シンジが望んだのは、「エヴァのいない世界」だ。『エヴァ』の世界の現実に存在していたエヴァも、われわれの心の中に存在するエヴァも、その全てをシンジは葬り去ろうとする。
ここで気づかされるのは、本作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』とは、“観客参加型の映画”だったということだ。われわれ観客が、本作を観て自分の話をしてしまう理由とは、自分の心の中のエヴァが本作に出演していたからであろう。そして、観客は自分の『エヴァ』と決別し、弔いをすることになるのだ。本作の核となる部分とは、まさにこの入れ子構造のユニーク試みなのである。
このシーンで流れているのが、映画『さよならジュピター』の主題歌だ。この作品のクライマックスでは、三浦友和演じる主人公が、人類の繁栄のために木星へと突っ込んでいくストーリーが展開する。シンジもまたマイナス宇宙のなかで、本作の登場人物たちやスタッフたち、観客のために、救世主として虚構の狭間へと溶けて消え去ろうとする。これが、自分の心を優先して多くの人々を死なせてしまった、碇シンジの贖罪のかたちである。
だが、思わぬマリの出現によって、シンジは寸前で助け出される。そして、二人は再構成された世界の中で駅に降り立っていた。碇シンジは、もうエヴァを必要としていない。だからこそ、“エヴァの呪縛”から解き放たれ、歳を重ね、『エヴァ』という列車から降りることができたのだ。それを可能にしたのが、人と人との「相補性」であり、出会いの可能性だ。
マリは、新劇場版において突然現れたキャラクターである。そして、彼女がこれまでの『エヴァ』の外部にいた突発的な存在だったからこそ、シンジをこれまでとは違う世界の外に連れ出す役割を果たすことができたのだろう。そしてシンジはマリとともに、実写映像として表現された、現実の世界へと踏み出していく。列車のレールが敷かれていない、無限の選択肢があるフィールドを、自分の足と自分の意志で進んでいくのである。
旧劇場版の公開から新劇場版が製作されるまでの期間において、庵野監督に起きた大きな出来事といえば、結婚したことである。おそらく、旧劇場版を製作していたときには、考えもしなかったパートナーと、いま生活を営んでいるはずである。だとすればそれは、本シリーズで映し出された、シンジとマリの関係そのものであるといえよう。一方でシンジは、旧劇場版において大きな存在だったアスカに、本作の中で「僕も、アスカが好きだったよ」と伝えている。アスカもまた、シンジとの関係を過去の恋愛だととらえ、その頃には想像もしていなかった相手をパートナーに選んでいる。アスカを真に救う相手は、シンジではなかった。だが、それが人生の面白さであり、醍醐味であるといえる。
「生きていこうとさえ思えば、どこだって天国になるわ。だって、生きているんですもの。幸せになるチャンスは、どこにでもあるわ」
庵野監督は、旧シリーズでシンジがセカンドインパクト後の地獄のような世界に誕生したときに、母親の碇ユイから受けた“福音(Evangelion)”を、自分の人生の中で体現したといえるのではないか。『エヴァ』が庵野監督のプライベートフィルムであり、碇シンジが監督の分身であるとするなら、そして庵野監督が一つの幸せに到達したのだとするなら、そのプロセスを描いてもいいはずだ。そして、実際にそれをやったのが、新劇場版だったといえるのではないだろうか。