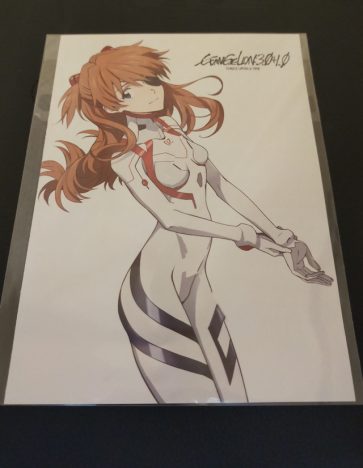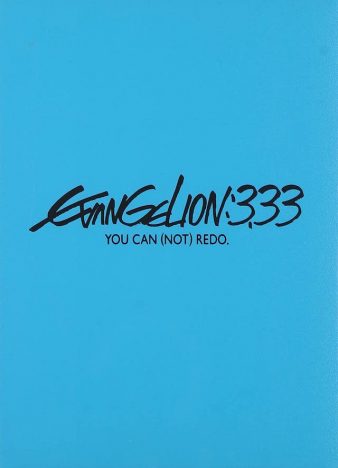【ネタバレ】『エヴァ』は本当に終わったのか 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』徹底考察

碇シンジは成長していたのか
さて、『:Q』の直後から開始される本作の物語では、すでに死亡していたと思われた、碇シンジの友人である鈴原トウジや相田ケンスケらが、アラサーの年代になって登場する。シンジがトリガーとなってしまった「ニアサードインパクト」から避難してきた人々が「ヴィレ」の手引きによって作り上げた「第3村」。トウジはそこで、「委員長」洞木ヒカリと結婚し、独学ながら医師として地域医療を担っていた。おそらく、かつて彼の妹の命を救ってくれた医者という職業への恩返しと憧れの感情が、トウジを献身的な人物へと成長させたはずだ。この絶望の世界で彼を勇気づけているのは、人と人との繋がり合いなのである。
“群体としての”人間の営み、集団社会のミニチュアとしての「第3村」は、『:Q』において深い傷を受けた碇シンジの心が癒される場所であり、ネルフ本部で与えられた命令だけをこなしていた「アヤナミレイ(仮称)」が、様々な学びを経験する場として設定されているとともに、シリーズ全体の中で、スイカ畑や夕焼けに照らされる水田として、かろうじて示されていた農業が、“田植え”というかたちで本格的に示される。
高畑勲や宮崎駿らは、農業や里山での生活を人間生活の根本として位置付け、『機動戦士ガンダム』の富野由悠季もまた、『∀ガンダム』において、ロボットアニメの中で農業を描く試みを行っている。この先人たちの道を庵野監督も結局歩むことになったという点は感慨深いところがある。とはいえ庵野監督は、同じく総監督作を務めたTVアニメ『ふしぎの海のナディア』(1990年〜1991年)の中でも、ジュール・ヴェルヌの小説『神秘の島』(1874年)を原案に、樋口真嗣監督の尽力のもと無人島における自給自足生活と開拓という要素を扱っている。だが、当時マネージメントの問題によって、これらのエピソードでは作画のクオリティが著しく落ちるという問題が起こった。その意味では、本作の丹念に描かれる自給自足パートは、一種のリベンジだったととらえることもできる。
このような、地に足をつけたプリミティブな人間の営みは、『エヴァ』がこれまであえて描かなかったことでもある。テクノロジーに満ちたジオフロントや要塞都市の中での生活描写は、製作された時代とリンクし、生きている実感に乏しい現実の都市生活者の世界観とシンクロしていたといえる。
そこでは、自宅の風呂に入浴することが、最も手軽に、世界の中で自分の存在を感じることのできる行為であった。身体全体に触れる湯が、自分自身に、自分の身体のかたちを意識させ、世界と自分との境界線を示すものとなっていたからだ。本作では、複数の他人と共同浴場で湯を共有することで、自分のかたち、他人のかたち、そして他者と繋がるということを体験するアヤナミレイ(仮称)の姿が描かれる。ときに離れ、ときに近づき、束の間のふれ合いに身体と精神を浸す。1000人ほどが共同生活を送る、この人間社会のミニチュアの中で起きるシンジの心境の変化が、本作のテーマと、新劇場版シリーズのテーマを明らかにすることにもなっているのだ。
「今の自分が絶対じゃないわ。後で間違いに気づき、後悔する。私はその繰り返しだった……。 ぬか喜びと自己嫌悪を重ねるだけ。でも、そのたびに前に進めた気がする」
旧劇場版で葛城ミサトがシンジに吐露した想いは、真希波・マリ・イラストリアスが初登場時に口ずさんでいた、「三百六十五歩のマーチ」の歌詞において、新劇場版でも象徴的にリフレインされている。それが示すのは、『エヴァ』という物語が、傷つきながら、そして汗やべそをかき、ときに後戻りしながらも、碇シンジが少しずつ成長していく姿を追っていくものであるという基本路線だ。
『:破』のクライマックスでは、旧劇場版の後ろ向きな態度を見せるシンジと比べて「成長した」と評価するファンが少なくなかった。たしかに、使徒に取り込まれ絶望の中にいた綾波レイを、物語の流れを無理やり突き破るようなかたちで救出したシンジの前進は、赤城リツコ博士の解説の中で「相補性」と表現したように、人と人が結びつくことで新たな奇跡が生まれるという、作品世界の中における人類の新しい可能性を示した。しかし、シンジはレイを使徒の中から救出するときに、こう言っている。
「僕がどうなったっていい、世界がどうなったっていい!」
レイの救出劇は、一見すると一人の少女のための献身的な行為のように思える。たしかに、そういう部分もあるのだろう。だが、シンジが自分や世界がどうなっても構わないという心境に至ったのは、前回エヴァに乗ったとき、アスカを助けられなかったことで罪悪感を背負ってしまったからだ。自分の運命と、大勢の他人が生きる世界を差し出してまで、シンジは自分の気持ちを救うという決断をしてしまったのだ。それはやはり成長の表現ではあり得ない。
そんなシンジは『:Q』において、自分がさらに引き起こしてしまった、人類の大量死につながる絶滅行動の儀式「ニアサードインパクト」のトリガーになったことを、様々な人々から糾弾されることになる。もちろん、「ニアサー」の責任の全てがシンジにあるわけではないし、ここまで大きな事態になってしまうとは、シンジ自身も思っていなかっただろう。だが弁解を重ねるシンジに、渚カヲルが指摘するように、「ニアサー」当時のシンジの理解不足など、犠牲者の遺族たちにとっては、たいして意味のないものだ。
『:破』のときとは比べ物にならない、人類に対する反逆者としての大きな罪悪感が、絶え間なくシンジの精神を責め続ける。パニックに陥ったシンジは、カヲルの与えた希望の選択肢にすがることしかできなくなってしまう。功を急ぐその姿は、あたかもカルト信者のようだった。カヲルは、シンジとともに新たな儀式へと向かうものの、独自の人類補完計画を進める碇ゲンドウの真の狙いに自分たちが利用されていることに気づき、シンジを制止しようとする。だが、視野が狭まり、一刻も早く重荷を捨て去りたいと願うシンジの暴走は止まらない。その代償として、シンジは新たにフォースインパクトを起こしかけ、それを瀬戸際で防いでくれたカヲルを、目の前で失ってしまう。
「ほんとに他人を好きになったことないのよ! 自分しかここにいないのよ!」
旧劇場版でアスカが指摘していたように、本シリーズで碇シンジが失敗を繰り返してきた原因は、彼が結局、自分のことしか考えていなかったということに尽きるだろう。それは、本作でゲンドウが起こそうとして、ヴィレの面々から総スカンを食った「アディショナルインパクト」における、自分勝手な迷惑さとも重なることになる。
「人の言うことには、大人しく従う。それが、あの子の処世術じゃないの?」
リツコがTV版や新劇場版で冷徹に指摘しているように、シンジは誰かの言うままにエヴァに乗った。それは、結局は自分のためであり、父親やミサトなど、自分が他の人からどう見えるかを意識した行為だったといえよう。だからこそ、自分のエゴによって、エヴァパイロットであることを、あっさりと何度も拒否することができたのだ。