小川紗良の『バッド・ジーニアス』評:映画全体が“カンニング”のように緻密に計算されている
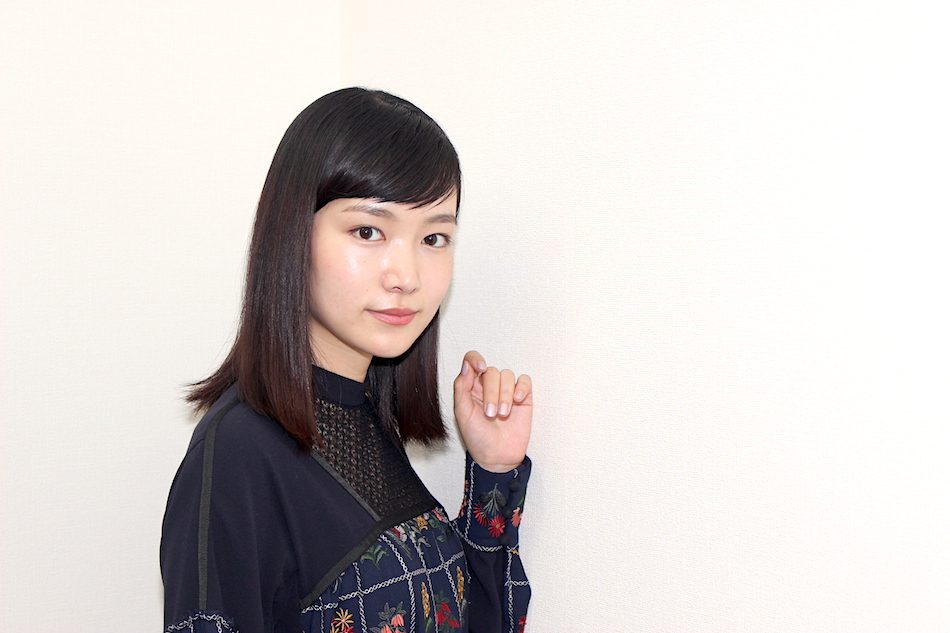
”making it happen”=「実現する」。少女の背中に書かれたその言葉は、希望か、それとも絶望の始まりか。映画『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』は、「カンニング」という犯罪行為をスリル満点に描いたエンターテインメント作品である。ある教室で咲いた小さな犯罪の芽が次第に根を広げていくその様は、もはや爽快にすら感じられる。「カンニング」という少年少女の悪行を、ここまでスリリングに描いた作品が今までにあっただろうか。教室は戦場と成り果て、試験開始のチャイムが鳴ると同時に生徒たちの視線が火花を散らす。指先で暗号を送り合い、シャープペンシルの剣を走らせる。進路も、夢も、友情も、すべてはこの「カンニング」にかかっている。失敗は許されない、実現するのみだ。

本作はタイ映画である。私はこれまでタイの作品にあまり馴染みがなかったのだが、その質の高さには本当に圧倒された。タイでは史上最大のヒットを記録したそうだが、「試験」や「カンニング」といった身近な題材を描いた本作は、日本でも多くの人の心を揺るがし続けている。また、本作は「カンニング」という分かりやすい犯罪を軸としながら、家族、友情、貧富の差といった社会的な側面も持ち合わせている。そのことでより作品の強度が増し、単なるエンターテインメントに収まらない深みを持った作品となっている。タイ映画という言葉にハードルの高さを感じて見逃すには、あまりにももったいない。

印象的だったのは鏡の演出だ。特にファーストカットの合わせ鏡の構図は、一気に観客を引き込む魔力を持っていた。「鏡」とは、ありのままの姿形を映すもの。それでいてそこに映るものは必ず左右反対である。ありのままであって、ありのままではない。そんな矛盾を孕んだ「鏡」は今まで多くの映画やその他の芸術で使われてきたが、本作においても主人公の心の機微や多面性を映しているようだった。ただの「優等生」だった少女が犯罪に手を染め、見た目も中身も徐々に変わっていく様をじっと捉えている。天才も一歩間違えれば犯罪者だと言わんばかりに、その鏡はたたずむ。

主人公・リン(チュティモン・ジョンジャルーンスックジン)は天才少女で、様々な手段を駆使してカンニングを成功させていく。リンが頭脳明晰であるのと同様に、この映画の持つ構図自体にも「頭脳」を感じた。まるで映画全体が、高度な「カンニング」のかように緻密に計算されている。ナタウット・プーンピリヤ監督はCMやMVを多く手がけてきたそうだが、その経歴を逆手に取った映画づくりだと感じた。どのカットも構図がばっちり決まっているし、人物のサイズやカメラワークがいつも的確である。「これ」を伝えるには「どう」表現するのが最も適切か、ということを分かっている人なのだろう。監督は脚本2ページに対して約200カットもの絵コンテを作ったというが、それも納得だ。シャンパンやコーラを開けるカットなんかは笑ってしまうほどCM的だが、不思議と嫌味がなく、作品に溶け込んでいる。





















