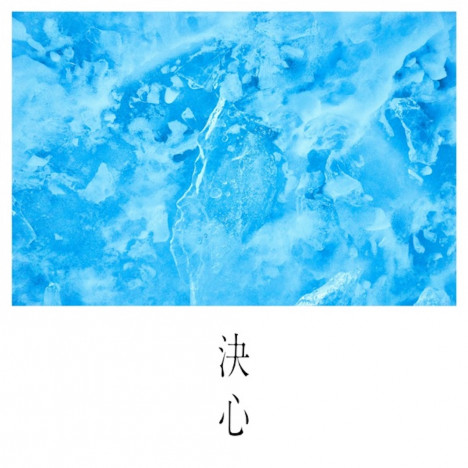金井政人、“相手の期待に応える”作詞家としての姿勢 Sexy Zone、timelesz、JO1ら作詞提供をもとに語る

メンバーになったつもりで書いたB&ZAI「Fist Beat」、熱量を追求したJO1「RUSH」
ーー続いては7 MEN 侍の「足跡」。彼らのライブでの熱唱ぶりからも、この曲に対する強い思いが感じられました。
金井:7 MEN 侍に歌詞を書かせてもらうことになった時、改めて彼らの活動を振り返ったんです。これまでにどういうストーリーがあって、今はどんな心境でステージに立っているのかを想像したくて。これは「バンドマンとして歌を歌っていてよかった」ということの一つなんですが、他の方よりもそういうことを想像しやすいと思うんですよ。全てのケースでメンバーと直接会って話せるわけではないですから、「しっくりこないな」と感じさせない歌詞って何だろう? と考えました。
ーーなるほど。B&ZAIの「Fist Beat」は、彼らにとって初めてのオリジナル楽曲です。
金井:B&ZAIにはバイオリンを演奏するメンバーがいるんですよ。僕らもバイオリンを入れたバンドを長らく続けてきて、その喜びだったり、酸いも甘いも知っていて。この曲の歌詞を書くときは、バンドを始めた20年前に戻って、こういう曲で始めることができたら……という普段とは少し違うバイアスがかかっていた気がします。あと、アーティスト側にも強い意志があるのが想像に難くなくて。B&ZAIというグループができて、最初のコンサートがあって、そこに相応しいオリジナル曲が絶対に必要なんだという。自分としてもできる限りシンクロ率を上げて、メンバーになったつもりで書いた歌詞でもありますね。
ーー金井さん自身のバンド経験も反映されているんですね。JO1の「RUSH」は、勢いのあるダンスチューンです。
金井:歌詞が言葉以上に振り付けや、ダンスとのシンクロを求めている場合があって、この曲がまさにそうですね。トラック自体にハードさ、タフさが宿っていたし、歌詞で熱量のあるパフォーマンスを引き出すことが自分に求められていることだなと。この歌詞で、こんなポーズを決めて欲しいとか、そんな願いを込めながら、正解を見つけることが私の役割だったと思いますし、ライブで最大の熱量を出せる曲にしてもらいたくて。そのイメージを落とし込んだのが「RUSH」の作詞だったと思います。
ーー特にダンスボーカルグループの場合、ライブでどう映えるかも大事なポイントになりますね。
金井:一流と呼ばれるアーティストのライブでは大概、こちらの想像を超えてきますけどね。自分が作詞しているときに思い描いているのはあくまでも想像の範疇だし、それを超えてくるのがカッコいいアーティストなんだろうなと。それはLiSAさんもそうですし、きっと「RUSH」でも私のイメージを優に超えるパフォーマンスが繰り広げられているんだと思っています。

BIGMAMAと作詞家活動を並行したことで得られた変化
ーー本当に1曲1曲アプローチが違うんですね。当然、アーティストのことを深く知る必要もあると思いますが、作詞する際のインプットについてはどう考えていますか?
金井:その時点でリリースされている楽曲やMV、ライブ映像はもちろんですけど、インタビューなどを含めて、リサーチできることはすべてやっています。アーティスト自身の言動だったり、メンバーが好きな言葉、よく使う言葉もインプットしたうえでーー歌詞を構成するうえで、数パーセントの要素だったとしてもーー歌詞を書いたほうが解像度が上がると思うんですよね。一方で、グループに対する先入観をなくして、曲に呼ばれるように書くこともあって。
ーーアーティストのファンの存在についてはどう捉えていますか?
金井:まず“ファン”と一括りにするのは間違ってるんじゃないかなと思っていて。BIGMAMAのファンの皆さんもそうですが、いろんな方がいらっしゃるし、年齢、性別から生活環境まで、一人ひとり違っている。だからこそ一括りにしてはいけないし、歌詞を書くときも基本的には“一人”をイメージするようにしています。そうしないと解像度が上がらないというか、ぼんやりした歌詞になりそうな気がして。
ーー大勢のファンではなく、そのアーティストを好きな“一人”に向けて書く。
金井:その人は今、どんな気分なんだろうな? というのは想像しますね。一方で、アーティストに対して「歌いたいものを歌ってほしい」「カッコイイと思うものを貫いてほしい」という思いもあって。あけすけに言ってしまうと、アーティスト活動は単一な接客業ではないと思うし、喜んでもらうことに重心が傾きすぎると、同じようなモノ作りになってしまいそうな気がするんですよ。そのバランスも大事なのかなと思っています。

ーー作詞家としてのキャリアが始まったことで、BIGMAMAの作詞に対しても何か影響がありましたか?
金井:自分で歌う歌詞と、他の人に歌ってもらう歌詞は私の中で明確に差があるんです。先ほども言ったように、提供する歌詞の場合は、アウトプットのスピード感をできるだけ上げるようにしていて。あとはディレクターの方、作曲家の方とのやり取りを通して、可能な限り早くできあがることが多いんですけど、バンドの歌詞は基本的に自分で判断しなくちゃいけないんですよ。メンバーも「あなたが歌いたいことを歌えばいいよ」というスタンスでいてくれるので、レコーディングの歌入れギリギリまで「これで本当にいいのか?」と悩むこともありますね。つまり仕上がりが遅いです。
ーー歌うのは金井さん自身なので、作詞を提供する場合とはベクトルが違いますよね。
金井:そうなんです。たとえば自分で書いたメロディに対して、「これはラブストーリーだな」と思って、それに似合う歌詞を書いたとする。でも、その歌詞を歌うと「この人は今、恋をしてるんだな」と思われてしまう可能性があるんですよね。たとえそうじゃなかったとしても、聴いてくれた方に「恋をしている」と思われてしまう。そういうギャップみたいなものを感じることがあるんですよね。ハッピーな歌詞も同じで、そのときに楽しい気分だったわけではなくて、落ち込んでいて楽しい気分になりたくて書いているのかもしれない。それを理解してくれるのは、相当コアなファンの方だけなのかなと。
ーー歌詞で描かれている状況や気分は、書いた本人の実体験であるとは限らない。ただ、リスナーは「実際にこういう気持ちだったんだろうな」と思ってしまう傾向がありますよね。
金井:その作用が強くなりすぎると、ある種の呪いみたいになってしまう瞬間もあって。そこは常に意識していますね。逆に、例えばUNISON SQUARE GARDENやSUPER BEAVERのように、ボーカル以外のメンバーがメインで歌詞を書いて、それをボーカルが歌っている場合はきっとまた違ったバランスがあって。そこに絶妙な言葉の玩具具合や、心地よい説得力の重さと軽さが同時に生まれていて、リスナーの心地よく響き、刺さるのだと思っています。私自身はバンド活動と、他のアーテイストに作詞することで、その二軸を体感できていて。片方だけだと苦しかったかもしれないけど、どちらも味わうことで、よりフラットな重心の保ち方を得られているんじゃないかなと思います。
ーー自分の歌詞を自分で歌う、そして、自分の歌詞を他のアーティストに歌ってもらう。この二軸を共存させているクリエイターは、とてもレアだと思います。
金井:どちらかに特化する良さもあると思いますが、それぞれの立ち位置で良い仕事ができたらなと。私の場合、他のアーティストに歌詞を提供することが、自分のバンドを大好きでい続けることにつながっているんです。もちろん、自分の歌詞によってアーティストがより輝く、そして、ファンの方が喜んでくださるのであれば「できることは何でもやります」という気持ちもあって。実際、まだまだできることはあるはずで。作詞家として書き続けることで、もっといいものが提供できるんじゃないかなと。作詞した曲がたくさんの方に聴かれたり、音楽番組でクレジットに自分の名前が載ると、BIGMAMAのファンの方も喜んでくださるんですよ。提供したアーティストのファンの方がBIGMAMAのMVにコメントをくださることもあるし、そうやっていい導線を作っていきたくて。今現在もいろんなお話をいただいているし、「これは勝負してみたい」という現場もあって。そうやって自分の作家としても、もちろんBIGMAMAとしても代表作をどんどん更新していきたいですね。

BIGMAMA、遊園地での煌びやかな情景が詰まった新曲「The Parade」元旦に配信リリース ラジオ初OAも
BIGMAMAが、新曲「The Parade」を1月1日に配信リリースする。 遊園地での過ごし方は人それぞれあるが、今作は“…
“JO1×和”が生み出す魅力 『HOT JAPAN with JO1』『5th Anniversary ~祭り~』に見る世界に届くパフォーマンス
JO1が『HOT JAPAN with JO1』の第6弾として「Handz In My Pocket × KANAZAWA」のS…