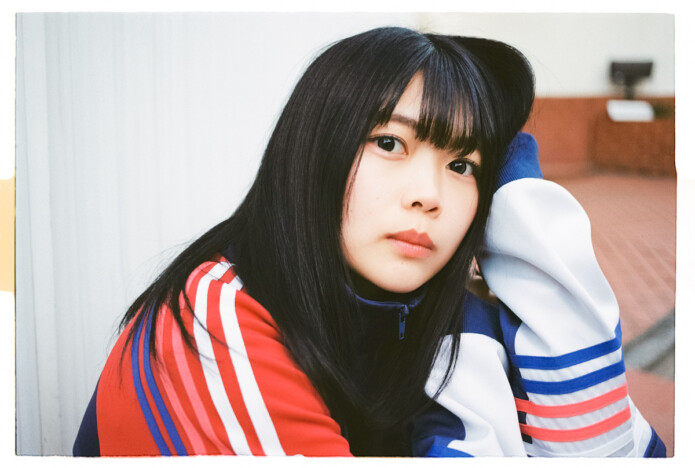lynch.が蘇らせた初期衝動と5人で鳴らす“今” 結成20周年の歩みを映し出すリテイクアルバムを全員で語る

最初に幅を提示して、そのなかで遊べる環境を作りたかった(玲央)

――そもそも『greedy dead souls』も『underneath the skin』も2005年リリースで、その間半年という短いスパンでのリリースでしたが、これは結成時からのプランだったのでしょうか?
玲央:まず、lynch.を始める際にフルアルバムをリリースしようというのは決めていて。同年の秋口からツアーをするにあたって、シングルを出そうというプランでした。
――しかし、シングルといっても5曲入りの実質EPサイズという。
玲央:当時から捻くれた存在だったので、シングルと謳いつつも5曲入りっていう(笑)。おかげで専門店の方から「これはアルバムじゃないの?」という問い合わせをいくつもいただいた思い出があります。
――(笑)。でも、あらためて『GREEDY DEAD SOULS』を聴いてみるとその楽曲の幅広さに驚きました。当時のlynch.は“激しいバンド”というものが根底にありつつも、それ以上に楽曲の幅の広さを意識したバンドだったのではないかとも思ったんですよね。
葉月:はっきりとは覚えてないですけど、当時から好きなものがたくさんあって。ということは表現したいものが多いということなので、どちらかに振るということをしたくなかったんだと思うんですよね。でもたしかに、今あらためて並びを見ると、特に『GREEDY DEAD SOULS』は激しいものとメロディアスなものがはっきりと分かれていて、混ざっていないですよね。
――個人的には『GREEDY DEAD SOULS』の構成はLUNA SEAを感じるんですよね。
葉月:ああ、そうかもしれない。
――『THE AVOIDED SUN』では激しさとメロディアスな部分が融合して、現在における“lynch.らしさ”のようなものが具現化されていくわけですが、結成当初の頃からそういったコアなものとメロディアスなものが融合した楽曲のイメージは、葉月さんの頭のなかで鳴っていたんですか?
葉月:その時はまったくなかったですね。lynch.としても初めての作品なので、“らしさ”もまだないわけで。アルバムを作るうえで「こういう構成にして……」「そのためにはこういう曲が必要で……」というふうに考えながら、ただがむしゃらに作っていったのは覚えています。
玲央:初めての作品だったので、言ってしまえば真っ白な画用紙なわけじゃないですか。当時はその画用紙に、思いつくままに色を塗っていたような感覚でしたね。

――『greedy dead souls』のリリースでlynch.の名前は一躍シーンに広まったわけですが、悠介さんもこの作品でlynch.を知ったんですよね。
悠介:そうですね。あの頃、僕は当時のバンドメンバーと一緒に住んでいて、そいつが『greedy dead souls』を聴いていたのがきっかけでした。実は昔、葉月くんがlynch.を始める前に名古屋MUSIC FARMで一度対バンしたことがあって、その時からいいボーカルだなと思って、声を覚えていたんです。そうしたら、数年後にバンドメンバーが聴いていたCDから聴いたことのある声が流れてきて、「どこかで聴いたことのある声だなあ」「あ、あの時のボーカルだ!」と。
――劇的な再会を果たした、と。
悠介:気になってCDを見せてもらったら玲央さんもいて、「keinの人だ!」って(笑)。
――やっぱり玲央さんは有名人なんですね(笑)。
悠介:「新しいバンド始めたんだ!」と思ったのと同時に、「かっこいいな、これで名古屋も安泰だな」と思ったことを覚えています。
葉月:その話、初めて聞いたかもしれない(笑)。
――20周年にして初出しのエピソードが飛び出しました(笑)。対して明徳さんは、『greedy dead souls』を名古屋バンドマンのバイブルと称していました。
明徳:このくらいの時期ってヘヴィな音楽の黎明期で、当時はあまり洋楽の要素を取り入れたヴィジュアル系バンドっていなかったので、めちゃくちゃかっこよくて。僕を含めた名古屋のバンドマンは、全員車のなかでlynch.を聴いていたと思います。
――そこから半年という短いスパンでリリースしたのが、『underneath the skin』です。当時『greedy dead souls』が幅を意識した作品であるならば、『underneath the skin』は深さを意識した作品と評していましたよね。当時のことは覚えていらっしゃいますか?
玲央:まず最初に幅を提示して、そのなかで遊べる環境を作りたかったんです。言ってしまえば、「lynch.ってこういうバンドだよね」という皆さんのイメージや共通認識を持たせるために作ったシングルでした。
――なるほど。
玲央:今でも覚えてるのが、「melt」のレコーディングをしている時に、エンジニアさんに「『lynch.らしい楽曲って何?』って聞かれたらこの曲だなあ」って言われたんです。実際に収録されている5曲のなかでもいちばんライブでやっている楽曲だし、直近のライブでも回数がいちばん多いんじゃないですかね。そういう意味でも、lynch.というバンドがそういうふうに見られているのかと認識したのもこの頃だし、この作品を出したことによってより深くlynch.というバンドを知ってもらえたと思います。なので、自分の中でも思い入れの強い作品ですね。
“lynch.らしさ”――今に繋がる個性の確立

――今「melt」のお話がありましたが、この作品から激しさやメロディアスに加えて、妖艶さやアングラな要素が加わり、現在のlynch.の片鱗が見えてきたかと思います。実際どのあたりからこういう要素を取り入れようと考えていたのでしょうか?
葉月:どこらへんからなんだろう? でも、「the whirl」や「melt」なんかもですけど、ハードなものにメロディが入ってくるというやり方がここでやっと登場してくるんですよね。この次の『THE AVOIDED SUN』では、その逆――つまりきれいなコード進行にシャウトが乗るというのが出てくるんです。なので、やっと混ざり出したなっていう。
――その発想は自然と生まれてきたものだったんですか?
葉月:特別何かを意識した記憶はないですけど、『greedy dead souls』の反省がここに出ているんじゃないかなと思います。もうちょっと一曲のなかで混ぜてもいいんじゃないか、みたいな。
――晁直さんも過去に『underneath the skin』は『greedy dead souls』で得たものをフィードバックして作ったとおっしゃっていましたね。
晁直:たしか「melt」か「lizard」はリリース前のライブからやっていて、その背景があったからこそ「above the skin」や「alien tune」という曲ができて。そこでバランスを取ったような覚えがあります。
――たしかに当時のlynch.の名刺代わりの一枚のイメージが強い『underneath the skin』ですが、悠介さんは発売日に買いに行ったんですよね。
悠介:そうですね。当時、個人的には『greedy dead souls』よりこっち(『underneath the skin』)のほうが好きだった気がします。前作から半年でこんなに洗練されたものができるという驚きと同時に、そもそも作品全体の空気感が好きで。色で言うと赤味みたいなものを楽曲からも感じ取れるし、それでいて毒々しさもあるし、「すごいバンドが出てきたな」「このまま名古屋を引っ張っていってくれるんだろうな」と。

――でも、翌年には悠介さんが加入するわけですからね。
悠介:その時はそんなこと微塵も思っていなかったですね(笑)。
――(笑)。翌年には悠介さん自身が加入して4人体制となり、新体制初のリリース作品となるのが『a grateful shit』です。この作品から『THE AVOIDED SUN』に至るまでが、“lynch.らしさ”を確立する過渡期ともいえるのかなと個人的には思っているのですが、当時バンドのなかでどのような変化があったか、覚えていらっしゃいますか?
葉月:今作にはカップリングしか入ってないですけど、「roaring in the dark」、「enemy」、「forgiven」の3部作が大きかったと思います。それこそ「liberation Chord」や「I’m sick, b’cuz luv u.」のような、皆さんが“lynch.らしさ”だと思ってくれているきれいなコード進行にシャウトが入ってくる展開というのは、もともと「roaring in the dark」のBメロが始まりだったりもするので、その頃はいろいろな発見が多かった時期だったと思いますね。
――より“激しさ”に特化したバンドになりたいと作ったシングルが『a grateful shit』だったわけですが、そこにはどういった意図や心境の変化があったのでしょう?
玲央:激しい楽曲って、比較的短めの尺のものが多いじゃないですか。なので、悠介が加入して、イベントとツアーで全国をまわった時に持ち時間30分で、ほかのバンドはMC込みで5、6曲やっているところ、僕たちはMCなしで10曲ぶっ続けでやったんです(笑)。主催者さんからはちょっとイヤがられたし、お客さんからも「lynch.だけ尺が長い!」って言われたりして。でも、僕はタイムキーパーもやっていて、必ず29分30秒で終わらせていたので、そんなわけないんですけどね。
――ルール内でしっかりやっている、と。
玲央:単純に曲数が多いから、みんな「lynch.だけ長い!」って、それで僕たちの名前を覚えて帰るんです(笑)。それを狙っていたところもありました。短い時間のなかにどれだけエネルギーを詰め込めるかという意味合いでもあって。
――そんな当時のバンドのスタンスを表したのが『a grateful shit』で。悠介さんにとってはlynch.に加入してから初めての作品で、過去には「いつか録り直したい」という発言もありましたよね。
悠介:当時は自分にそこまでスキルがなかったのと、加入したばかりでこのバンドの体になっていなかったというのもあって、ジレンマや悔しさの残る作品ではあったので、それを払拭したいという思いはずっとありましたね。なので、ようやく20年経ってその機会をもらえて。願いが叶ってよかったです。