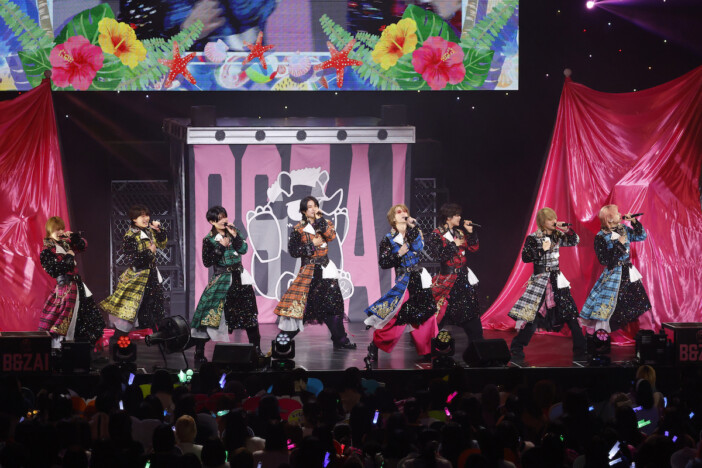G-FREAK FACTORY、新体制ならではのグルーヴ 守るための反骨心を貫いたツアーファイナル

G-FREAK FACTORYがいなかったら、ロックは、レベルミュージックは、ライブハウスはどうなってしまうのだろう? 2月3日、渋谷Spotify O-EASTで行われた『“RED EYE BLUES” TOUR 2023-2024』ファイナル。真っ先にそんな想いが頭をよぎるほど、堂々たるバンドの姿がそこにはあった。
もちろん、G-FREAKは27年間“堂々とし続けている”バンドなのだが、いつも以上にそのことを強く感じたのは、彼らをロックバンドたらしめている根っこの部分が、強烈に剥き出しになったライブだったからだ。すなわち、カウンター精神。コロナ禍という足枷が外れ、一見するとライブハウスシーンは自由になったように思えるけれど、そんな時こそ我先にと新たな重りを背負って、世の中と真正面から対峙し、中指を立てていくのがG-FREAKである。それだけ見過ごせないものが多すぎるということだが、時代が急速に移ろう中で、カウンターを貫き続けるのは相応の覚悟が伴うもの。しかし、そういうバンドが少しずつ減っていく中でも、G-FREAKは変わらずレベルミュージックを鳴らし、「お前はどうなんだ?」と直球で問いかけ続けてくる。何に抗い、何を守るのか。そんな覚悟が一層明確になったことで、G-FREAKの核が揺るぎないものであることを確信できるステージだった。

例えば「らしくあれと」を歌う前、茂木洋晃(Vo)はSNS上で次々に飛び交う言葉の刃に向かって「そんなに急いでどうする?」と疑問符を投げかけつつ、今この瞬間も苦しんでいる能登半島の人々に想いを馳せた。脅かす何かに抗うこと、我を通すことはすなわち、大切な場所を守ることと同義。群馬に腰を据えて活動してきたのも、誰かの故郷を同じくらい大切に思えるようになるという側面も大きいだろう。そうやって“守るために闘う”バンドがいることは、世の中がギリギリのところでグラつかない土台の1つになっていると思うし、〈いつもここにいるから 隠れないで帰ってこいよ〉と歌える心強さこそ、G-FREAKのエッジとハートがたぎっていることの証なのだと思う。

と同時に、ライブの始まりを告げた「RED EYE BLUES」がそうであるように、闘いを止めたらいつ〈骨抜き〉になってしまうかわからないから時代だからこそ、観客をアジテートしていく茂木の姿にも強烈な意志が宿る。ライブ中盤、楽器隊のダブセッションが渦巻く中、茂木が「こういうバンドが1つくらいいてもいいんじゃねえか」と語り、活動を始めた27年前を振り返って「島生民」につなげる流れがあったが、こうしてフラストレーションを吐き出すことでカウンターを打っていく姿勢もまた、G-FREAKの全く変わらないエッジの1つである。
とはいえライブがずっと張り詰めていたかというと、そんなことはない。「DAYS(#29)」のギターソロは細かいことを抜きにしても抜群に気持ちいいし、「日はまだ高く」や「EVEN」での軽やかなメロディラインと、愛を歌った切実な歌詞の大合唱は、何度聴いても胸を打たれる。ツアーを通してジャンプ力が上がったという吉橋“yossy”伸之(Ba)にほっこりした一方で、肋骨が折れたままライブに臨んでいるという原田季征(Gt)の気合いに客席もどよめいた。怪我はあったかもしれないが、こうして1本も欠けることなくツアーを完走できたことは本当に感慨深い。コロナ禍を経て、戦争や震災で次々と“当たり前”が奪われている2024年、G-FREAKのメンバーが揃ってステージに立っていることは、ささやかだけどかけがえのない奇跡なのだと改めて感じ入った。

昨年加入したLeo(Dr)の存在も大きい。他のメンバーと20歳近くも年の離れた彼が刻む器用かつアグレッシブなビートは、「REAL SIGN」や「Unscramble」などで特に際立っていて、明らかにバンドに新しい躍動感をもたらしていた。Leoの放つ若くてフレッシュな空気が、ドラマーの脱退・加入が相次いだG-FREAKの“新しい当たり前”を担うのは素敵だと思うし、若い世代の加入によって、G-FREAKのカウンター精神がより普遍的な説得力を帯びたことも素晴らしい。