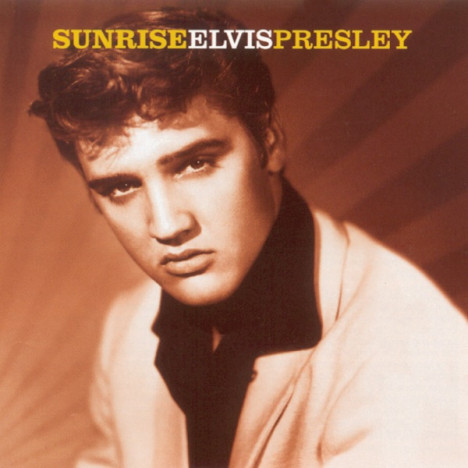『バビロン』暴力的な物語を加速させる“コントロールされた不協和音” 『ラ・ラ・ランド』との共通点も見える映画音楽を解説
映画『バビロン』のサウンドトラックが凄まじい。全48曲(日本盤ボーナストラック除く)、トータルタイム1時間37分。アイデアとバラエティに富んだ楽曲群が、ぎっしりと詰まっている。作曲を手がけているのは、『セッション』、『ラ・ラ・ランド』で知られるジャスティン・ハーウィッツ。監督のデイミアン・チャゼルとは、今回で5回目のタッグ。だがその音楽は、熟成による洗練ではなく、より派手で、より攻撃的で、より過剰なものになっている。第80回ゴールデングローブ賞で作曲賞を受賞、第95回アカデミー賞で作曲賞にノミネーションを果たしたのも、納得の仕上がりだ。
物語の舞台は、1920~30年代のハリウッド。サイレントからトーキーへと映画が大きな転換点を迎え、時代に取り残された者たちの栄光と転落が壮大なスケールで描かれる。『華麗なるギャツビー』などを生み出した作家 F・スコット・フィッツジェラルドは、狂騒と狂乱に満ちたこの時代を「ジャズ・エイジ」と呼んだ。まさに1920年代とは、デューク・エリントンやルイ・アームストロングといったジャズミュージシャンが台頭してきた時代でもあったのだ。
だが『バビロン』のサウンドトラックは、オーセンティックなジャズとは完全に一線を画している。もちろん、ベニー・グッドマン、グレン・ミラーのようなスウィングジャズでもない。トランペット、トロンボーン、サックスのホーンセクションがパーカッシブな音を吹きまくり、ラテンのリズムがそれを下支えするような、現代のパーティーミュージックとでもいうべきサウンドなのだ。
ジャスティン・ハーウィッツは、作曲の参考にと作成したデイミアン・チャゼルのプレイリストに、1920年代の音楽が全く入っていなかったとコメントしている。そこに収録されていたのは、1990年代のダンス・ミュージックや、1960年代のジャズ。あえて時代性を無視することで、カオスに満ちた『バビロン』の熱気を表現しようとしたのだ。むしろ彼が参考にしたのは、ロックンロールだったという。
「The Rolling StonesやAC/DCのようなロックバンドからインスピレーションを得て、リフをベースにした曲作りをたくさんしました。 彼らの曲はエレキギターで弾くリフを中心に書かれていますが、そのリフをユニゾン・ホーンに任せることで、20年代ジャズのような軽いスタイルとは異なる、筋肉質な音楽になっているんです」(※1)
さらにジャスティン・ハーウィッツは、ひとつのトラックに異なるテンポやキーを重ね合わせる実験も行なっている。“コントロールされた不協和音”が、全編に散りばめられているのだ。混沌としたサウンドは、デイミアン・チャゼルがこの映画で目指したものとジャストマッチしている。“史上最年少オスカー監督”という肩書きを脱ぎ去り、スマートで洗練された物語を放棄し、とにかく野蛮で暴力的な映画を撮ろうとしたはずなのだから。