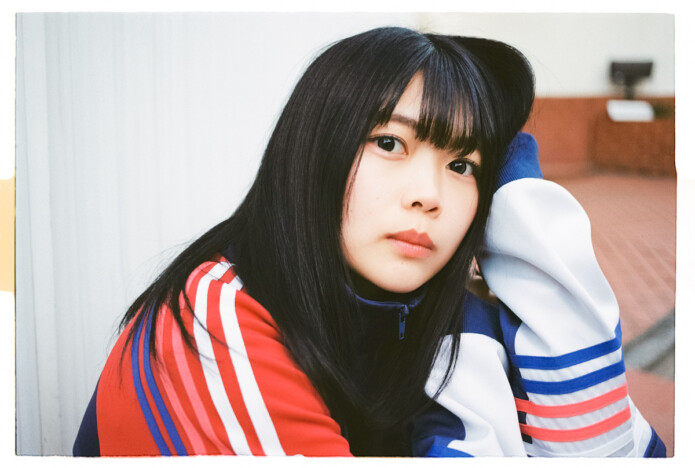Yogee New Waves、未来への希望を音楽に託す意味 バンドの信念を貫いた、初の日比谷野音ワンマンライブ

その場所で鳴らされる音はどこまでも正直だった。Yogee New Wavesが初めて日比谷野外大音楽堂で開催した一夜限りのワンマンライブ『Yogee New Waves Special Live “SPRING WAVE”』だ。昨年10月にリリースされた最新アルバム『WINDORGAN』は、『PARAISO』『WAVES』『BLUEHARLEM』と続いてきた「島三部作」に区切りをつけ、現代を生きるこの瞬間の逡巡や未来への思いがリアルに描かれた1枚だった。その気分がこの日のライブには溢れていたのだ。野音という、これまで数々のロックミュージシャンが伝説を残してきたステージは、どんな会場よりも、そこに立つアーティストの人間力を生々しく炙り出すように思う。Yogee New Wavesにとって初めての野音もまた、彼らが貫いてきた信念、築き上げたアイデンティティ、音楽に託す情熱と希望がダイレクトに伝わってくる一夜だった。

17時半。浜辺に打ち寄せるさざ波の音が会場に響きわたるなか、角舘健悟(Vo/Gt)、竹村郁哉(Gt)、上野恒星(Ba)、粕谷哲司(Dr)が現れた。4人が向き合い、一斉に音を鳴らした瞬間、ステージから光が溢れた。1曲目は「Hello Ethiopia」。2014年のアルバム『PARAISO』に収録されたスローナンバーでゆっくりと幕を開けた。そのポストアポカリプスを想像させる詞世界で紡がれるのは〈平和を願った夜もあった〉というフレーズだ。意図したわけではないかもしれないが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻によって世界が緊迫する今、この曲をオープニングに置いたことには何か言葉では言い尽くせない意味があるような気がしてならなかった。角舘と竹村によるツインギターが繊細に絡み合い、「楽しんでいこう!」と呼びかけて突入した春を待つ歌「You Make Me Smile Again」から、粕谷が繰り出す軽快なビートが爽やかな風を巻き起こした「White Lily Light」、角舘の「オンベース、恒星ー!」を合図にふくよかなベースが弾んだ代表曲「Ride on Wave」へ。開演と同時に総立ちになった客席は、はじめは少し遠慮がちに、次第に音楽に合わせて自由に体を揺らす、素敵な空間ができ上がっていった。

天然の舞台装置=野音を最大限に生かすべく、この日は二部構成のライブだった。とはいえ、一部と二部が均等というよりも、どちらかというと一部はプロローグのような位置づけだろうか、テンポを落とした曲が多かった。パーカッションの松井泉とキーボードのgomesを迎えた6人編成で柔らかなまどろみを生んだ「Good Night Station」のあと、「CAN YOU FEEL IT」では躍動感のあるドラムに乗せて、角舘が何度も〈CAN YOU FEEL IT?〉と問いかけた。感じることができているかーーそれはYogee New Wavesの音楽を紐解くキーワードだと思う。その問いに答えるように、思い思いに感情の高まりを表現する客席を見渡して、角舘は「それで合ってるよ」とでも言うように、サムズアップのポーズを見せた。一部のラストは暮れゆく時間帯にぴったりな「Toromi Days」と「Sunset Town」で終演。その頃には、あたりはすっかり薄暗くなっていた。