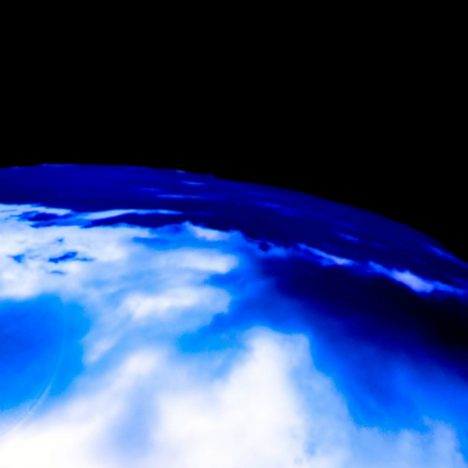GEZAN マヒト、踊ってばかりの国 下津光史が持つ言葉の訴求力 「現実から未来を想像させる」詩人たちの歌
歌は世につれ、世は歌につれ。この言葉は今も有効だろうか。
いよいよキナ臭い世界情勢。跋扈するレイシスト。痛みばかりの増税。テレビを見れば正直者の告発もトカゲの尻尾切りで、ひとつの失敗を徹底的に吊し上げて叩く芸能界ーー。個の繋がりをスマホに求めても、そこはもう正義警察の監視社会。多様性が大事と言いながら、噴出する問題は解決されぬままタイムラインを流れ去っていく。ふと顔をあげた電車の中では、周囲への苛立ちを隠せないストレスの塊たちが揺られている。
そんな世相を歌にしてどうする、と言ってしまえばそのとおり。だからポップミュージックは肯定する。麻痺したように肯定を続ける。大丈夫、前に進める、未来はきっと一一。現実がこうだから音楽くらいはきれいな夢を見せなきゃいけないのだろう。ただ、そのセオリーはどこか空虚で、現実を見れば若者たちが無邪気に夢を語れない時代である。
ここでは、そんな音楽からきっぱりと距離を置いたミュージシャンたちの話をする。踊ってばかりの国とGEZAN。ともに大阪・難波BEARSで関西ゼロ世代のカオスを見ながら育ってきた同世代バンドだ。2010年代に本格始動、いくつかのレーベルと手を組みながらも、結局はそれぞれ自主で独立。前者はサイケデリック/歌もの、後者はオルタナティブ/パンク。音楽性は異なるけれど、時流を無視した動きやフロントマンのカリスマ性は妙にシンクロする。そして、2020年の幕開けとともに彼らから素晴らしいアルバムが届いたことが、いま音楽ファンの間で話題となっている。踊ってばかりの国『私は月には行かないだろう』と、GEZAN『狂(KLUE)』である。
繰り返すが音楽性は違う。ただ、下津光史(Vo/Gt)とマヒトゥ・ザ・ピーポー(Vo/Gt)、二人の詩人にスポットを当ててみると視点はかなり近い。「夢を見せる」常識に背を向けた彼らの歌は、「現実から未来を想像させる」一点において、とてつもない訴求力を発揮するようだ。

新作から一曲ずつ引用しよう。踊ってばかりの国の「サリンジャー」。〈未だに人間は争い/未だに僕らはそれらを止めれない〉と冷静に書く下津は、反戦を声高に叫ばない。〈せめて世界は愛のために廻るべきなの〉と理想を描きはするが、プロテストソングの方向に筆が進むことはない。結局彼の目に映るのは〈今日も空はただ深いです〉。これだけなら、やれやれ、と村上春樹が出てくるところだが、面白いのは彼が自分をちっぽけで無力な存在と認識している様子がなく、人の一生そのものを、すべて小さな点と捉えていることだ。
〈種がいつか花になり〉〈川がいつか海になり〉。一曲の中でどんどん飛躍していくイメージ。長い目で見れば命は一瞬。長い目で見ても人はずっと争い続ける。だったら想像してみよう、と子供に諭すように下津は歌う。〈すれ違う一人一人 名前があり 花束抱いて生まれ〉。かくも小さなことを意識するだけで他人への意識は変わるだろう。ささやかな希望を込めるかのように歌はこう幕を閉じる。〈飛び跳ねれば宇宙にだってなれるよ〉。宇宙一一それはあなたのイメージによっていかようにも変わる未来のことだと思う。