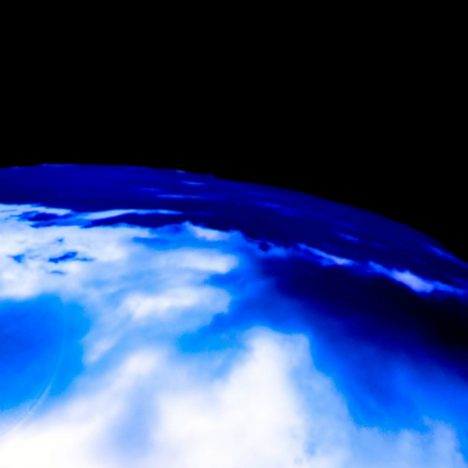GEZAN マヒト、踊ってばかりの国 下津光史が持つ言葉の訴求力 「現実から未来を想像させる」詩人たちの歌

GEZANは「東京」を取り上げよう。〈今から歌うのはそう/政治の歌じゃない〉との前置きから始まるマヒトの歌は、〈戦争/銃声が聞こえるだろう〉と近未来的なイメージを絡めつつ〈新しい差別が/人を殺した朝〉〈誰も幸せな人はいないのにさげすみあってるループ〉と街の景色を生々しく掬い上げていく。ただ、やはり彼も反戦・反政府と旗を掲げることはしない。ひたすら息苦しい現実を掻き消すように〈想像してよ〉と叫ぶのだ。
強烈なのは後半。歌の冒頭に戻るように〈政治〉という言葉が再度出てくる。そこから浮かぶのは首相や大統領の〈dirty faceではなく〉、〈花を見て笑う/好きな人の顔であるべきだから〉。これまた非常にささやかで具体的な想像力。みんなにそれができれば何かが変わるだろうか。問いかけを繰り返しながら最後は〈答えを聞かせて?/東京〉。東京一一これもまた、聴き手の想像力によっていくらでも変わる未来の暮らしのことを指しているはずだ。
そういえば、マヒトへの取材中に偶然下津の名前が出てきたことがある。「あいつたまにいいこと言うんです。感心したのは〈ロックバンドが責任感なんか持っちゃダメだ〉ってこと。今の世の中と逆行してますよ。どんな発言にも責任が伴う世の中で」。そう笑ったあとマヒトは自分の言葉を重ねて言った。「音楽なら空だって飛べる。〈責任なんか持つな〉っていう言葉には、その後ろに〈空を飛ぶために〉がくっついてくるんですよ」。
旧作の話になるが、踊ってばかりの国にも「東京」という曲がある。なんてことのない様子で〈政治家のジジイが決めたことで また子どもが死ぬよ〉と歌う下津はさすがに不謹慎、無責任な印象を与えるのかもしれない。新作で過激なアジテートを繰り返し、〈すべての構造を この場所で破壊する〉と叫ぶマヒトも然り。二人の詩人はシビアな現実を見据え、まずは過激に言いたいことを言う。だがそれ以上にデカい看板は掲げず、何かを引き連れようとする様子もない。ただ目の前にいる他者の存在に気づかせ、ささやかな想像力を使おうと提唱する。それこそが空を飛ぶための、花を咲かせるための、最大の抵抗だと言わんばかりに。
ロックが反体制、革命の音楽だったのは60〜70年代の話だ。その幻想をなぞったところで有効であるわけがなく、革命など起きようもないくらいグローバル社会は管理されきっている。そもそも革命とは何か。「アラブの春」を筆頭に、それが人類に素晴らしい変化をもたらすとは言えない現実を、我々はすでに知ってしまった。八方塞がりで無邪気に夢も革命も語れない時代に、刺さるほんとうの歌とは何だろう。
〈僕らは幸せになってもいいんだよ〉(GEZAN『Silence Will Speak』収録「DNA」)。
〈あなたは自由よ/誰も君を笑わないよ〉(踊ってばかりの国『私は月には行かないだろう』収録「バナナフィッシュ」)。
歌は世につれ、世は歌につれ。この歌詞を見るたびに世相を感じる。こんな時代に、これだけ美しく空を飛んでみせる詩人がいてくれて良かったと思う。2020年のインディシーンは面白い。肯定を続ける音楽が見せる夢とは違う未来がある。
■石井恵梨子
1977年石川県生まれ。投稿をきっかけに、97年より音楽雑誌に執筆活動を開始。パンク/ラウドロックを好む傍ら、ヒットチャート観察も趣味。現在「音楽と人」「SPA!」などに寄稿