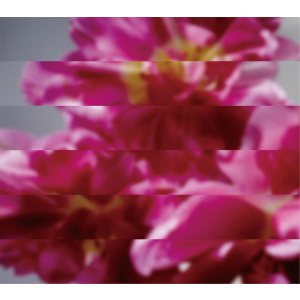MONDO GROSSO『何度でも新しく生まれる』 大沢伸一×谷中敦 特別対談
大沢伸一×谷中敦が明かす、満島ひかりとの「ラビリンス」制作秘話「このテイクが一番“歌っていない”」

谷中「時代が変わった時も、新鮮な音楽だと感じられる」

ーー確かに、そういう歌詞ですね。(スカパラとして)デビューは谷中さんの方が先ですけど、谷中さんの目からは、これまでの大沢さんの活動はどのように映っていましたか?
大沢:難しいですよね、本人を目の前にして(笑)。
ーーいくらミスター・リップサービスと言えど?
谷中:いや(笑)、これはリップサービスでもなんでもなく、カッコいいことしかやってこなかった人だと思うんですよ。
大沢:いやいやいや(笑)。
谷中:今回のアルバムにしたって、全然ブレてない。時代が変わっても、やりたいことがずっと変わってないっていうか。自分の音楽を真空パックに入れたまま、ずっとやり続けているような。だから、時代が変わった時も、新鮮な音楽だと感じられるんですよね。大沢くんは変わってないんだけど、周りの風景が変わったことで、それが新しいものに見えてくるっていうか。時代に合わせていると、どうしたって時間が経つとそれが古くなってしまうけど、大沢くんみたいにずっと独自のことをやってきた人は、時代を超えていくんだなって。
ーーそれを、流行り廃りが激しいダンスミュージックの世界、エレクトロニック・ミュージックの世界でやってきたっていうのが、大沢さんの音楽の稀有なところですよね。
大沢:もちろん、リズムだとか、音楽のフォーマットだとかは、その時代時代のものを好きに取り入れていいと思うし、自分も部分的にはそうやってきたんですけど、やろうとしてることの根幹みたいなものは、ずっと変わってないのかもしれませんね。それに、今ってもう「何が新しいのか?」って誰も言えなくないですか? 例えば、昨年出た作品の中で、自分がすごく好きだった作品の一つがBADBADNOTGOODってカナダのジャズバンドの『Ⅳ』ってアルバムだったんですけど。
ーーあぁ、ケンドリック・ラマーの『DAMN.』にも参加してましたね。
大沢:そうそう。あの作品で彼らがやってることって、70年代のスピリチュアルなラウンジ・ジャズの完全な模倣でしかないんですよ。それの、めちゃくちゃクオリティの高い模倣。でも、彼らの音楽って、言ったら「最新」のものでもあるんですよ。最新の技術で昔の音楽を再現していて、自分はそれを最新の音楽として聴いている。そういうことを考えると、もう音楽として「何が新しいのか?」なんて、意味がないような気がするんですよね。今回の自分の作品もレビューで書かれたりしたんですよ。「なんかちょっと古臭い、90年代みたいな曲を今さら作ってる」みたいな。そういうのを目にすると「ふざけんなっ! ボケっ!」とかって思いますけど(笑)。
ーー(笑)。
大沢:でも、ある意味、その通りなんですよ。別にこの作品は90年代に出ていてもおかしくなかった。でも、それを作ってる自分は現在のーーこの作品を作ったのはほぼ2016年だからーー2016年の気分で、2016年の機材を使って作ってる。それはやっぱり、新しい音楽なんですよね。90年代にあったような音楽のフォーマットでも、新しく聴こえる部分はあるはずなんですよ。僕が「新しさ」について考えていなくても、それは自然に新しいものになっていく。

ーー自分の中でMONDO GROSSOの音楽って、一貫してどこか叙情的で、ドライかウェットかって言ったらウェットで、日本という、地球温暖化もあって今やほとんど亜熱帯地域といっていいこの風土の中でしか生まれない、高温多湿なダンスミュージックという認識があるんですよ。
谷中:うんうん。
大沢:使わせてもらいます(笑)。
ーーいやいや(笑)。
谷中:でも、本当にそうだよね。

ーーで、今回のアルバムを最初に聴き終えてふと気づいたのは、すごく多彩なトラックで、それでも全部日本語で、全部歌もので、「そっか、ラップも一切入ってなんだ」ってことで。もし今の世界の音楽シーンをもっと反映させるなら、そこにラップの要素って入ってきそうなものですけど。そこで敢えて「歌」オンリーっていうのが、すごくMONDO GROSSOっぽいなって。
大沢:あぁ、言われてみるとそうですね。うん、そうとしか言えない(笑)。
谷中:そもそも、今回どうして日本語にこだわったの?
大沢:きっかけは本当に谷中さんに書いてもらった「ラビリンス」だったんです。その前から漠然と日本語でいきたいなっていう気持ちはあったんですけど、「ラビリンス」を日本語でいくって決めた段階で、だったら全部日本語でいこうって思った。その前に作っていたデモは、もうちょっとカッコつけてたんですよ。この10年間に自分がDJとして培ったものをフィードバックさせて、今一番自分がピンときている最新のスタイルを打ち出していこうとか。でも、よく考えたらそれって、今の自分にとって挑戦じゃなくて逃げだったんですよね。せっかく14年ぶりにMONDO GROSSOとしてアルバムを作るなら、自分にとって最も負荷の高いものを作ってみたくなった。それが、全部日本語でいくっていうことだったんです。
谷中:「ラビリンス」がきっかけになったっていうのは、本当に光栄ですね。やっぱり、いい曲だよね。いまだに1日1回は聴いてるもん。そういう曲に関わることができて、本当に幸せですよ。