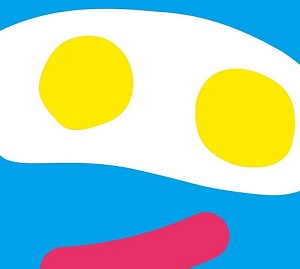金子厚武のプレイヤー分析
Analogfishと新世代ポップバンドの接点とは? 新作アルバムの独自性を探る
Analogfishが前作『最近のぼくら』から11か月というバンド史上最速のインターバルで、新作『Almost A Rainbow』を発表した。今年の彼らは上半期にYogee New Waves、下岡晃と斉藤州一郎の別バンドであるelephantでAwesome City Club、つい先日はtofubeatsと、いわゆる「新しいシティポップ」に括られる若手との2マンを数多く行ってきた。
もちろん、この「シティポップ」というジャンル名は完全に流行り言葉となっていて、若手のポップスに対しては何でもかんでもラベルのように貼られている状態であり、その中にはオリジナルの「シティポップ」とは似ても似つかないものも数多く含まれている。ここで改めて「新しいシティポップ」を定義すれば、それはアメリカをはじめとした海外の音楽シーンにおけるブラックミュージックの復権を背景としながらも、それを日本語のポップスとして鳴らす若手の音楽だと言える。そして、Analogfishというバンドはこれまでも常にアメリカのインディロックを中心に海外の音楽シーンを意識しながら、日本語のロック/ポップスを作り続けてきたバンドであり、彼らとのリンクが生まれるのも自然な流れなのだろう。
近年のAnalogfishの楽曲は、ループを基調としたミニマルなアンサンブルが大きな特徴になっている。この方向性は2010年に発表された『Life Goes On』に収録されている“平行”あたりから顕著になり、2011年の『荒野 / On the Wild Side』、2013年の『NEWCLEAR』という流れで、さらに突き詰められていった。ただ、震災・原発事故以降に発表されたこの2作は、名フレーズ〈失う用意はある?それともほうっておく勇気はあるのかい〉を持った“PHASE”や、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文をはじめ、多くのミュージシャンやリスナーからの称賛を集めた“抱きしめて”など、下岡のメッセージ性の強い歌詞が重要視されていて、ループ主体の楽曲というのは「言葉を強く印象付けるために、演奏はシンプルに」という方向性の表れでもあった。
しかし、前作『最近のぼくら』においては、「ループを基調としたミニマルなアンサンブル」をよりフィジカルに、有機的に演奏する方向性へとシフトし、それがより突き詰められたのが『Almost A Rainbow』なのだと言える。この背景には、ジェームス・ブラウンのバックバンドであるThe JB’s、さらにはMetersといった往年のファンクバンドに対する下岡の憧憬があり、さらには前述した通り、近年のアメリカのインディシーンにおけるブラックミュージックの復権がある。前作から今作にかけて、彼らがインスピレーション源として挙げているのは、BADBADNOTGOOD、Toro Y Moi、The Internetといった名前で、それぞれがジャズ、R&B、ソウルなどと強い接点を持ちながら、それを独自のサイケデリックな音像で鳴らすアーティストたち。こうした影響を消化しつつ、やはりあくまで日本語のロック/ポップスとして鳴らしているのが、『Almost A Rainbow』なのだ。