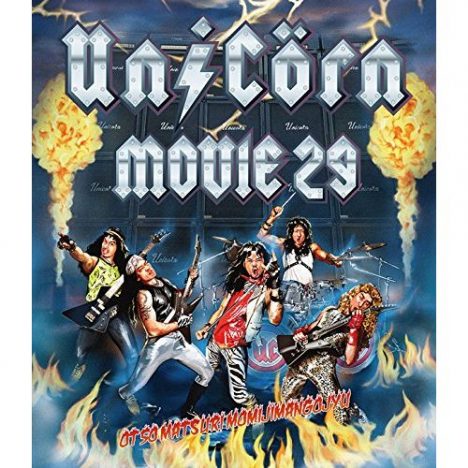『メロディがひらめくとき アーティスト16人に訊く作曲に必要なこと』発売記念対談
沖井礼二と黒田隆憲が語る“ポップスの暴力性”とは?「気持ちいいところは過剰にした方がいい」
リアルサウンドでも楽曲分析記事を執筆するライターの黒田隆憲氏が、9月18日に書籍『メロディがひらめくとき アーティスト16人に訊く作曲に必要なこと』(DU BOOKS)を上梓した。
同著では黒田氏が、Galileo Galilei、tofubeats、Maika Leboutet、AZUMA HITOMI、sugar me、Predawn、小林祐介(THE NOVEMBERS)、kz(livetune)、コンピューター・マジック、まつきあゆむ、OLDE WORLDE、三浦康嗣(□□□)、Crystal((((さらうんど)))、Traks Boys)、沖井礼二(TWEEDEES)、宮崎貴士(グレンスミス、図書館)、冨田ラボといった16組のアーティスト・ソングライターへ、作曲についてインタビューを行っており、彼らが普段どのように楽曲と向き合い、メロディを作り上げているのかが語られている。今回リアルサウンドでは、同著の発売を記念し、黒田氏と沖井礼二氏(TWEEDEES)による対談を企画。世代や価値観などに共通点のある2人に、メロディの作り方や“沖井っぽい曲”、“ポップスゆえの暴力性”などについて、大いに語ってもらった。
「持っている絵筆の数はそんなに多くない」(沖井)
――同年代のお二人、音楽面の共通項とは?
黒田隆憲(以下、黒田):沖井さんも僕もビートルズをはじめとする60年代のものを好むなど、文化圏が同じなんです。僕は途中でミュージシャンからライターになりましたが、同じくらいのタイミングでCymbalsのデビューがあったり、他にも人生におけるターニングポイントの多くが似ていました。過去にミトさん(クラムボン)と沖井さんの対談で司会進行をさせていただいたことがあるのですが、3人ともベーシストだったので、「レコーディングで宅録していて、一番最後にベースを入れる」という点が共通したり、「ポール・マッカートニーも同じようなことをやっていた」といった話で盛り上がりました。
沖井礼二(以下、沖井):そんな境遇の一致のせいか、みんなカッコいい感じにインタビューされているこの本においても、僕だけは黒田さんと人生観を語っているみたいになっていて(笑)。まあ、実際はほかの皆さんみたいに機材があまり得意じゃないというか…興味がないからというのもあります。基本的には「この曲を作るのに何が必要か」を考えて、最低限のものを揃えるくらいで、『Garage Band』があればいいという結論にしかならないですから。
――著書のなかで語られていることでもありますが、沖井さんはどのようにして作曲法を身につけていったのでしょうか。
沖井:最初は作曲というより、中学生時代にダブルカセットを使って遊んでいて、それを弟に聴かせるところから始まっているんです。高校時代は失恋や水球のレギュラー落ちなど、悲しい出来事があり、その隙間をセックス・ピストルスが埋めてくれて……(笑)。彼らのことを教えてくれたベーシストの友人からベースを借りて、曲作りの手法を真似したところから作曲がスタートしました。そこからとくに、何かが大きく自分の中で変わったという意識はありません。音楽を始めてからしばらくバンドを組まずに、自宅で自分のレコードを流しながら、それに合わせてベースを弾いていたのですが、ビートルズの曲でポール・マッカートニーが弾いているベースラインを聴きながら「こっちのほうがいいんじゃないか?」と思いついて録音したり。そこからメロディー制作にも興味が湧いて、頭の中でなっている和音をどうアウトプットするかという曲作りを身に着けたのですが、一人で弾いてるだけだったから、「バスドラのキックに合わせて弾かなきゃいけない」みたいなことも2年くらいはわからず、ベースは低音で主旋律に対してカウンター・メロディーを奏でる楽器だと勝手に思っていたんです。
黒田:ラジオで流れているような音楽を聴いて、鼻歌で歌っているうちに、イントロや間奏で「このメロディーよりも自分が今考えているメロディーのほうが面白いのかもしれない」と思うことって、よくあったりしますよね。
沖井:「思いついちゃったんだから実践してみたいじゃん」という考えになったことで、より創作意欲が強くなりましたね。あと、プラモデルが好きな子供だったのですが、あれはメーカーが用意したものをどれだけ綺麗に作るかというもので。でも音楽は「自分が作った」と言えるもので、創作欲と所有欲の両方を満たせるものだから、それがまた性に合ったのだと思います。
黒田:最初に曲を作った時って、自分で「良い曲だなあ」と思いましたか? それとも、思ったより良くなくて落ち込みましたか。
沖井:最初は遊びという気持ちが大きかったし、デビューしてからしばらくの間までは、世間一般で流れているポップミュージックに太刀打ちできるなんて思っていませんでした。そのうち、プロとしてデビューしたからには、尊敬している音楽家も商売敵になるわけなので、世に出して恥ずかしくないものを作っていかなければという自覚はするようになりましたよ。
――沖井さんはCymbalsでの活動や、ソロとしてFROG、現在は清浦夏実さんとタッグを組んでTWEEDEESと、いろんな形で音楽を作っていますが、それぞれにおいて使うチャンネルは違いますか。
沖井:そういうスイッチみたいなものはあまり意識していませんが、持っている絵筆の数はそんなに多くないですし、あまり数を増やそうとも思っていません。洋服の仕立て屋に近いというか、自分の感覚でもってその人にどこまで似合うものを作るかという発想ですね。それはCymbalsのときも同じで、バンドから発注を受けて作っている感覚でした。だからこそ、ソロ活動は自家中毒を起こしたような感じになって、難しいなと思ったんです。
黒田:それって、沖井さんが自分で歌わないからというのもあるかもしれませんね。
沖井:そうかもしれません。
黒田:あらかじめボーカリストが決まっているユニットなら、そこでの自分の役割も明確になりますが、ソロの場合は自分が歌うべきか、誰かに歌ってもらうべきかを決めなければならない。そして、そこでどのボーカルでも選べるとなったときに、だれにするかというところで方向性が決まる。
沖井:例えばこの本でも冨田恵一さんなんかは、本当に上手なボーカル選びをしているなと。
黒田:そういう意味では、自分で歌えて曲も作れる方って、自家中毒的なものはあまりないと考えてもいいのでしょうか?
沖井:作家としてソロで活動している人と、歌えるけど曲も作る、という人では、意味合いが違うでしょうね。歌える人たちはフィジカルを使った表現に慣れているから、バンドの中であっても、自作自演のボーカリストに関しては、ソロと違わないつもりでやっているのかもしれない。
黒田:そういう人は楽曲提供をするとなったら、スイッチは換えやすいのでしょうか? 例えば、自分でいつも歌っているから、バンドをやっているときは自分が歌うけど、何か他人に作品をつくるときは自分が歌わないから、そこでスイッチを切り換えられる、みたいに。沖井さんはずっと常に誰かの歌を作曲しているから、ソロも楽曲提供もスイッチが切り替わらないと思ったのですが。
沖井:そういうのはあるかもしれませんね。ある友人が「こういう曲を作ろうとしている」とデモを聴かせてくれたことがあったのですが、その時点では主旋律がまだ歌になっていなくて、楽器の音だけガイドで入っていたんです。それを聴いてそのメロディを疑問に思っていたのですが、歌が入ったものを聴いたら、ちゃんとカッコよくなっていて「この段階で、ここまで考えてメロディーが作られているんだ」とショックを受けました。でも、そんな彼が誰かほかの人に曲を書くなら、そのアーティストに伝わるように翻訳する作業が必要になるから大変だな、とも同時に思いましたね。
黒田:自分で歌って聴かせることができないからこそ、沖井さんのメロディーはカラフルになっていった、ともいえますか?
沖井:はい、意識している部分ではあります。
黒田:何の楽器に置き換えてもいいメロディーになるのが、沖井さんの特徴ですよね。ビートルズにおいてジョンとポールの楽曲を比べると、ジョンの曲って少ない音数をシンプルに並べて、クレッシェンドやベント、歌い方や節回しでニュアンスを出している曲が多いですが、ポールは色々飛び回っていて。
沖井:「I Am the Walrus」(レノン=マッカートニー名義だが、実質ジョン・レノンが作曲したもの)とかは、シンプル過ぎてスーパーの食品売り場みたいな音で聴いても、何かわからないですからね(笑)。そういう意味で、僕の曲はポール的といえるのかもしれません。ただ、人間の声は一番強い楽器だと思っているので、それを自分が使えないのは残念ではありますね。
黒田:ちなみに、清浦さんに渡す際には、メロディをどこまで作りこんでいるのでしょう。
沖井:最初はエレピみたいな音でガイドを入れますね。僕が歌詞を書く時もあれば、彼女が書くときもありますから。その段階で仮歌を一回録って、ああでもないこうでもないと微調整をしたあと、スタジオに持ち込んで本番を歌う、という流れが基本です。
黒田:その微調整は、節回しやメロディーに対する言葉の当て方などが基本的なんですか。
沖井:あとは「ここはビブラートなしね」とか。このあたりはスタジオへ持ち込む前段階で、ある程度決めてしまいます。
黒田:沖井さんの頭の中で鳴っている音と、清浦さんの仮歌ではどのくらいの誤差がありますか?
沖井:結成時から、やり方が定まるまでは大変でした。清浦は歌が上手く、色々な歌唱法を使えるからこそ、“清浦らしい歌い方”をまだ発見できていなくて。でも、やっていく中で「頭で考えて演じるのではなく、一番気持ちいい声で歌うのが合っている」と確信したので、そこからはスムーズになりました。
黒田:では、今の沖井さんは、清浦さんに合いそうなメロディーを作っているし、清浦さんはそれを自分なりに解釈してポイントを見つけていると。
沖井:そうですね。TWEEDEESには「ブリキの思い出」という曲があって、これは曲と同時にタイトルを伝えて歌詞を書いてもらったのですが、ブレスのタイミングまでしっかり考えて完璧に歌詞を作ってきたし、思った以上に彼女らしくなった。そのときは目からウロコが落ちるくらい安心感がありましたね。
黒田:その辺、Cymbalsのときと比べるとどうですか?
沖井:あの頃はパソコンで作業することが少なかったので、メロとコード、あと少しだけリズムを作って、歌詞を書いていました。それをスタジオに持ち込んで、セッションっぽく仕上げていった感じですね。最初は自分の頭の中にあるものを伝えるボキャブラリーも不足していたし、ボーカルディレクションもやらせてもらえなかった。でも、他のエンジニアさんやプロデューサーさんが作業しているのを見て、色々学んだ結果、『Higher than the Sun e.p.』以降は自分がディレクションを手掛けることになりました。ここでの経験は、その後の活動にかなり活きていると思います。