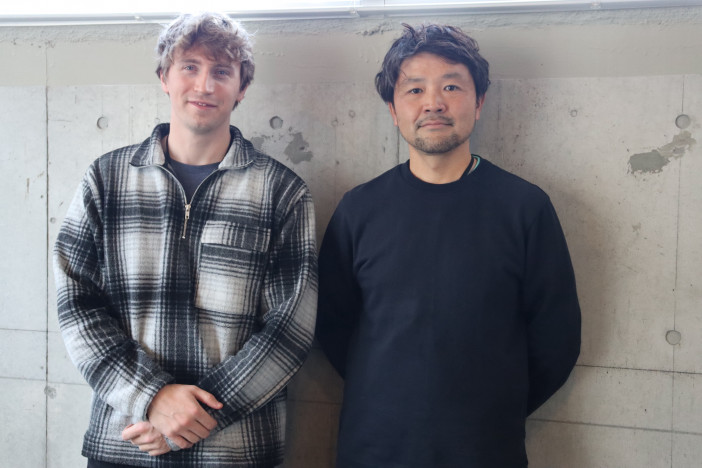アーティストは「AI以降の人類」に期待していいのか 渋谷慶一郎×岸裕真が語りあう“生成AIとの理想的な関係”

AIに期待するのは「人間を超越すること」

岸:渋谷さんにお聞きしてみたかったんですが、僕と渋谷さんの大きな違いとして、僕は展示をオープンしたら、基本的に会場にはおらず、作品が自立して観客に語りかける。一方で渋谷さんの『Scary Beauty』や『MIRROR』などの舞台では、その場でオルタと渋谷さんだったり、オーケストラのメンバーだったりとの関係性を見せていく。以前、映画監督の長久允さんが僕の作品を見たとき、「岸くんはAIとセックスしてるんだね」とおっしゃって。長久さんは僕の制作スタイルを「肉体という媒介を通して他者と交流しながら一つの作品=子どもを産み出す行い」としてセックスにたとえたんだと思うんですが、渋谷さんの制作はセックスというよりも恋愛関係のほうが近いのかなと思いました。実際に制作されていて、いかがですか。
渋谷:よく言われます。「僕が即興で弾くピアノの音にオルタが反応して歌う」というパフォーマンスをよくやるんですが、これは特に見ていると恋愛やセックスみたいだと言われます。この形式でやると、オルタがどう歌うのかはコントロールできない。だから自由に即興しているように見えて、オルタについていくのも大変なんです。しかも、即興のピアノが「いい感じだな」と思ってる時は、たしかに歌も良くなる。でも、ちょっと惰性で弾いてるとか、繋ぎで弾いちゃってるときは、途端に歌も駄目になる。かなり調教しながら弾く感じがあるから、セックス感が強いかもしれない。
ーーそうした即興演奏において、アンドロイドに「身体性」を感じることはありますか。
渋谷:身体性は感じますね。アクシデントや事故が背後にあることを知っていると、人間は身体性を感じるんだと思う。だから「絶対、正確で安全なロボット」には身体性を感じないと思う。テクノロジーとかアンドロイドが予期しないエラーを起こすときに、身体性を感じますよね。ドバイ万博で即興演奏をした際、本来終わるはずのタイミングでアンドロイドの発する最後の1音が30秒ぐらい延びちゃって、予定通りに終わらなかったんですよ。次の曲のイントロもすでに鳴っているのに、前の音が伸びている状態で、やばいとは思ったんですが、でも、こういうのは興奮しますよね。
岸:あらかじめ規定されたプログラムを超えるエラーやタブーのような挙動は、作家やアーティストからすると歓迎できるし、そのタブーを起点にして創作が広がる感覚があると思うんです。タブーって基本的に犯してはいけないものですが、それをある種演劇的に「AIがやっちゃったんだよね」と無邪気に言えるのは自分の制作の中でも起きることで、とても面白いと感じます。
渋谷:それはちょっと俯瞰して見るといまっぽいというか、20年代っぽいと思う。というのは90年代〜00年代には「エラー」という言葉はめちゃくちゃ流行ったし、特に僕は複雑系科学研究者の池上高志さん(東京大学大学院情報学環・教授)と共同研究を始めたのが00年代だったからその只中にいたし音楽と結合させることで色々なことが出来た。彼は92年に「テープとマシンの共進化」という論文を書いていて(橋本敬と共著)、それはDNAをテープに、タンパク質をマシンにたとえて、これらの相互作用が生命を進化させてきたという前提のもとで、テープが自己を複製するループ状態を作り、この自己複製中に意図的に外部ノイズを与えると複雑なネットワークが生まれて、突然変異が起きる、「外来製の原因で生じる複製の不正確さが、安定な自己複製ネットワークを”進化"させる」ということを言っている。つまりなんらかのエラーとかバグが進化を爆発的に促進するんだということで、当時この論文はとてもエキサイティングで話題になったんです。カールステン・ニコライ(alva noto)もこの論文にすごく影響を受けていて、初めて日本に来たときは池上さんの研究室を訪ねたらしい。
だから「エラー」という事象はそれからもずっと鍵になっていて、ノイズ・ミュージックのように非常に抽象的な、抽象性がフルに発揮された音楽が「エラー」によって新たな局面を迎えたんだけれど、こうした抽象性の力が弱まっていったのが10年代から20年代だと思う。特に最近の音楽はヴォーカル以外にも人の声がすごく中心にあるじゃないですか。ビートでサンプリングされて使われてる音も人の声だらけですよね。つまりノイズのような抽象性よりも声のような具象性を溢れさせる方向に向かっている。それは多分、すごく安易に言うとインターネットの普及で情報が増えたから、人々が抽象的なことにかまう能力が落ちたというか暇がなくなったとも言える。そして今は具象的・記号的なことのなかに抽象性も見出すし、より高度に具象的な戯れに浸っている段階だと思うんですよね。
陰謀論が流行するのもそういう理由でしょう。陰謀論って要するに記号性の極致で、名前とか場所の羅列がやたら多い。しかも世界は陰謀でできているから、陰謀論が支持されるのは仕方ない(笑)。そういう時代のエラーっていうことで言えば、ChatGPTの書くもっともらしい嘘が話題になったり、AIを間違ったデータセットで学習させてみたりした先にどんな表現が出てくるのかということには興味がある。これは後の時代から見ると、2020年代ってのはそういう時代だったんだと。エラーが具象の世界、記号性とか表彰性にも大幅に関与してきた時代なんだと言えると思います。
岸:アメリカの『Time』紙が今年の1月に報じたニュースによれば、ケニアの「Sama」というクラウドソーシングの請負企業がOpen AI社の依頼を受けて『ChatGPT』のデータセットのブラッシング、精査を行っているらしいんです。Samaが具体的に何をしているかというと、『ChatGPT』は基本的に大量のテキストデータを集めて学習するわけですが、ソースの中から政治的に問題のある文章とか、交通事故の詳しいレポートとか、性的虐待にまつわるようなテキストを弾く仕事をしている。つまりOpen AIは生成結果として出たらまずい内容のテキスト、自社が損をするようなテキストをSamaにアウトソースして排除しているわけです。こういった事実は搾取として当然批判を受けているわけですが、生成内容もこうした状況を踏まえるとおそらく、どんどん「プロダクトっぽいこと」しか言わなくなる。
『ChatGPT』が偏ったことだったり、支離滅裂なことを言うのは本当にいまこの時期だけ、2023年だけなのかもしれません。
渋谷:僕はAIから人間の議論を超えるような議論が生まれていくことに期待していて、そのほうが今後の方向としては面白いと思います。僕は『GPT-2』も使っていたんですが、あれはほとんど現代詩みたいだった。散文的な、「砂漠・花・君・水が居る……」みたいな感じで(笑)。対して『GPT-3』は結構平凡な文章を生成する。いまの『GPT-4』は文章の精度がかなり良くなったと思うんだけど、ある種散文的な意味でのエラーの発生には期待できない。
岸:僕も普段、人間を超越するというか、「向こう側」になにか別の世界が広がっていて、そこに対してAIと一緒にどうやってアクセスできるだろうか、と考えています。最近大事だと思ってるのは「人工知能を孤立させること」で、これは今後、一つの指標になるんじゃないかと。それは渋谷さんも実践されてることだと思っていて。それこそ『ドラえもん』で描かれていた出来事にも近いのですが、ベルトコンベアに並んでいる、正規品の黄色いドラえもんが、いまリリースされている『ChatGPT』とか『Stable Diffusion』だと思うんです。でも、黄色いドラえもんと22世紀のユーザーは、おそらくそんなに、新しいコミュニケーションというのはできなくて、むしろ耳をかじられて、恐怖で青ざめてしまったドラえもんが21世紀ののび太と不思議なコミュニケーションを取り始める。基本的には社会一般に使われるAIというのは画一化されたものになっていくはずで、そういう世界におけるユニークなAIというのは、エラーを起こしたドラえもんなんじゃないかなと。渋谷さんとオルタの関わりも、かなり『ドラえもん』だなと思いながら見ていました。
渋谷:ということは僕はのび太くんか(笑)。でも、近いものはあると思う。