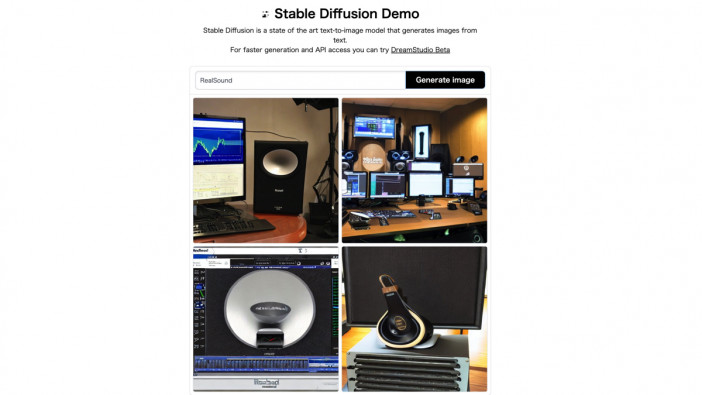「新しさと変わらなさ」の狭間でヒトとAIが共存するには 渋谷慶一郎と考える

画像生成AIが描いた絵がネットを賑わせている。この先、スマートフォンや自動車に限らず、文化的な分野にAI技術が入り込んでいくだろう。
これを音楽に用いた先駆者が、渋谷慶一郎である。2018年のアンドロイド・オペラ『Scary Beauty』に始まり、2022年3月にはドバイ万博で『MIRROR』を初演するなど、人工知能と音楽を掛け合わせるという道なき道を駆け抜けてきた。
その彼がアンドロイド歌唱、AI作詞による世界初のポップミュージック『BORDERLINE』のMVをリリース。誰もいない渋谷の地下空間で、アンドロイド・オルタ3、コンテンポラリーダンサー・飯島望未、渋谷自身がパフォーマンスする映像はインパクト大だ。
しかし本作は公開から1カ月ほどが経過した現在も、制作について具体的に語られる機会が少ない。いまだにミステリアスなイメージに包まれている本プロジェクトの全容を探るべく、今回は満を持して渋谷に話を聞いた。
自身が運営するATAK社の20周年コンサートを控える彼が『BORDERLINE』に仕込んだ魔法の正体とは。(小池直也)
人類は常に新しさと変わらなさを同時に求めるもの
ーー「BORDERLINE」の制作経緯を教えてください。
渋谷慶一郎(以下、渋谷):渋谷の公共空間を使用した新たな文化プロジェクトの第一弾ということでオファーがありました。夜中、地下鉄の改札をクラブにしたり、広告がない時は若手アーティストの作品を展示したりとか、ヨーロッパでは割と見慣れた光景ですが、そんな場所が東京にもあればいいなと思って引き受けたんです。
それから僕が「キャンペーンや広告に出演している」というよりも、「MV制作で場所を使っている」という方がスマートだし共感性が上がると思ったので、あえてミュージックビデオという既にあるフォーマットでコンテンツを作るということを提案しました。
ーー渋谷さんが渋谷出身という点も白羽の矢が立った理由だと聞いています。
渋谷:僕の学生時代は円山町のホテル街を自転車で抜け、渋谷区立の松濤中学に通っていました。とか言うと、都会だなあとか思うかもしれないけどセンター街が実家の子とか、中心に行くほど田舎の人みたいな構わなさになっていくというのが現実なんです(笑)。
あと信じられないと思いますが、僕が中高生だったころ、神泉はゲットーみたいだったんです。隣は日本でも有数の高級住宅地・松濤で、ギャップがすごかったですね。で、当時に比べると、いまの渋谷は均質化してマスカルチャーに寄りすぎているので、今回のようなプロジェクトは刺激剤として大事だと思います。
ーー制作はどこから着手しましたか?
渋谷:まずテーマを何にしようかなとぼんやり考えてるときに、BORDERLINEとプリントしてあるTシャツが部屋で目に入ったので、タイトルはそれにしました(笑)。ちょうどコロナ禍で国境を越えられなかったですし、改札はある種のボーダーですし、人間/AIの境界なども含まれるのでシンクロしたんです。その「BORDER」、「UNDER GROUND」など、いくつかのキーワードをもとに親友で東京大学教授の池上高志さんに協力してもらって言語生成AI「GPT-3」でテクスト生成したら、すごく面白いリリックが出てきたんです。それを見て「これはいける」と思ったのが制作の最初でしたね。
それから対比として人間をフィーチャーしたいと考えていて、最初は日本人ラッパーの何人かに声をかけたんですけど、「自分達はストリートだからこういうハイカルチャーに入ると裏切ることになる」とかなんとかいう、よくわからない理由で断られたりしたから(笑)、「もういいや、ラップもAIとアンドロイドでやろう」ということになったんですが、結果良かったと思います。
ただ、これは結構深刻な問題だと思いますね。アメリカのラッパーと同じことを日本人がただ真似するのではなく、なにか違うことを生み出す機会になるはずだったのに飛び込む人がいない。他方でNYのラッパー、ヒップホップで名前を言ったらびっくりするようなオリジネーターみたいなアーティストからアンドロイドのプロジェクトについてミーティングのオファーがあったりするのが現実で、本物の意識は先に行っている。そういう意味では、未だに「ストリートが」とか言っちゃってる日本は本当に島というか村なんですよね、意識が。
ーーいまのお話を踏まえると、作詞を務めたAIのクレジットが、路上でのフリースタイルラップによるセッションと同語(Cypher)なのは興味深いですね。
渋谷:たしかに。せっかくだから作詞家の名前を付けようと思ったんだけど、こういうときにありがちな古代の神の名前とかにしたくなかったので、それを避けてAI自身に「これからの進化を見守りたくなるような名前は何?」と聞いたら、Cypher(暗号・ゼロ)と教えてもらったから従いました(笑)。たしかにストリートのセッションも「Cypher」ですから、すごい皮肉ですね。
ーーそのCypherが生成したリリックはどのように使用されたのでしょう。
渋谷:3パターンほど作りましたが、結局は2パターンから字数やメロディに合わせて引用して使っています。抜粋はしていますが編集はしていません。「あなたの好きだった世界はもうここにはないです」、「痛みは私たちの人生に欠かせないもので」とかAIから吐き出されることで不思議なリアリティが出てきて興奮しました。
今回、この作品をリリースして国内外のインタビューをたくさん受けてわかったのは、人々は未だにAIに警戒心があるということです。しかし、AmazonやGoogleマップもAIを使っています。つまり、我々はAIなしでは生活できません。
それとは少し違うレベルで最近感じたのは、たとえばパリコレクションのレビューで「前シーズンとあまり変わらなかった」という主旨のものが増えていると思うんです。内容は全然悪くない、でも前シーズンとあまり変化が感じられないというレビューですね。しかし、AIに誘導された生活に慣れていたら、変化や快適さを提供してくれるセルフカスタマイズに囲まれて生活しているわけですよね。そういうオーディエンスを相手に半年に一度、毎回驚くよう変化と進化を人力だけで提供していくのは難しくなってきている気はします。
だからあらゆるデザインも部分的にAIを使うのは普通になっていくだろうし、音楽もそうなるはずです。人類は常に新しさと変わらなさを同時に求めるものです。ただ、新しさの部分をAIを無意識に駆使している人類に対して人力だけで作り出すのは難しくなっています。もう一つの方法は「新しくない、変わらない」という提案なんですけどね。
ーーなるほど。
渋谷:これはAIやテクノロジー礼賛ではありません。僕はオーケストラと仕事もしますし、手で譜面も書きます。同時にAIで作りました、という曲は既存の音楽を参照しすぎていて音色も既成のものを使っているから、AVのBGMみたいにつまらないことが多い(笑)。それとは逆に全てが新しいというだけだと、わかりやすく実験的という範疇に収まってしまってもはや人は聴かないので、新しい音の連結やレイヤードはAI、オリジナルな部分は自分、とか配分を変えつつ分担、ミックスすればいいんです。だってルンバだけで家事してて、洗面所とかめちゃ汚い彼女とか付き合いたくないでしょ(笑)。
ーーたしかに(笑)。また冒頭のオルタ3によるラップのような部分が印象的でしたが、今作の歌に関してはどのように制作していったのかも教えてください。
渋谷:ラップなどの表現も全然出来がよかったので即決しました。音色に関しては「VOCALOID5」などの音声ソフトを色々組み合わせています。この分野については進化は青天井なんですよ。アダルトコンテンツが含まれるとテクノロジーの発達が加速するように、使いたい人の多いボーカロイドに関するものはどんどん進化していきますね。
AIが活用された「VOCALOID6」も使い始めています。GUCCIの音楽でもそうでしたけど、人間ではあり得ないエモーションというのは僕の音楽と相性がいいんです。