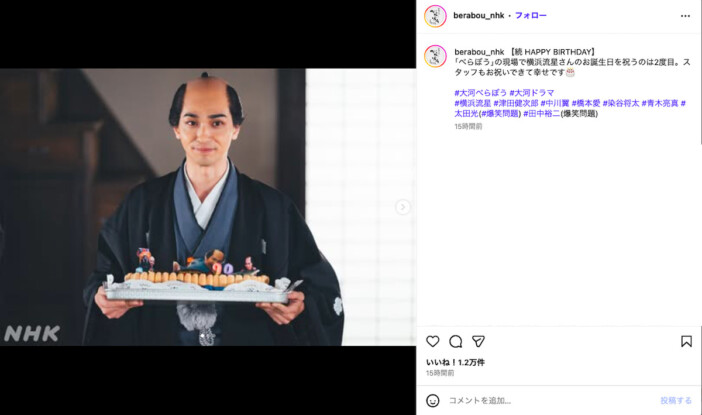『べらぼう』すべてがこぼれ落ちていく悲しみの第43回 蔦重×定信が奪われた“夢”

そこには、輝かしい未来が待っているはずだった。待ち望んだ我が子。ゆくゆくは耕書堂を継がせ、江戸をますます盛り上げていってほしいと願った蔦重(横浜流星)。一方、将軍になるという願いは届かなかったものの、大老という重職を得て、この国を正しい世へ導こうとしていた松平定信(井上祐貴)。そのためには多少強引なやり方もいとわなかった。これまでもそうしてきたように。だが、運命は残酷にもふたりから夢を奪っていく――。
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第43回「裏切りの恋歌」は、蔦重と定信が「俺がやってきたことは一体何だったんだろうな」と嘆かずにはいられない、すべてが指の間からこぼれ落ちる瞬間を描いた回だった。

蔦重の妻・てい(橋本愛)が授かった子は、産声をあげることなくこの世を去った。『べらぼう』では、これまでも子が親よりも先に命を落とす場面が何度も描かれてきた。それは将軍・徳川家治(眞島秀和)も、老中・田沼意次(渡辺謙)も、そして市井の人・小田新之助(井之脇海)も等しく経験した、理不尽な死だった。
子を亡くすということは、未来を失うことに等しい。その子とどんな日々を過ごそうかと思いを馳せ、その子が生きる世界をより良くしたいと願う。そのために何ができるかを模索し、できる限りのことをしようと意欲を燃やす。そんな存在を奪われる痛みがどれほど深いものか。蔦重も他人の悲しみを見届けてはきたが、やはり我がこととなって初めて、胸の奥底から実感したに違いない。

加えて、蔦重は小さな命との別れだけではなく、ときに我が子のように思ってきた歌麿(染谷将太)との決別も重なる。義理の弟としての人生を与え、才能を見出し、育て、売れっ子の絵師へと導いた。これからもともに生きていくと疑わなかった歌麿。しかし、それほど近い関係性だったからこそ「歌麿ならば」と甘えきっていた部分もあったのは、私たち視聴者の目から見ても明らかだった。
歌麿ならば自分のことをわかってくれるはず。なぜならば、自分こそが歌麿を一番に知っているから。ときとして、親は子のことを“自分の思い通りに動いてくれ“”存在だという錯覚に陥りがちだ。何もわからないところから生きるすべを教え、育ててきたからこそ、“こうなってほしい”という祈りから、やがて“こうあって当然”という期待を押し付けてしまう。

「身重のていには苦労させたくない」と言った言葉も、歌麿としては「じゃあ、自分は苦労させてもいい存在ってことか」と傷つけたに違いない。けれど、蔦重としては一心同体の歌麿だからこそ、いっしょに苦労してくれるという絶大な信頼の裏返しだったのではないだろうか。
守り、導いてきたからこそ、何の疑問も持たずにずっと変わらず自分に付いてきてくれる、他の人よりも慕い続けてくれるという過信が生まれた。そこに自分の思いもよらぬ恋心が芽生えていることなど想像もつかなかったのだろう。
恋心とは、相手から一番に見つめてほしいという願い。「当代一の絵師」にするという蔦重の夢に、歌麿は「蔦重にとっての一番の存在」と重なる部分があった。むしろ、そこだけを信じてきたから、付いていくことができた。ところが、蔦重に新たな家族が築かれ、多くの戯作者や絵師が出入りするようになると、歌麿は“抱え絵師の中のひとり”になり下がってしまった寂しさを募らせていったのだ。

「お前は江戸っ子の自慢、当代一の絵師なんだから」と言われても、蔦重から耕書堂を譲り受ける実の子に勝つことはない。ていのように蔦重の一番近くに居続けることも叶わない。この報われない恋心から逃れることでしか、歌麿としてはもう自分を保つことが難しくなってしまったのだ。
「俺をあの店の跡取りにしてくれよ」
「蔦重はいつもそうだ、お前のためって言いながら俺のほしいものなんて何ひとつくんねぇんだ」
子どものわがままのように言い放ったのは、歌麿にとっても蔦重への最後の甘えだったのかもしれない。