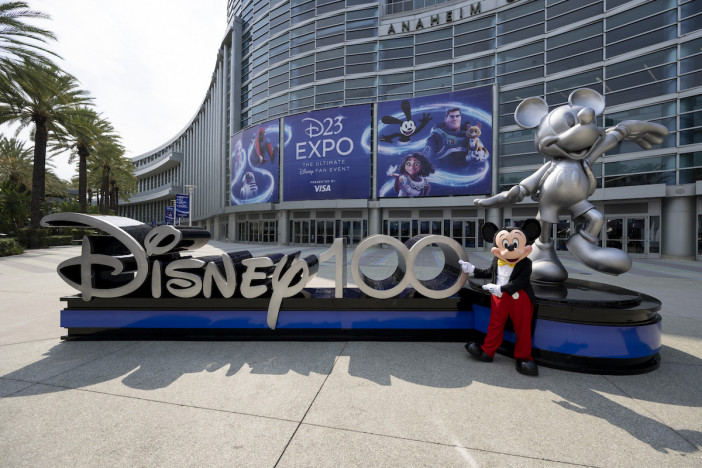マーベル・スタジオ“初のホラー作品” 『ウェアウルフ・バイ・ナイト』にみる新たな可能性

ディズニープラスからハロウィンのシーズンに合わせて配信された『マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション:ウェアウルフ・バイ・ナイト』(以下、『ウェアウルフ・バイ・ナイト』)は、マーベル・スタジオが「初のホラー作品」として打ち出した一編だ。
コミックヒーロー原作映画の人気が定着した現在、『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年)で、一つの頂点に達した熱気を保持し続けるため、とくに業界の最前線にあるマーベル・スタジオは、新たな要素を作中に組み込み、多様なアプローチを試している。本作『ウェアウルフ・バイ・ナイト』は、そういった方針が最もよく分かるものとなっている。
ここでは、そんな本作がマーベル・スタジオ作品のなかでどのような存在なのか、そして今後どのような意味を与えることになるのかを考察していきたい。
モンスターとハンターが殺し合う闇の世界が、本作の舞台。絶対的なハンターが死去したことから、彼の持っていた強力な武器「ブラッドストーン」の継承権を巡り、世界中から集まった凄腕のハンターたちがデスゲームをおこなうというのが、本作の物語だ。
主人公は、ガエル・ガルシア・ベルナルが演じる男、ジャック・ラッセル。気弱で戦いが得意ではないラッセルは、恐ろしいモンスターと渡り合えるようなハンターにはとても見えないが、彼には隠された“秘密”が存在した……。
54分の中編作品という、イベントで同じ時間を過ごす家族や友人たちでわいわい楽しむのにちょうどいい、「TVスペシャル」的な枠の提案。一部カラー映像を含む「パートカラー」ながら、ほぼ全編モノクロームで進行する試みは、一部モノクロだった『ソー:ラブ&サンダー』(2022年)のチャレンジをさらに進ませるものとなった。
そして『狼男』(1941年)に代表される、クラシカルなホラー映画の風合いや演出を再現し、上映中の映画館で映写技師が手動でアナログフィルムを交換するためスクリーン上に表示される「パンチマーク」を、わざわざ加えているなど、あざといともいえるオマージュをおこなっているところも楽しめる。
本作の監督と音楽を手がけたのは、映画音楽家として著名なマイケル・ジアッキーノ。短編作品を除外すれば、本作が本格的な監督デビューとなる。凄腕のハンターたちが集まって殺しのゲームを始めるに至るまで、彼の巧みな劇伴が、自分自身の演出で使用されているところが、見どころ、聴きどころだといえるだろう。
冒頭で示されるように、本作はこれまでのヒーローたちの奮闘する世界から隔絶し、ダークな雰囲気に包まれている。もともと同名の原作コミックもまた、『狼男』の内容とさほど変わらないホラー作品として始まっているのだ。であれば、映像作品として、クラシック映画の要素を組み込むことは、一見意外に見えるものの、つくり手からすれば妥当な表現方法だったといえるのではないだろうか。そして、映画『狼男』同様に、モンスターと人間との間にいる存在が、“ヒーローとヴィラン”といった構図ではない、より大人に向けた、世の中のグレーな見方、価値観を提供しているのである。