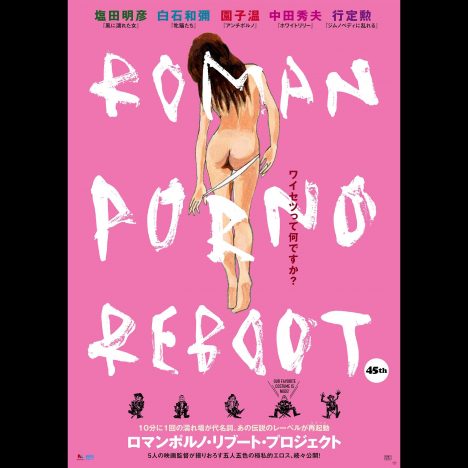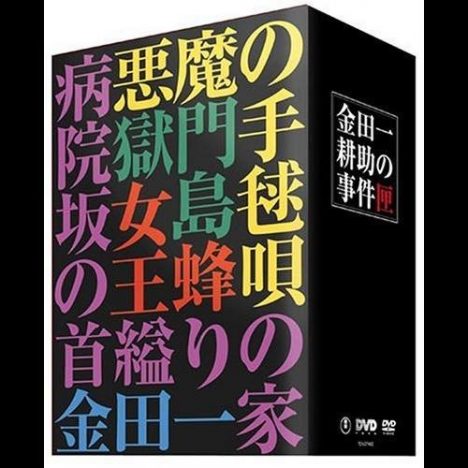庵野秀明、山崎貴に続くのは山田洋次と黒沢清!? 『海賊とよばれた男』が示す日本映画とVFXの関係
“脇役”として渋い活躍をみせるCGとVFX

『海賊とよばれた男』は終戦間際から幕を開け、店主の鋳造が戦後の焼け跡から石油商・国岡商店の再起を図ろうとする。30数年前の事業を立ち上げて間もない若き日を回想しつつ、復興期の日本でたくましく成長を遂げていく姿が描かれる。VFXは大正・昭和、戦前・戦中・戦後と、文字通り大きく変貌する背景を担う。こうした過去の失われた風景をCGで再現する作品は、監督がVFXをどう活用し、どう撮るか、演出意図とも密接に絡み合う。
単にCGで背景を作ってその手前で芝居を撮るだけでは、『スパイ・ゾルゲ』(03年)の様に書割というか銭湯のタイル絵みたいなショボいCGをそのまま使って、昭和初期が再現できたと喜んでいるだけの平面的なカットばかりが連続する作品になってしまう。かと言って、やたらとCGで作ったことをひけらかすような不必要にキャメラが動きまくるのも鬱陶しい。その点、流石に山崎監督は現状を熟知しており、「現在CGはごく当たり前の存在になっていて、それだけじゃお客さんを呼べない時代になりました。一方でCGやVFXは居てもらわないと困る、そんな中堅どころの良い役者になってきた感があります」(『CG WORLD vol.221 January 2017』ボーンデジタル)と語る。

実際、この映画のCGやVFXは実に渋い脇役なのである。冒頭の東京大空襲と焼け跡への空撮から崩れた建物をくぐり抜けるキャメラワークを除けば、基本的に固定画面か緩やかにパンするぐらいで、背景が主張しすぎないように留意されている。観ている間は、かなりの部分がCGなのだろうなと思いつつ、ほとんど気にならず、上映後、パンフレットを開いて、あれもこれもグリーンバックと最小のセットだけで撮ったのかと驚かされた。これまでも『リターナー』(02年)の海上油田や、『Always 三丁目の夕日』で画面の手前を走るSLをミニチュアで作るなど、観客の目線が向かうポイントや重量感が必要な場面ではフルCGに頼らずに実写やミニチュアへ振り分けて活用する試みが成功していた。今回もセット、ミニチュア、3DCG、マットペイントなどを組み合わせる技法を駆使して充実した画面を作り出している。
『海賊とよばれた男』は山崎貴には不向きな題材?

だが、冒頭の東京大空襲でB-29の爆弾倉からクラスター爆弾が落下するのに合わせてキャメラも一緒に落下し、空中で数十本の焼夷弾が開いて地上へ降り注ぐという3DCGで作られたシーンは、これまでにない見せ方を意図したとのことだが、逃げ惑う人々が俯瞰で一瞬映されるものの、これでは敵側の視点でしかなく、地上の視点から木造家屋や人体が炎上するといった灼熱地獄的描写もないので恐怖が伝わってこない。この空襲が主人公の戦後の原動力となるだけに、この描き方ではアメリカへの敵対心は生まれない。
この作品はVFXがなければ成立しないシーンが多くあるとは言え、これまでの山崎作品の中でも最もドラマが主体となる作品である。殊に鋳造が北九州で国岡商店を立ち上げた若き日々は、最も情熱的な時代となるはずだ。新規参入業者の鋳造と取引をする者がおらず、もはや万事休すという時に伝馬船で海上まで石油を売りにいくことで形勢逆転する。しかし、旧来の業者からは反発を食らい、海上で一触即発の危機となるが、船と船の間をすり抜けて対立を回避する。これが戦後、国岡商店が所有する大型タンカーがイランへ赴いた際、イギリス艦隊と一触即発になるシーンへの伏線となるが、構図としては過去と現在の対比になるとしても、若き日の鋳造が既得権益を貪る者たちを跳ね除ける〈海賊とよばれた男〉たる海での暴れぶりが描かれないのが物足りない。史実はどうあれ、ヤクザの出入りに近い荒っぽい対立があってもおかしくないのではないか。
鋳造を店主と呼んで慕う店員たちとの関係も、この時代ならばヤクザまがいの親分子分の関係に近かっただろう。鋳造のもとへ雇ってくれと入店してくる若い男たちにしても、台詞以上には鋳造のどこに惹かれたのかが分からない。かつて東映が高倉健主演で製作した『山口組三代目』(73年)は、後に山口組三代目組長となった田岡一雄を主人公にした作品だが、山口組が斡旋する港湾の荷揚げ作業の仕事にありついた田岡がわらじを脱ぐきっかけは、転がり込んだ時に食べさせてもらった白米である。貧しかった田岡が白米を大泣きしながら口にかきこむ印象深いシーンによって、彼のその後の忠義に納得がいく。これはヤクザの世界ではあるが、この作品の店主と店員の関係はあまりにも近代的すぎるのではないか。
また、伝馬船の海上販売のシーンの描写不足と同様に、映画の軸になりそうなシーンがことごくスキップされてしまうのが物足りない。満鉄への車輌油の売り込みで、機関車を使っての実験に成功するが、「この後、国岡商店は大陸に販路を広げ、めざましい発展を遂げた」という字幕のみで終わってしまい、映画の中で絶頂期が描かれない。戦後、旧海軍の備蓄タンクを空にさせる業務を国岡商店が請け負った時も、最初に雇っていた人夫があまりの匂いで頭痛を起こして逃げ出し、店員たちが自ら作業に当たらねばならなくなる。このプロジェクトこそは、国岡商店の戦後復興を象徴するエピソードになるはずだが、吉岡秀隆が『Always 三丁目の夕日』(05年)の茶川竜之介みたいな芝居で事に当たるので、まるで深刻な作業に見えない。こうした肩すかしがクライマックスとなる大型タンカーとイギリス艦隊の場面にまで影響する。それ以前の絶頂期が描かれないので、緊迫感あふれる状況の中で、コトの成り行きを日本から見守る鋳造が自らの若い頃の〈海賊〉時代に重ね合わせて盛り上がる――とはなってくれない。
VFXが不可欠な作品でありながら、VFXが作品を象徴しないというこの映画の特性からして山崎貴には不向きな題材だったのではないかと思えてならないが、それでは誰がこんな映画を監督できるのか? という話になる。ドラマ部分を重厚に描く手腕を持つ監督はいるだろう。だが、VFXへの判断はどうか。今後、こうした作品が増えていくならば、VFXへの知識は専門家に任せるとして、演出意図をVFXに組み込み、事前のイメージの共有、上がってきたCGへのジャッジが可能な監督が、アニメ・VFX畑以外の実写監督にどれだけいるだろうか。現在、そうしたVFXと演出意図を最も意欲的に接合させているのは、山田洋次監督と黒沢清監督ではないかと思う。