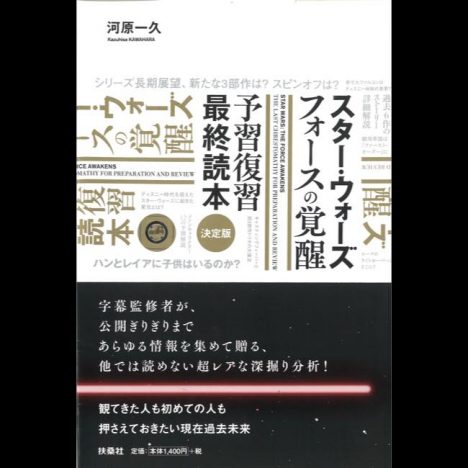『マイ・ファニー・レディ』に漂う“優しさ”の由来は? P・ボグダノヴィッチ監督の過去から考察

昨年の第27回東京国際映画祭におけるサプライズのひとつは、ピーター・ボグダノヴィッチ監督とオーウェン・ウィルソンの来日だったのではないだろうか。その時、上映された作品こそ、ボグダノヴィッチ監督にとって13年ぶりの劇場用長編作品となった映画『マイ・ファニー・レディ』だった。
舞台演出家アーノルド(オーウェン・ウィルソン)と彼の妻であり女優でもあるデルタ(キャスリン・ハーン)は、新作の共演者を決めるオーディションを開催。そこに現れた女優の卵イザベラ(イモージェン・プーツ)は、かつてアーノルドと関係を持ったコールガールで、彼は何とか妻との共演を阻止しようとするものの、デルタはイザベラの演技を絶賛しオーディジョンに合格させてしまう。さらにイザベラに恋する脚本家、脚本家の恋人であるセラピスト、セラピストの患者でありイザベラの別客でもある判事などが入り乱れ、物語は複雑怪奇な様相に。

ハリウッドにおいて<映画評論家>という稀な出自を持つ映画監督のひとりであるピーター・ボグダノヴィッチは、本人も女性と多くの浮き名を流してきた人物。浮気男と妻と女優の三角関係を中心にした本作は、現実の映画製作においても劇中同様の微妙な男女関係によって成立しているという面白さがある。
例えば、本作の脚本を手掛けたのは、ボグダノヴィッチの元妻。女優として活動していた彼女が、自身の主演作として企画した脚本だったという経緯があり、本作にはプロデューサーとしても参加している。そして、イザベラの母親役を演じたシビル・シェパードは、ボグダノヴィッチの元恋人。本作では元ミス・コニーアイランドという設定になっているが、シビル自身もミスコンで優勝してファッションモデルとなった人物。その後、女優に転向し『タクシードライバー』(76)では、ロバート・デ・ニーロが一目惚れする選挙事務所の女性を演じていたが、彼女の映画デビュー作こそ、ボグダノヴィッチの監督作『ラスト・ショー』(71)だった。

『ラスト・ショー』は、寂れた地方の映画館が失われてゆく姿を描いた作品。カラー映画全盛の時代にあえてモノクロで撮影されたこの作品によって、ボグダノヴィッチは長編監督2作目にしてアカデミー監督賞候補となり、一躍人気監督となった。その後のフィルモグラフィを眺めてみると、ボグダノヴィッチ監督作品の多くに、ある共通点が指摘できる。例えば、1930年代のアメリカを舞台に当時の流行歌をふんだんに盛り込んだ親子劇『ペーパー・ムーン』(73)や、1910年代のサイレント期における映画産業を描いた『ニッケル・オデオン』(76)。ボグダノヴィッチが描く、ということは、つまり、描かれていることが、その時代において「失われつつある」ということなのである。
本作でも、矢継ぎ早な台詞の応酬や、レストラン、ホテル、劇場と場所を移しながらキャストそれぞれの姿を描きつつ、最終的には全員がひとつの場所に勢揃いしてしまうという構成に、ハリウッド黄金期を飾った“スクリューボール・コメディ”や“グランドホテル方式”といった類いの映画の要素を盛り込んでいることが判る。また、映画冒頭でフレッド・アステア主演『トップ・ハット』(35)の楽曲「Cheek to cheek」を使用したり、エルンスト・ルビッチ監督のある映画を引用していたり、台詞と音楽を同期させたような劇伴を作らせていたりもする。つまり、これらハリウッド黄金期の魅力もまた、今のハリウッドで「失われつつある」ということなのである。