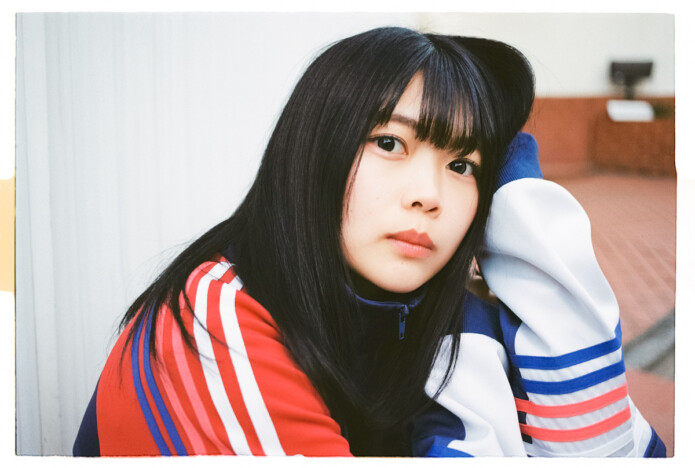『ピーター・パン』朗読×音楽で浮かび上がらせる新たな物語 由薫&菜々香が語り合う、世界観の再解釈

主役は現実を生きる人たち――大人の立場で見るからこその気づき

――おふたりの声の混ざり方にも注目ですね。ちなみに、会場の形も珍しいですよね。
菜々香:こういった会場は初めてかもしれないです。できるだけいろんな角度のお客さんを見ながら、演じられるようにしたいと思っています。
由薫:私はそもそも横から見られる経験がないかもしれないです(笑)。でも、音楽舞台の文脈において、円形劇場って音がいいイメージがあって。実際、会場のBAROOMの音もすごくいいんですよね。それに、こういった構造だと誰が主役なのかがわからなくなるのがいいなと感じています。位置的にも客席のほうが高いですし、演じる側と観る側という単純な二極ではなくて、会場全体の雰囲気が出やすいのかなって。
――観客としては、普通のステージだと客席とステージの間に絶対に越えられない壁を感じるんですね。でも、BAROOMのようなステージだとその壁が薄く感じられて。
菜々香:演者側でもその感覚はありますね。こんなに客席と近い劇場は初めてですし、いちばん前の方なんて目線がほぼ一緒なんです。今回の作品では会場の一体感を生むためのちょっとしたシーンがあるんですけど、BAROOMだからこそより際立つシーンになると思っています。
由薫:私、演じている途中でお客さんが急に立ち上がって、一緒に踊り始めたらどうなるんだろう、っていう妄想をしちゃいます(笑)。
菜々香:フラッシュモブみたい!
由薫:普通の舞台だと、そもそもステージに上がってこられないから、そういう妄想もリアリティがないと思うんですけど、今回は手を伸ばしたら手が繋げそうな距離なので。誰か踊り出してしまうのでは、って(笑)。
菜々香:踊ってくれたら面白いけどなあ。
――その一体感も見どころのひとつかもしれないですね。『ピーター・パン』という作品は誰もが知る名作ですが、今作を通して新たな発見などはありましたか?
菜々香:妥協したり、大変なことを乗り越えたりして大人として生きていくなかで、『ピーター・パン』という作品が子どもの時のピュアな気持ちを思い出させてくれるわけですが、嬉しさだけじゃなくて切なさも感じるんだなと思いました。子どもが読んで「楽しい!」と感じる作品のイメージがあったんですけど、今作を通して大人にも楽しめる物語だったんだと気がつきました。自分のためにも、子どもたちのためにも、読み聞かせをしたい作品です。
由薫:私もありました。稽古中の雑談でも「年代によって共感する部分が変わってくるね」という話が挙がったのですが、まさにそうで。たとえば、昔はフック船長って、悪者だからすごく嫌いだったんですね。でも、音楽朗読劇(Song Storytelling)を通してもう一度『ピーター・パン』の物語に向き合ってみて、「フック船長がかわいそう」という気持ちが芽生えて。私も大人になったんだな、と思いました。この歳になってあらためて『ピーター・パン』と向き合えてよかったな、って。それはきてくださる方々も感じると思います。ピーター・パンが主役のように思えるけれど、ウェンディやお母さん、娘のジェーンなど、現実世界を生きる人たちの存在がすごく大事。主役は現実を生きる人たちなんだな、とも思いました。
――なるほど。
由薫:それに、登場人物がみんなきれいすぎないんですよね。だからこそ、いろいろな解釈や考え方ができるというか。ピーター・パンもウェンディも、完璧じゃない部分が描写されていて、大人が見るとそこに心を打たれると思います。
菜々香:みんな、人間らしいよね。
「大人になる」は決して子どもじゃなくなるわけではない

――そんな登場人物をおふたりが演じるわけですが、自分が演じる役に似ていると思う部分はありますか?
由薫:MBTI診断ってあるじゃないですか。私、その結果が自由奔放なタイプだったんです。だから、ピーター・パン役を任せてもらえたのは間違いじゃないな、って。仮にみんなの心のなかにピーター・パンがひとりずついるとすれば、私のなかのピーター・パンは存在感が強め(笑)。私がピーター・パンに似ているというよりも、心のなかのピーター・パンが出てきやすいタイプなんだと思います。
菜々香:あははは! 私はハーフ&ハーフかなあ。ウェンディに共感するんですよね。規則だったり、お母さんの言いつけを守ったりっていう「ちゃんとしなきゃ!」という部分は私も持っていて。でも、心のなかでは「自由に生きたい」と思っている部分がすごく強いんです。たまに爆発して自由を貫くけど、結局「ちゃんとしなきゃダメだ!」って戻っていくタイプ。側はウェンディだけど、なかでピーター・パンを飼っている感じというか。ピーター・パンが飛び出さないように頑張ってる(笑)。でも、年々自由度は増しているかもしれません。
――押さえつけられていたピーター・パンが出てきているわけですね(笑)。作品においてピーター・パンから見たウェンディ、ウェンディからみたピーター・パンはそれぞれどんな存在だと解釈していますか?
由薫:ピーター・パンって、すごく忘れっぽくて。でも、不思議とウェンディのことは忘れていない。ピーター・パンは自信家でわがままなのに、ウェンディに揺さぶられているシーンが結構あるんですよね。それはきっと、ウェンディから何かをもらったんだろうな、って。ウェンディはピーター・パンの弱い部分を包みこんだり、揺らしたりする存在なのかなと思っています。
――たしかに、ピーター・パンとウェンディって不思議な関係性ですよね。「恋愛感情があるのか!?」と思ったり。
菜々香:私が思うのは、ピーター・パンはウェンディの母性に包まれたのかなと思っていて。実はピーター・パンは悲しいことを背負っている部分があるのですが、それをウェンディが包みこんでくれたんじゃないかなと思うんです。だから、本当は忘れっぽいのにウェンディを思い出して、思い出した時にウェンディに会いにきてくれているのかなって。だから恋愛になっていないんだと思います。
――恋愛を超えた愛のような。
菜々香:はい。家族ごっこをするシーンがあるのですが、そこでピーター・パンは母性のようなものを感じたのかなと思いました。
由薫:ぜひ皆さんも考えながら観ていただきたいです。
――観劇したうえで考えることがあるのは面白そうですね。音楽朗読劇(Song Storytelling)の紹介文には「大人になる事ってなんだろう」という文言がありますが、この答えをおふたりはどう考えますか?
菜々香:子どもの頃は自分が行きたい方向に進むことができるけれど、大人になるとそうもいかない。自分が望むことも望まないことも、酸いも甘いもすべて受け入れて愛することが大人になることだと思っています。20代の頃は、それに抗ってストレスを感じることも多かったんです。でも、それを続けていたら生きていけなくなると思って。その時に「自分に愛を持てばいいんだ」「それが大人になることなんだ」と気がつきました。
由薫:『ピーター・パン』に出てくる大人は、日常のやらなきゃいけないことに追われてしまっているんですよね。だから、大人になるというのは年齢ではなく、やりたいことを日常のために諦めることができたり、犠牲にできたりすることなのかなと思いました。それは素晴らしいことではあるけれど、自分勝手な心や自信を持ち続けることも大切だというのが、ピーター・パンが伝えたいことなのかなって。「大人になってしまった」だと子ども心を忘れてしまったことだと思うけれど、「大人になる」は決して子どもじゃなくなるわけではないというか。観てくださる方には、自分のなかの子どもの部分をぜひ思い出してほしいと思います。ちなみに、私はおばあちゃんになっても子どものような側面を持ち続けるのが人生の目標です(笑)。