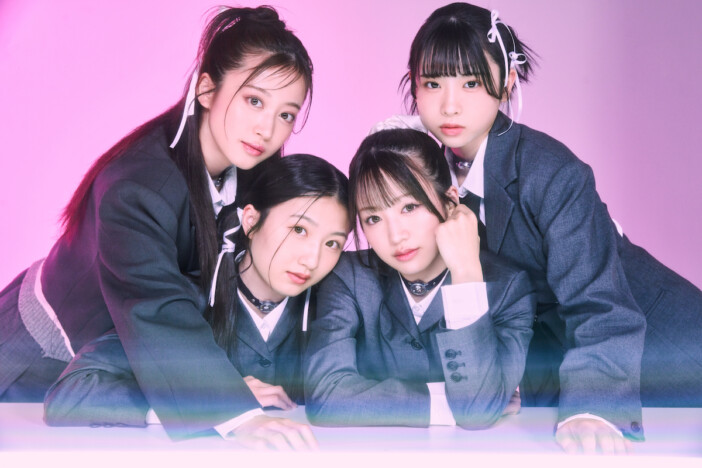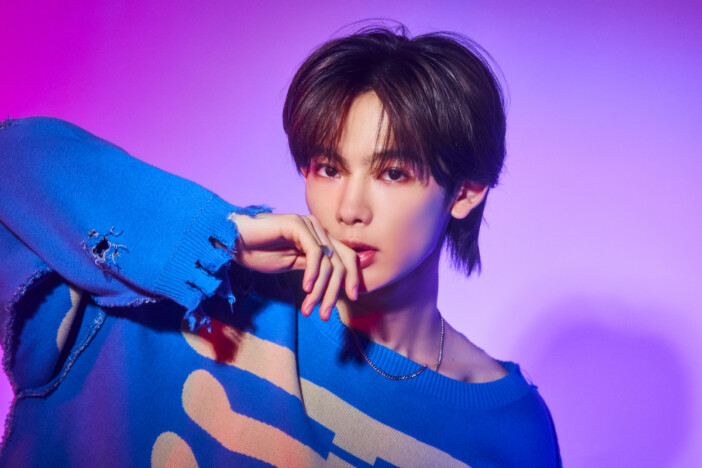10-FEET、太陽が丘に刻んだ25周年の集大成 全33曲のセットリストで網羅した“ロックシーンを切り拓いてきた軌跡”

結成25周年を迎えた10-FEETが、バンド史上2度目の大規模な野外ワンマンライブ『10-FEET 25th ANNIVERSARY ONE-MAN TOUR 2022 FINAL in 太陽が丘』を11月12日に開催した。約2万人の観客が会場を訪れたこの日。10-FEETのワンマンライブとして最大キャパシティとなったことはもちろん、3時間近くにわたって披露された全33曲の“網羅性”という意味でも、まさに25周年の集大成を刻むライブだったと言えるだろう。
同じく太陽が丘で開催されている自身の主催フェス『京都大作戦』をはじめ、各地のフェスで大規模なライブを行うことはあるものの、ワンマンライブは長い間ライブハウスのみで行うことを一貫してきた10-FEET。だが、近年は大きな変化が訪れており、2019年5月には初めての大規模な野外ワンマンライブを長崎市稲佐山公園野外ステージにて開催。2021年にはコロナ禍を逆手に取った初のホールツアー『10-FEET “アオ” TOUR 2021-2022』を廻っており、ワンマンライブやツアーの方向性を広げてきている。短い持ち時間で沸点まで着火させるフェスのライブではなく、2〜3時間かけてじっくり聴かせるワンマンライブで規模の拡大を果たしていったことには、大きく2つの要因があると思う。
1つは、「分かり合えないけど、分かり合いたい」「時には傷つけ合ってしまうけど、それでも側にいたい」「言葉だけでは伝えきれないことを音楽で伝えたい」といった想いを爆音のエネルギーにして、心の奥底に問いかけていく10-FEETの楽曲が一段とスケールを増し、特に2010年代以降はストレートなメロディの強さが際立つようになったから。「その向こうへ」や「蜃気楼」を経て、「アンテナラスト」「ヒトリセカイ」「シエラのように」などがすっかりライブの定番曲になっていることを思えば、“今こそライブハウスの外へ広げていこう”と自然な流れで思えたのかもしれない。

そしてもう1つは、10-FEETが“ストーリー”を大切にしているバンドだから。3年前に野外ワンマンを行った稲佐山公園は、2001年に10-FEETが初めて出演した野外フェスであり、2006年に初めてフェスでヘッドライナーを務めた『Sky Jamboree』の会場である。その頃はまだ『京都大作戦』もなかったため、フェスの大トリでライブをすることは当時の彼らにとって特別な瞬間だったのだろう。それから10-FEETはほぼ毎年『Sky Jamboree』に出演し続けており、初の大規模な野外ワンマンも同じ場所で行ったというのは、まさにアツいストーリーの賜物だった。今回、25周年ワンマンの会場に太陽が丘を選んだのも、これまで『京都大作戦』に出演してきた全ての仲間たちがいたから今があるというストーリーを大切にしたからだろうし、25年間を1本の線で結ぶような、強い心意気を持って臨むライブだったからなのではないだろうか。
だが、1つ大きな違いを挙げるとしたら、稲佐山でのワンマンが多数の盟友をゲストに招き、『京都大作戦』を凝縮させたようなライブだったのに対し、今回はゲストミュージシャンの出演が一切なかったこと。3人だけのステージで、しかもMCも最小限にして、10-FEETが25年間で何を紡いできたのかを、時間の限り“音楽に乗せて”届けていくーーそんなライブとなっていた。

迎えた当日は、心地よい秋晴れが広がり、猛暑や雷雨に見舞われることの多い『京都大作戦』とはまた違った表情の太陽が丘を感じることができた。会場内にはオリジナルのグッズやフードが販売されていて、開演までまだ時間がある中、昼間からのんびりと公園内で過ごす家族連れもたくさん見受けられる。また、『京都大作戦』で牛若ノ舞台になっているステージには10-FEETのバンドセットをイメージしたセットが組まれ、自由に楽器(のパネル)を持って撮影できるようになっていたり、10-FEETがエンディング主題歌を務めることでも話題の映画『THE FIRST SLAM DUNK』の巨大なビジュアルボードがずらりと並んでいたりと、フォトスポットも多く用意され、ライブ前のワクワクを消化できる遊び場になっていたのも印象的。こうした空間もまた、10-FEETが目指してきたものだ。


夕方になると、憩いの時間を過ごしていた観客たちが「さて、そろそろかな」と話したりしながら、ゆっくりライブ会場へと向かっていく。そして17時過ぎ、オレンジの空の下でいつものSEがかかり、開演。それぞれお気に入りの10-FEETタオルが一斉に掲げられ、『京都大作戦』そのもの、いや、それ以上に壮大な光景が一面に広がったところで、TAKUMA(Vo/Gt)、NAOKI(Ba/Vo)、KOUICHI(Dr/Cho)がステージに現れた。「よっしゃー! 結成当初、よくこうやって始まってました。懐かしい始まり方で!」とTAKUMAが叫んで、いよいよ渾身のセットリストの幕が上がる。

1曲目「DO YOU LIKE...?」は「お前らテンフィが好きでここに来たんやろ?」と問いかけるような、いわば出席確認の1曲。そこから「4REST」「STONE COLD BREAK」「hammer ska」「チャイニーズ・ヒーロー」などを立て続けていくが、この序盤のパートには、メタル、ヒップホップ、レゲエ、パンクなどを混ぜ合わせ、2000年代のロックシーンを新しいサウンドで開拓してきた10-FEETの“ミクスチャー性”が凝縮されていた。ダウンチューニングで演奏される「super stomper」「JUNGLES」などは、その真骨頂。今となっては1つの楽曲が複数のジャンルを内包することは当たり前だが、10-FEETは初期から3ピースバンドとしてそこにトライし、海外のパンクやニューメタルと共振するミクスチャーロックを鳴らし続けてきた。と同時に、本人たちのキャラクターも相まって、あくまでそれをキャッチーなジャパニーズロックとして鳴らす面白さを確立させたバンドだ。そうやって切り拓かれたフィールドと、2010年代以降のバンドがそこに咲かせた花を振り返ると、10-FEETが日本のロックシーンにおいて、いかに大切な存在だったのかを痛感させられる。

その流れはメタルサウンド直系の「aRIVAL」で頂点を迎えるわけだが、特筆して触れておきたいのは「GOODBYE TO ROMANCE」。スタッフから「ROTTENGRAFFTYの曲のこと?」と問われるぐらい、ご無沙汰になっていた曲だとTAKUMAも冗談混じりに語っていたが、歌心とラップの混ざり合い、間奏パートへの展開も含め、今聴くと10-FEETのミクスチャー性がとてもいい塩梅で混ざり合った1曲だ。久しぶりに披露してみて、「37人ぐらいしか手が挙がらんかった(笑)」ようだが、おそらく手を挙げる以上に1秒も聴き逃したくないと、観客はレア曲にじっくり聴き入ったのだと思う。