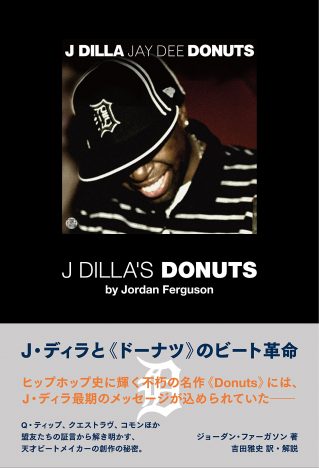the band apart 木暮栄一「HIPHOP Memories to Go」第3回
the band apart 木暮栄一「HIPHOP Memories to Go」第3回 高校時代、原昌和の部屋から広がった“創作のイマジネーション”

the band apartのドラマー・木暮栄一が、20年以上にわたるバンドの歴史を振り返りながら、その時々で愛聴していたり、音楽性に影響を与えたヒップホップ作品について紹介していく本連載「HIPHOP Memories to Go」。前回は16歳でバンクーバーに渡り、A Tribe Called Questの洗礼を受けたところまでだったが、第3回では帰国後の春休み、メンバーたちと再会した後のあれこれについて語られる。そこには、バンアパの制作の原点とも言える風景があった。(編集部)
カナダでの約1年の生活を終え帰国したのは1995年の春。
時差でぼんやりとしたままの頭で「地下鉄サリン事件」のニュースを見て、全く現実感が湧かなかったのを何となく覚えているから、3月20日前後だったのだと思う。
一週間くらいは誰とも会わずに家で漫画を読んだりしていたが、高校に進んだ同級生たちはちょうど春休みの時期だったので、帰ってきたよー、と電話で報告すると、「マジかよ、会おうぜ!」とすぐに会うことになったのだった。
地元の友人たちと久々に会って驚いたのは、一年前まで愛読雑誌は『MEN'S NON-NO』、目指せ武田真治みたいなフェミニンな服装だった彼らが全員やさぐれていたことだ。長く伸ばした髪を茶色に染め、ダボダボのジーンズを穿いてスケートボードを足で弄ぶヤツ、あるいは全身オーバーサイズのラルフローレンで原付に跨がりセブンスターをふかすヤツなど。耳にでかいピアスをぶら下げている者もいた。
一年前にブリティッシュコロンビア高校で受けたカルチャーショックの再来......というよりは、日本での流行の発信源はほとんどの場合海外から、という黒船以来の仕組みに初めて実感を伴って触れた瞬間だったと言えるかもしれない。
そんな春休み中に再会した原昌和は、前回軽く述べた通り坊主頭で、軽く汗ばむ陽気にもかかわらずイエローのダウンベストを着ていたのを覚えている。中学の卒業ライブではフードを被ってMegadethを歌っていた原だが、その時はまだ楽器は何も弾けなかったと思う。しかし一年ぶりに会った彼は小沢健二 featuring スチャダラパーの「今夜はブギーバック」のバックトラックをシーケンサー(ピアノ、ベース、ドラムなどを打ち込んでループさせる機械)で再現できるほどになっていて、軽くギターを弾いたりもしていた。今考えれば、後のマルチな演奏巧者の片鱗がすでに見え隠れしていた。
川崎亘一も髪が長くなっていたが、当時流行のチーマー風ではなく、どちらかと言えばロック・ギタリストの風情が強い長髪だった。再会してすぐにバンドをやろう、という話をしたと思う。この時の彼はスラッシュメタルばかり聴いていたような気がするけど、徐々にRage Against The Machine やKORNなどの当時「ミクスチャー」と呼ばれていたジャンルや、Nirvana、Pearl Jamなど、メタル以外のバンドにも食指を伸ばしていく。彼の家に泊まりに行くと、そういったレコードが乱雑に積み上げてあった。CDではなくあえてレコードという、いわゆるアナログ・リバイバルもこの頃に始まったムーブメントのひとつ。
荒井岳史の初対面の印象も前回書いた通りだが、彼とは原の家でよく一緒に映画を見た。バンド名の由来にもなっている『パルプ・フィクション』などのタランティーノ作品に加えて、ゾンビものや古き良き大らかさが炸裂しまくっている80年代後半のアクション映画が多かった。僕はその辺のジャンルに疎かったので、いま考えれば大いに勉強になった......というか、原と荒井コンビが揃った時の映画のディテールに対する独特な着眼点、ツッコミの入れ方が相当面白かったので、毎回爆笑しながら見ていたと思う。
例えばアーノルド・シュワルツェネッガー主演の『コマンドー』で、サブマシンガンを連射しながら走り出てくるモブキャラの銃口が左右にブレまくっているシーンを「これ相手に当てる気ねえだろ」と、何度も巻き戻して弾丸の射出角度を確認したりとか。
the band apart の曲作りの特徴の一つとして、各々が出したアイデアを基本的に否定しない、というものがある。今も変わっていないそのコミュニケーション方式は、振り返ってみればこの頃によく溜まっていた原の部屋からなだらかに始まっていた。