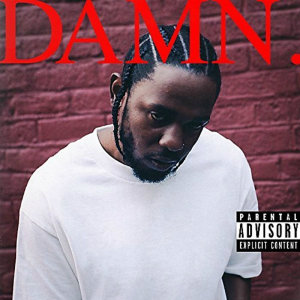小熊俊哉の新譜キュレーション:特別編
小熊俊哉が選ぶ、2017年邦楽ベスト10 作り手の意識の変化による“アップデート”感じた一年に
海外ではVisible Cloak『Reassemblage』やコンピレーション『Mono No Aware』など、近年のニューエイジリバイバルを通過したアンビエントの傑作が目立った。その辺りとの同時代性も感じさせるのが、やけのはら、P-RUFF、H.TAKAHASHI、大澤悠大によるUNKNOWN MEの2作目『subtropics』。陽だまりのような音響がじんわり溶けていく快感は、筆舌に尽くしがたい。ほんのりトロピカルな空気感と内省的(密室的)なトーンが共存しているあたりは、ジャンルこそ全然異なるが、ドレイクの「Passionfruit」やカルヴィン・ハリス『Funk Wav Bounces Vol. 1』、あるいはTAMTAMの『EASYTRAVELERS mixtape』あたりと重なる部分もあるように思う。
「ロックが停滞気味」と書くのにうんざりしているなかで、8ottoがプロデューサーの後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)と一緒に作り上げたプロダクションは衝撃的だった。打ち込みも交えながらバンドサウンドを再構築し、アレンジやリズムアプローチなどで実験を重ねたことで、名うての中堅バンドが大変身。ナイジェル・ゴドリッチ(Radioheadなど)やブレイク・ミルズ(Alabama Shakesなど)といったプロデューサーたちのモダンな方法論を意識しつつ、8otto独自のソリッドな演奏とGotchらしいパワーポップ的なエッセンスが組み合わさったことで、はち切れそうなテンションが徹頭徹尾に詰まっている。
こういうふうに、「いいものはいい」だけでは生き残れないことを、ある程度上の世代がはっきり自覚しだしたのも興味深い兆候だろう。元キリンジの堀込泰行が、D.A.N.やtofubeats、WONKらとコラボしたEP『GOOD VIBRATIONS』で、堀込高樹のKIRINJIとは異なる「ネオ」を獲得していたのも象徴的だ。そして何といっても、ストリーミングサービス時代のリアルと向き合い、質・量ともに桁外れすぎる大作となったサニーデイ・サービスの『Popcorn Ballads』は、やはり問答無用のマスターピースである(大作といえば、凄まじいのが同作に参加したCRZKNYの『MERIDIAN』。3枚組160分のヴォリュームだけでなく、ジュークを拡張する破壊的サウンドも規格外!)
実際、『Popcorn Ballads』のスケール感とフットワークの軽さには大きなヒントが隠されている気がして、2018年は若い世代のロックバンドからも無邪気な野心が飛び出してきたら面白くなりそうだ。志の高いアルバムも少なくなかったが、今のバンドシーンは正解に頼りすぎて、こじんまりとしている気がしなくもない。
最後に、曲単位ではシャムキャッツ「このままがいいね」、Negicco「愛は光」、あっこゴリラ「ゲリラ × 向井太一」の3曲に強くときめいた。それにやっぱり、SKY-HI「キョウボウザイ」も欠かせない。勇気と情熱をもった音楽に心動かされる一年だった。
■小熊俊哉
1986年新潟県生まれ。ライター、編集者。洋楽誌『クロスビート』編集部を経て、現在は音楽サイト『Mikiki』に所属。編書に『Jazz The New Chapter』『クワイエット・コーナー 心を静める音楽集』『ポストロック・ディスク・ガイド』など。Twitter:@kitikuma3。