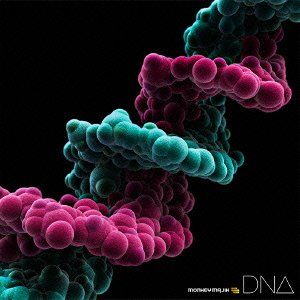東北で精力的に活動する両者が意気投合
MONKEY MAJIK×渡辺俊美 対談「震災後は『何のために歌うか』を考えるようになった」

「音楽が生き物になっていく」(渡辺)
――BlaiseとMaynardのご両親も、時々日本に来られていますね。
Blaise: これまで3回来ていますね。10数年前と5年前と数ヶ月前に来て、特にお父さんが日本大好きになりました。昔は単純に「すごくきれいな国だ」と言ってましたけど、来るたびにどんどん好きになっているみたいで。3回目は特に感動していて、「スピリチュアルな力がすごく強い」と言っていました。オタワに住んでいるんですが、気温以外はちょっと仙台に似ているかもしれない。人も優しいし、食べ物とか名物を大事にしている街です。みんなメープルシロップをカナダと思っているけど、あれはケベック。オタワもいいところですよ。
渡辺: ふたりは震災を経て、音楽との向き合い方は変わりましたか?
tax: 最初は本当に苦しかったです。何を作ったらいいのか分からなかった。ものの見方が変わってきたというのもあるんですけど、現実を受け入れた先の答えがない、迷いしか書けなかったというのもあって。そんななかで、フレデリック・バックというカナダのアニメーション作家が日本で展覧会をするということで、テーマ曲を書いてほしいという依頼があったんです。もちろんうれしかったし、まずは引き受けた仕事からしっかりやっていこうと思って、曲を作り始めたんです。戦後の話を描いた『木を植えた男』という作品を見ながら曲を書いたんですが、そのおかげで「僕らのいまの思いを形にしていいんだ」と気持ちの整理がつきました。それで、そのまま「木を植えた男」というタイトルの曲を作ったんです。そこで現実に起きていることに向き合って、受け入れて、自分たちの思っていることを形に残す…という繰り返しでいいんだと思いました。そういう風にしかできない、それがいちばん自然体でいいんだとメンバーの中で思えるようになって。
Blaise: 新しい曲もそうだけど、昔の曲に対しての気持ちが変わりましたね。例えば、仙台でチャリティイベントをやったとき、「アイシテル」や「fly」を作った当時とはぜんぜん違う世界に入っていて。若いときにデビューして、ハッピーな気分で作った曲を歌いながら、歌うことの意味が完璧に変わっていることがわかって。遊びの曲が、真面目な曲に変わったんです。みんなで歌って、歌詞の意味が本当に変わって聴こえたし、「アイシテル」のひと言が、本当に大切な言葉だと思えたんです。歌詞の意味の大切さに、あらためて気づくことができましたね。
渡辺: そうそう。曲を作っているとき、どうやって録ったかというフィーリングは覚えているけど、今はどんどん曲が育っていく感じがあるんです。音楽が生き物になっていくというか。逆に震災後に作った曲が、震災と関係ない人に響いたりしているんですよね。楽しい曲を作っても、日常の楽しさが膨らんで逆転する。曲がいいとそういうことになるんですよね。それがちょっとバカな曲でも。
tax: 震災前は自分たちが満足すればいいと思っていたけど、本当に曲が育っていくんだと思います。また自分が歳を重ねてそぎ落とされることがたくさん出てきて、発想が変わってくるんですよね。本当に3年前を機に僕らは大きく変わったように思います。俊美さんも、20代のころに作ったTOKYO No.1 SOUL SETの曲がぜんぜん違うように響いたりしていますか?
渡辺: そうですね。例えば95年に作った「黄昏'95~太陽の季節~」なんかは、テレビでかかっていて「今ヒットするんだ!」って思いました(笑)。「太陽の光と月の明かり」ってまったく違うものなんだけど、いまになってみると重要視されるというか、どんどん自然の言葉が重要になっている。日本全体が苦労していて、「楽しいだけじゃない」って思うようになっていて。そういった意味でも、ひとりひとり思い入れが曲を進化させているのかなと思います。やっぱり自分で書くもの、思いつくのは息子のことですからね。嘘つかないで物語を書くのは、息子のことになってしまうんですよ。だから、昔の曲だけど息子が0歳、4歳、7歳のときに作ったもので、今でも歌える。「息子は息子だもん」って(笑)。