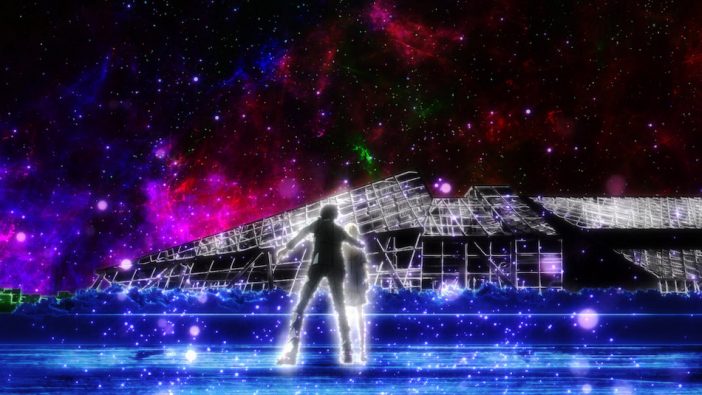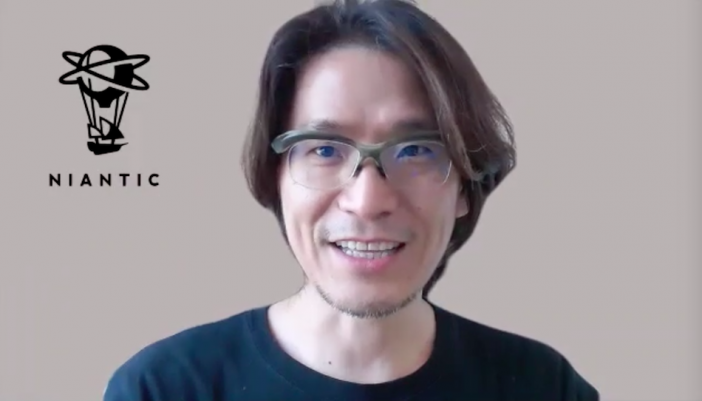『Ingress』開発陣インタビュー エージェントとコミュニティが象徴する、10年の軌跡

ゲーム業界に位置情報ゲームというジャンルを確立し、多大な影響を与えた『Ingress』。恒例行事だったリアルイベントは昨今の情勢を鑑みて長らく見送られていたが、『Ingress』の10周年を記念し、アメリカ・ロサンゼルスを起点として「Epiphany Down(エピファニードーン)」が開催された。そして、日本では約3年8ヶ月ぶりとなる2022年12月10日、横浜を舞台として「Epiphany Down」のフェーズ3が行われた。
今回は、同イベントで日本を訪れたBrian Rose氏(総責任者)、Michael Romero氏(エンジニアリング・ディレクター)、Thia Hightower氏(コミュニティ担当者)の3名に『Ingress』の10年の軌跡と、今後について訊いた。(編集部)
10周年を迎えて
ーー『Ingress』がリリースされてから、10周年を迎えました。エージェント(編注:『Ingress』のプレイヤー)のみなさんに何か言いたいことはありますか。
Brian:まずなによりも、この10年間支えてくださったエージェントのみなさんに感謝をしたいと思います。サービスを10年間続けるのは難しいことだと思うのですが、我々や『Ingress』はエージェントやコミュニティのみなさんに支えられ、ここまでたどり着くことができました。
ーー10年間を振り返ってみていかがでしょうか。
Brian:いろいろなことがありましたが、あえて1つお話するとすれば、『コミコン』というイベントでのことです。マーチャンダイズを作ってくださるパートナーの方とイベントに立ってTシャツを販売していたんですが、ある小さな女の子がぴょんぴょんと飛び跳ねながらこちらに向かって来てくれました。
彼女が我々の元にたどり着くと、すごく小さな声で「パスワードはカサンドラだ」と言ったんです。その言葉を聞いて、我々は彼女にデッドドロップ(宝探しのようなイベント内で秘密が書いてあるもの)をお渡ししました。それを受け取った彼女の手は震えていました。後でその子のお父さんがいらして、「彼女は『Ingress』がとても大好きで、宝探しゲームも大好きなんだ」と教えてくれたんです。
なぜこの話が私の心に残っているかというと、彼女はその日、間違いなく英雄になれたんです。彼女が所属している陣営では、とても大切な秘密が書いてあるデッドトロップを手に入れられたというのは、とても価値のあることだったはずです。
『Ingress』を遊んでくださっているみなさん一人ひとりが、あのときの女の子が感じてくれたような気持ちで「私がヒーローなんだ」「私がこの陣営に貢献したんだ」という気持ちを持ってもらえるのは、本当に嬉しいことなんです。すごく大きいことに自分が関わっているということをエージェントのみなさんに感じていただく、それを実現したいなと思ってやってきました。

Michael:私はスペイン語とポルトガル語を話せるので、メキシコやブラジルやパラグアイなど、いろんなイベントに参加してきました。 先月はロサンゼルスにいたのですが、この3年間はイベントが少なかったんです。ロサンゼルスでエージェントのみなさんにお会いしたときは、本当に久しぶりに会えてとても喜んでくださいました。改めて、自分がそのコミュニティの一員であるということが、とても嬉しかったです。ようやく日本にも来ることができ、みなさんとお話できるのを楽しみにしていました。
ーー10年間のなかで、ターニングポイントだと思った瞬間はありますか。
Brian:NianticはもともとGoogleのプロジェクトのひとつだったのですが、それがとても特別で、ユニークなのかもしれないと思ったきっかけがありました。
それはエージェントのみなさんと行ったロサンゼルスのイベントで、来場してくれた18歳の子が、私にこう言いました。「見て! 『Ingress』のロゴのタトゥーを入れて良いとお母さんに言ってもらえて、タトゥーを入れてきたんだ!」と。
Googleには12年間在籍していましたが、Googleのロゴのタトゥーをしてくれる方とはお会いしたことがなかったですね。『Ingress』を通じて、みなさんが自分の居場所や何かしらの絆を見つけてくださっていることは、とても特別なことだと思います。
チームのみんなでエージェントのみなさんの写真やエピソードを集めているのですが、いまお話したことも大切なコレクションのひとつです。余談ですが、本当にタトゥーを入れたのか気になってしまい、実際に擦ってタトゥーが消えないことを確認してしまいました(笑)。
ーーコロナ禍でイベントなどが開催できない苦しい期間もありましたが、これを前向きに捉えると、どんな変化がありましたか。
Brian:『Ingress』はコミュニティが強いという話をよくさせていただくのですが、その中でエージェントのみなさんが、お互いに連絡をとり続けてくださっていたのが印象的でした。「元気にしているよね?」という確認をチェックインしながら行ってくださっているのを見るのは、なによりも嬉しかったです。
リアルイベントはできなかったけれど、みなさんがZoomなどでつながってくれていました。そういう意味でも、コミュニティのつながりはより強くなったと感じています。我々のチームとしては『Ingress』がどんなものなのか、これからどんなことをするべきなのかを考えるタイミングでもありました。
現実と混ざり合うARのメタバース構築、VRとの棲み分けは?
ーー2022年は、メタバースという単語が大きく広がった1年でもありました。ARをベースとして現実と混ざりあったメタバースの構築や、理想について教えていただけますか。
Brian:まずVRに関してですが、一番適しているのはビデオゲームなど、周りの全てのものを遮断したいとき、そんな環境を構築するのには最適だと思っています。
ただ、私が考えているのはあくまでも現実世界の美しさを楽しむことです。今日のように外に出て、エージェントのみなさんにハグやハイタッチをするような触れ合いなんです。こうして美しい横浜に来たらガンダムも見に行きたいし、ほかにも新しいものにふれて知りたいと思います。もちろん、VRやビデオゲームなどの技術を活用できる部分もありますが、最終的には人と人とがつながって新しい友人をみつけたり、パートナーを見つけたり、みんなが集まる理由になるようなものを作りたいと思っています。
実はGoogleにいたときには、VRを担当していました。そのときに学校の教室の中で行われたVRのプロジェクトを視察したのですが、私はそこで、教室の中で子どもたち全員がVRのヘッドセットをつけているところを見たんです。それが私には少し異質に感じられてしまいました。同じコンテンツをARでも行っていましたが、ARで授業を行ったときには、全員が同じもの(その時は太陽系の模型)を一緒に見ることができたんです。皆が立ち上がって「あれ見える?」「ほらほら」など話しながら席を移動して、体験を共有している様子を見ることができました。
VRかARか、どちらが正しいということはまったくなく、共存するものだと私は思っています。VRやビデオゲームは、新しい技術をみなさんに体験していただくには素晴らしい技術ですよね。ARの技術や、これから出てくるARグラスなども新しい技術ですが、たとえばこれをゲームで体験していただくと、受け入れてもらいやすくなるかもしれないですね。