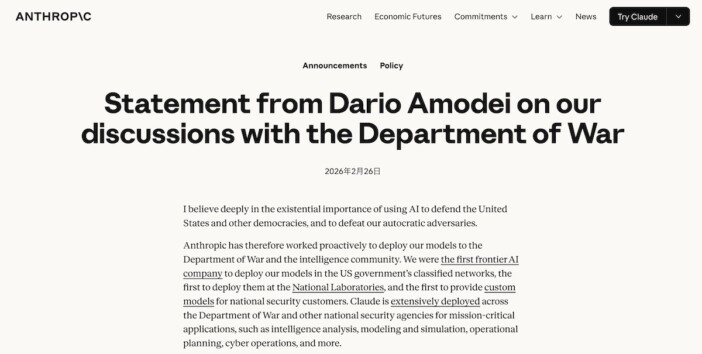『ヘブンバーンズレッド』 その核をなす、麻枝准というクリエイターの「最大の武器」と「人生」

麻枝作品に「バンド」が登場する必然性
次に、『ヘブバン』が麻枝准という人間の「第2の人生」の集大成であるという話をしていきたい。本作のシナリオや世界観が持つある種の迫真性の正体を探るには、彼の経歴を辿ることも有効な補助線になると思うからだ。
麻枝はアニメ『Charlotte』放送終了後の2016年、特発性拡張型心筋症という病を患い、生死の境を彷徨う大手術を行った。主治医からは実際に「手術が成功したのは奇跡。あなたは何かをなすために生き残ったとしか思えない」という旨の言葉をかけられたといい、本人曰く「医者ですらスピリチュアルなことを言うほどの」奇跡的な生還劇だった(この辺りの経緯は2017年発売のシンガーソングライター・熊木杏里との共作アルバム『Long Long Love Song』初回限定版に付属の冊子に詳しい)。麻枝自身、その主治医の言葉に感じるものがあり、以後オファーのあった仕事は何かの縁と基本的に受けるようにしてきたとのこと。『ヘブバン』の企画・開発がスタートしたのは2017年というから、まさに本作もそのような導きによってスタートした作品と言える。
ここではそうした経験が本作のシナリオや世界観に反映されている、といった素朴な話をしたいのではない。とはいえ、以前から麻枝作品に通底していたひとつの心象風景が、より研ぎ澄まされた形で表れているとは感じるのだ。
麻枝作品を貫くキーワード/モチーフには「過酷」、そしてそれを耐え抜く「強さ」というものがある。ざっと思いつくものを挙げるだけでも、『AIR』のラストに流れる印象的なフレーズ〈彼らには過酷な日々を、そして僕らには始まりを〉および主題歌「鳥の詩」の〈わたつみのような強さ〉をはじめ、〈その足は歩き出す やがて来る過酷も〉(「Little Busters!」)〈本当の強さを誰も持ってない〉(「灼け落ちない翼」)など、枚挙にいとまがない。麻枝作品は「泣けるシナリオ」が特徴とされがちだが、そのベースにあるのは「人生とは基本的に理不尽なものだ」というある種の諦観めいた認識であり、麻枝の好む言葉を借りれば「殺伐」とした荒野をひとり歩いていくようなものだ。実際、〈ひとりになっても歩くんだ〉(「Life is like a Melody」)〈ひとりでもゆくよ/例え辛くても〉(「一番の宝物」)など、「ひとり」と「行く/歩く」を組み合わせた表現も麻枝の書く歌詞には散見される。『Charlotte』を視聴された方には、最終話で主人公の乙坂有宇(おとさか・ゆう)がたったひとり、ぼろぼろに傷つきながら世界中を旅して回ったイメージを思い出してもらえるかもしれない。
恋愛アドベンチャーという「学園もの」の形式をとるジャンルを主な発表の場としてきたこともあって、従来のゲーム作品において上記のイメージは日常空間とは異なる「もうひとつの世界」として立ち現れてくることが多かった(ちなみにこの構造について麻枝は村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』からの影響を公言している)。それが今回の『ヘブバン』では未知の地球外生命体・キャンサーと戦うバトルRPGという形をとって、物語の前面に展開している。それまでは人生に時おり訪れる理不尽さのメタファーにとどまっていた「過酷」な荒野のイメージが、それ自体生きるべき戦場として目の前に投げ出されているのである。リアルタイムストラテジーの要素を含む緊張感ある戦闘や、荒れ果てた終末世界を画面をフリックしながら移動する経験も、キャラクターたちが戦場を生きているということを容赦なく突きつけてくる。
そんな戦場を生きるキャラクターたちは、どのような関係性を築き日々を生き抜いていくのだろうか。ここで重要となってくるのがバンドの存在だ。『ヘブバン』の主人公・茅森月歌(かやもり・るか)は〈She is Legend〉というバンドのボーカリストとして一世を風靡した過去を持つ根っからの音楽好きで、キャンサーと戦う部隊に配属されてからも、部隊員5人とともに新生〈She is Legend〉を結成してしまう。麻枝作品とバンドといえば、LiSAを輩出した『Angel Beats!』の〈Girls Dead Monster〉が真っ先に思い出されるだろう。その後『Charlotte』でも〈ZHIEND〉というバンドが登場しており、『ヘブバン』はそれに続く3作目となる。
ここに筆者は、近年麻枝の抱く人間関係のリアリティが「家族」的なものから「バンド」的なものへと移行していることが見て取れると考えている。
『AIR』や『CLANNAD』をはじめ、麻枝の初期作品では「家族」というテーマが支柱となってきた。しかし『リトルバスターズ!』で「友情」がテーマに据えられて以降は、愛情や血のつながりといったものに支えられた人間関係よりも、ある共通点を持った個々人が、ばらばらなままひとつの共同体を形成するような人間関係のモデルが前面に出るようになっている。理不尽な死を遂げた人々が死後の世界で「神への反逆」を目的に活動する〈死んだ世界戦線〉(『Angel Beats!』)や、特殊能力という「病」を抱え、同じような「病」を抱えた者たちの引き起こす問題に対処する〈星ノ海学園〉生徒会の面々(『Charlotte』)がそうだ。そしてこれはバンドという共同体のあり方にも重なる。ばらばらな個性を持ったプレイヤーが、ただ音の響きを通してのみひとつとなる。メンバー同士の仲が良いバンドが良いバンドとは限らないし、普通の意味での相互理解は必要ではない。音楽という魔力に魅入られてしまった者同士であるというその事実が、どんな言葉よりも深い信頼を築くのだ。
こうした共同体のあり方は、麻枝がゲーム開発やアニメ制作の現場で感じてきたリアリティを反映しているのではないだろうか。本稿では時おり留保なく「麻枝作品」と書いてしまっているが、当然ながら実際には麻枝ひとりの手によってそれらの作品が出来上がっているわけではない。先述の通り、最もピュアに作家性が発揮されていそうな音楽でさえ、編曲の工程に関してはノータッチなのである。作品作りという、普通ならこだわらなくても良いものに取り憑かれてしまった人間であるということ。愛情などなくとも、ただその一点において「自分と似ている」と感じられるからこそ信頼できるということ。麻枝に聞いたら「ときに意見を戦わせながら仕事をする人間に対して、そんなウェットな感情などない」と返されそうだが、はたして信頼ゼロで誰かとともに仕事をすることなどできるだろうか。
初小説『猫狩り族の長』刊行時のインタビューで麻枝は、「自分には仕事をしていない空白の時間こそ恐怖で、特に他の人は休んでしまう土日は絶望的だ」という旨のことを語っている。麻枝にとって作品作りという戦場は、文字通り人生そのものなのだ。そんな麻枝にとって「バンドが音を奏でる」という瞬間は、どんな理不尽に見舞われたとしてもその理想が自分ひとりのものではないと信じられる、貴重な瞬間に重なるのではないだろうか。だからこそシナリオ上の必然性ではなく、演出的な必然性として、麻枝作品にバンドの演奏シーンは組み込まれているのである。