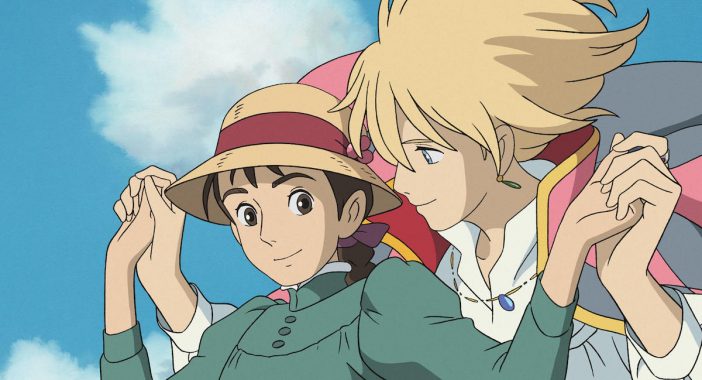『TOKYOタクシー』は至福の時間旅行映画 倍賞千恵子×木村拓哉の“視線の交わり”を読み解く

山田洋次監督が比較的最近のフランス映画をリメイクするということもなかなか驚きではあったが、それ以上に『TOKYOタクシー』という作品が、近年のフランス映画のなかでは随一の秀作であるオリジナルの『パリタクシー』をここまで忠実になぞっていることにはただただ驚かされた。
ややぶっきらぼうだが家族思いのタクシー運転手(木村拓哉)と、複雑な過去を持つ乗客の老婦人(倍賞千恵子)。舞台を東京に移した本作では、山田作品ではお馴染みの柴又帝釈天をスタートに、直線距離でおよそ70km、高速道路を使えば1時間半ほど(Google map参照)で行ける葉山までの道のりを、たびたび寄り道しながら何時間もかけて車を走らせる。その間に、老婦人の過去の回想が重ねられていき、たった一日のたった数時間の一期一会の旅のなかで、80年もの月日を遡る。至福の時間旅行映画である。

車窓を流れ去る街並み(これは270度のラウンド型LEDウォールを使ってスタジオにいながら東京中をドライブできるバーチャルプロダクションという技術が採用されている)はもちろんのこと、オリジナルからの多少の変更点は随所に見受けられる。その最たるものは、運転手の“個”にフォーカスしていたオリジナルよりもはっきりと、彼の“家族”を描いたことであり、それはいかにも山田監督らしく、松竹作品らしく、日本映画らしいところである。

最初の“寄り道先”である言問橋で語られる、老婦人の80年前の東京大空襲の記憶。ここはオリジナルでは、ナチスによって老婦人の父親が処刑された地を訪れるというものであった。山田監督の前作『こんにちは、母さん』でも触れられた3月10日のできごとを、この物語においてもあらためて描く。その後の朝鮮人青年との恋と別れ、結婚相手との団地での生活、そして犯した罪。とてもフランス的だったオリジナルの筋書きを丁寧に日本にローカライズしながらも、老婦人の置かれた境遇や見出されるテーマがまったくブレることはない。まさに職人技ともいえる脚色の妙に唸らずにはいられない。