鬼頭明里が「おはよう」の4文字に込めたすべて 『鬼滅の刃』禰󠄀豆子役は納得の抜擢
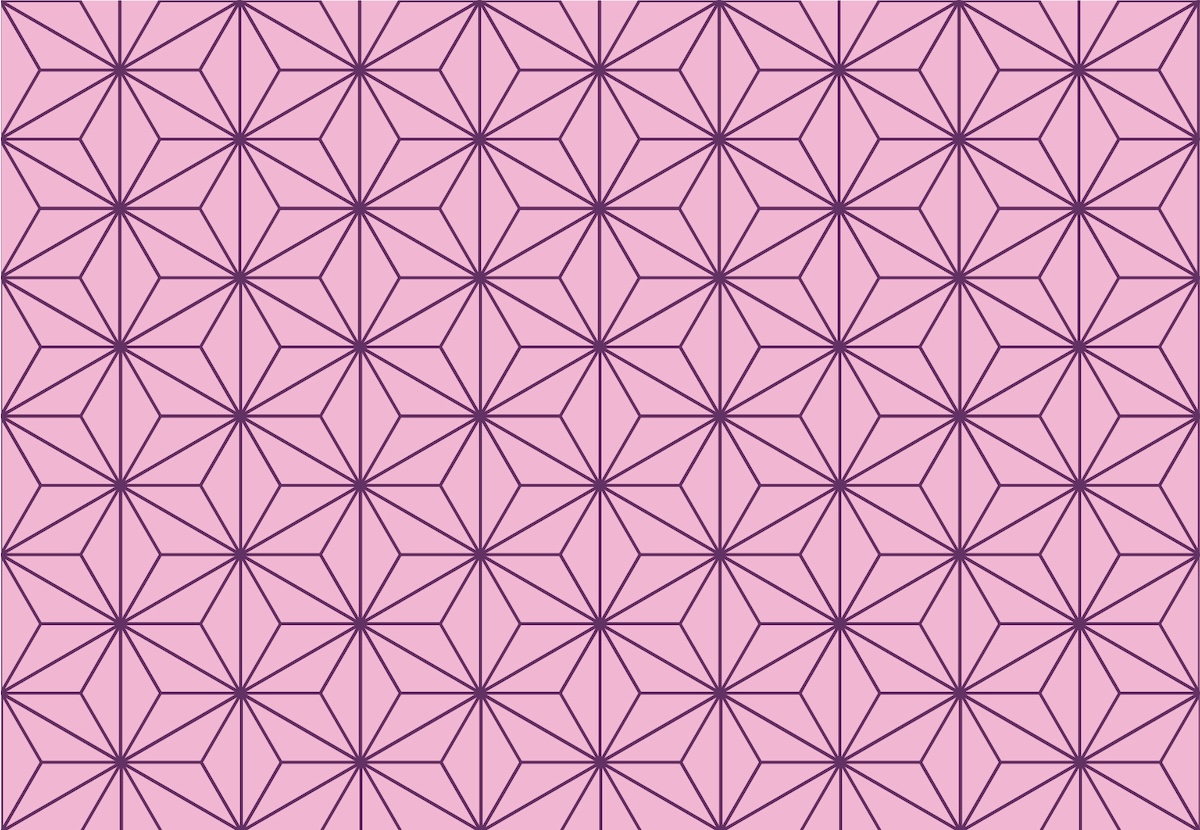
『鬼滅の刃』において、鬼頭明里の「出番」は多くはない。けれど、彼女が声を吹き込む竈門禰󠄀豆子の存在は、物語の芯を支える大きな柱のひとつだ。可憐さと柔らかさ、そして言葉を封じられた奥に潜む野性。そのひと言では言い尽くせない声の奥行きは、台詞がほとんどない役だからこそ、より強く浮かび上がってくる。
そんな鬼頭が演じる禰󠄀豆子は、鬼に変わり果てながらも、人としての心を保ち続ける少女。言葉を奪われ、唸り声と息遣いだけで存在を示すその姿は、派手な台詞回しよりもずっと雄弁に物語を語っていた。人間と鬼の思いが交差する中にあって、禰󠄀豆子はほとんど言葉を発さない。それでも炭治郎を守り抜く意思、兄妹の絆、鬼としての凶暴さと人間としての優しさのすべてを声だけで表現しなければならなかった。
オーディション時、鬼頭に伝えられたディレクションの一つが「もっと獣っぽく」というものだったのは有名なエピソードだが、その言葉は彼女にとって、役者としての“声”の役割を根本から問い直す挑戦でもあった。声優として台詞を磨くのではなく、言葉を削ぎ落としていく挑戦。唸り声にどれだけの感情を込められるか、息遣いや声のかすれをどう扱うか。試行錯誤しながらも鬼頭が到達した󠄀禰󠄀豆子が放つ唸り声には、理屈を超えた衝動と、なお残る人としての温度を絶妙なバランスで表現されていた。
特に那田蜘蛛山での「血鬼術 爆血!」の叫びは、その象徴的な瞬間だ。守られるだけだった妹が、自らの血を燃やし、兄と共に鬼と戦う。その声は言葉以上に禰󠄀豆子の意志を伝え、観客の心を撃ち抜いた。普段は可愛らしく小さな声で鳴いていた禰󠄀豆子が、戦うときだけ獣のように唸り、叫ぶこの落差こそが、彼女の二面性を形作っている。鬼頭は「声を封じる」という制約を、禰󠄀豆子にとっての最大の武器に変えたのだ。
禰󠄀豆子のもう一つの特徴と言えば、口に咥えた竹筒だ。鬼として人を噛まないための枷だが、声の演技においては大きな壁でもある。実際に何かを咥えて演じれば声はこもり、明瞭さを失ってしまう。だが、竹筒を無視してクリアに演じてしまえば、キャラクターとしての説得力は失われる。鬼頭は当初、自分の指を噛みながら声を出してみたりもしたというが、最終的にたどり着いたのが、口をほとんど開けずに、かすかな隙間から声を出すというものだった。
そんな“声を封じた演技”の集大成とも言えるのが、『刀鍛冶の里編』のクライマックスだろう。夜明けが近づく中、炭治郎は最後の鬼を討つか、太陽に焼かれそうな禰󠄀豆子を守るかの選択を迫られる。禰󠄀豆子は自ら兄を蹴り飛ばし、燃えながらも笑顔を絶やさなかった。そして、奇跡のように太陽を克服し、兄の前に現れたとき、彼女は初めて人間の言葉を取り戻す。
その一言が「おはよう」だった。たった四文字の言葉だが、鬼頭の絞り出した声にはこれまで抑え込まれていた感情が滲んでいたように感じられた。はっきりとしながらも、どこかかすれて不器用な響き。その不完全さこそが、禰󠄀豆子が鬼でありながら人としての声を取り戻したことの証でもあった。





















