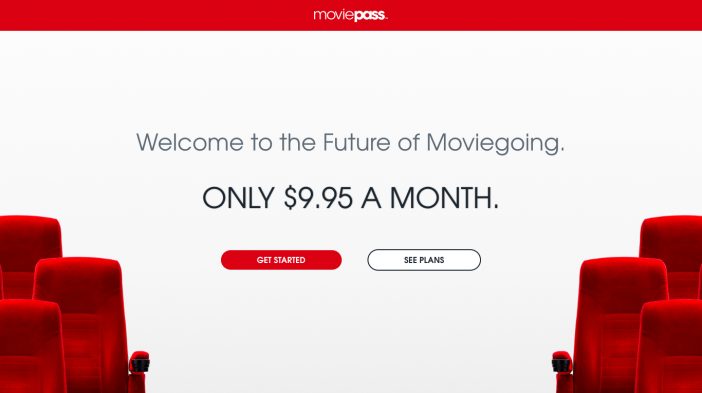『判決、ふたつの希望』監督が語る、レバノンからのインスピレーション 「葛藤や衝突からいい物語が生まれる」

第90回アカデミー賞外国語映画賞にもノミネートされたレバノン映画『判決、ふたつの希望』が8月31日より封切られた。レバノンの首都ベイルートが舞台の本作は、住宅の補修作業を行うパレスチナ人の現場監督ヤーセルと、キリスト教徒のレバノン人男性トニーの間で起こった些細な口論が、やがてレバノン全土を震撼させる騒乱へと発展していく模様を描いた人間ドラマだ。
リアルサウンド映画部では今回、クエンティン・タランティーノ監督の『レザボア・ドッグス』や『パルプ・フィクション』などの作品にカメラアシスタントとして参加した経験を持つ本作の監督、ジアド・ドゥエイリにインタビューを行った。自身の実体験からスタートしたという本作の制作過程から、レバノンに対する思いまで、赤裸々に語ってもらった。【インタビューの最後には、プレゼント企画あり】

「『ニュルンベルグ裁判』と『評決』は何度も観て参考にした」
ーーこの作品は監督自身の実体験がベースになっているそうですね。
ジアド・ドゥエイリ(以下、ドゥエイリ):僕自身が数年前にベイルートで実際に経験した、ある配管工の男性との口論がきっかけだったんだ。その数日後、もしもそのときの自分の怒りが収まらずに、雪だるま式になっていったら……と考え始め、それが物語になっていった。ただ、それは脚本の執筆をスタートしたきっかけに過ぎないんだ。アイデアを考えたときに、掘り下げてみる価値があると思ったからね。だから、その出来事は物語を書き始めたきっかけではあったけれども、自分の過去を掘り下げたり、自分の人生観ということを考えたりしながら脚本を作っていったから、導入の部分だけが実体験の基になっていると言えるね。

ーー後半にかけて物語の中心になってくる法廷劇はどのような流れで生まれたのでしょう?
ドゥエイリ:アイデアを掘り下げ始めた段階で、心のどこかで「これは法廷劇になるな」という自覚があったし、同時にそういう作品を作りたいという気持ちもあったんだ。法廷劇をやるということについては、主に2つのことをリサーチした。まず、僕の母親が弁護士だったから、実際に裁判で行われるルールやプロセス、弁護士や判事の喋り方、レバノンの司法制度などについて聞いたんだ。レバノン内でヘイトスピーチをしたとき、法的に罪に問われる可能性があるのかも聞いたね。それで、一部にはヘイトスピーチを取り締まる法律があるということを知ったんだ。もうひとつは、とにかく裁判ものの映画を観ること。特に、スタンリー・クレイマーの『ニュルンベルグ裁判』とシドニー・ルメット監督の『評決』は、何度も繰り返し観て参考にしたよ。

ーーレバノンにおける司法制度などを知っていく中で、もっとも驚きだったことは?
ドゥエイリ:リサーチのため、ベイルートから30kmほどの南部の裁判所に行ったんだけど、そこでまず判事が女性だったことに驚いたよ。それ以上に驚いたのが、実際に劇中にも出てくるように、法廷内に檻が用意されていて、被疑者がその檻の中で陳述することだった。その様子を見た瞬間、「これは絶対に映画で使おう」と思ったね。本来であれば法廷内で写真を撮ってはいけないんだけど、隠れてスマホで写真を撮って、美術担当に「これをそっくりそのままに再現してくれ」とお願いしたんだ(笑)。