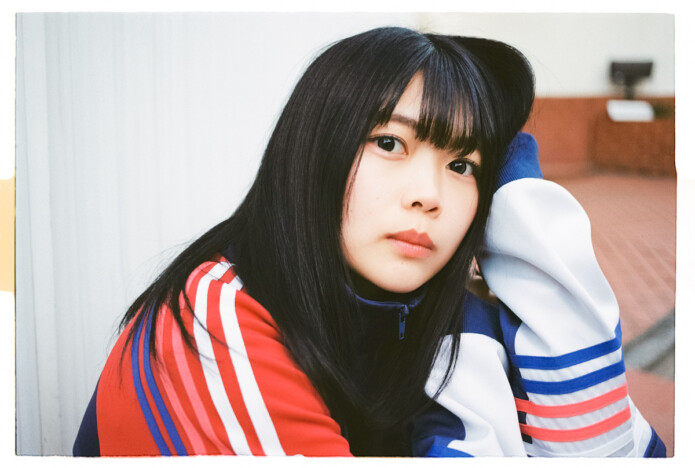LiSAがステージに刻んできた音楽と人生 歴代ライブと共に辿る、“ロックヒロイン”の軌跡

「私はやっぱりライブが好き」コロナ禍、初のオンラインライブに込めた願い

ーーそこから時が経って、世界はコロナ禍に入る。そして、LiSAは、初めてのオンラインライブとして、『ONLiNE LEO-NiNE』をやるわけだけれど、あのライブはどういう想いで向き合ったものだったんだろう。
LiSA:それこそ順序を経て、山を登っている途中だったんです。さいたまスーパーアリーナから次のステージに挑もうとしていたわけですから。アコースティックツアーとアリーナツアーを発表して、いよいよ10周年に向かっていくっていう、加速度を上げて走ろうとしていた時にコロナ禍がやってきて。私からするとーーというか、みんなにとって悲劇でしたよね。すべての計画が崩れて、体験したことのない、映画でしか見たことのないような事態になって。新しい音楽の形、新しいエンターテインメントの形を考えなくてはいけなくなった。でも、私はやっぱりライブが好きなんですよね。テレビに何度も出させていただけるようになってから、画面を通して伝えていく難しさをより感じるようになっていた頃で。たとえば、荒々しく歌う「Rising Hope」も、テレビで観ている人からするとただのノイズかもしれないなと。目の前で歌ったら、そうではないこともわかるし、私の気持ちも伝わるんだけど、(画面を通すことでそれが)伝わりづらくなるのかもしれないって実感していた時期だったから。そのなかでもやれることを探したライブでしたね。それでも届けたい歌と届けたいメッセージがあった。だから、リアルなライブという形じゃなくても、どこにいても伝わる歌、楽しさ、好きなものを届けたかった。
ーーそうだね。
LiSA:それに、私にとっては『紅蓮華』ツアー(『LiVE is Smile Always~紅蓮華~』/2019年)のすぐあとで。ちょうど『ONLiNE LEO-NiNE』の時に「炎」を出した頃なんです。だから、「炎」をみなさんに届けたくても、画面のなかでしかできなかったんですよね。そういう願い、想いを込めたライブでしたね。
ーーあのオンラインライブを観て、「いつの間にかLiSAはこういう戦い方もできるようになっていたんだな」とも思ったんだよね。ショーのなかでいろんな形で「LiSA」を見せていく。強さだけでなく、艶っぽさ、機微のある表情、あるいは、衣装をどう着崩すのかとかね、そういうトータルの振る舞いを通して、“最強”だけじゃないLiSAの姿も育んできていたんだなと。
LiSA:それは、アリーナツアーをちゃんとやれたからだと思いますね。ライブハウスだけで戦っていたら、あるいは、テレビで歌唱させていただく機会がなかったら、あのオンラインライブにはたどり着けてなかった。曲ごとに、歌う場所を移動していったり、画面のなかでの楽しさ、エンターテインメント表現も、アリーナツアーをちゃんとやれたからできたんだと思います。あれはあれで楽しかったです。

ーーLiSAの楽曲、LiSAのパフォーマンスは、いろんな切り口で映えるんだなと思った。
LiSA:あのライブをやらせてくれた事務所はすごいと思う(笑)。だって、普通は思いつかないし、それをやることに意味があるんだという想いを受け取って、実際やらせてくれるのはすごい。LiSAにとって必要なライブなんだと理解してくれたのがすごいと思った。
ーーうん。この重要なライブが、こういう形でまた観られるのは嬉しいね。
LiSA:はい。私もすごく好きなライブです。
ーーあの当時の、必死の歩み方がちゃんと刻まれているよね。そして、その翌年、デビュー10周年になる年に行ったのがアリーナツアー『LADYBUG』で。これはどういうツアーだった?
LiSA:『ONLiNE LEO-NiNE』から時間を空けて、まだどうなるかわからない、夜明けを願ったツアー、ライブでした。だから、このツアーでのライブは、ドアを開けるところから始まるんですけど。まだ、みんな、声を出せない状態での初めてのツアーで。でも、私のライブにおいて、みんなの声って私の自慢なんですよね。私自身が、この自慢の声がない状態でのライブを知らないんですよ。ずっとみんなの声を頼りにライブしてきたから、みんなを楽しませられるのかという不安があった。だけど、同じ願いを持った人が集まって、あたたかな温度が感じられる拍手に包まれながら歌うツアーでーーそうですね、“歌”を歌ったツアーであり、ライブでした。
ーーたしかにそうだったね。このツアーのハイライトとしてすごく覚えているのが、「Letters to ME」であったり、「ハウル」であったり、自分を鼓舞しながらなんとか歌を重ねていくというLiSAのイメージで。その印象が強いんだよね。
LiSA:どうなるかわからない世界のなかでも、それぞれが希望の光を消さないように。私自身、そういう願いを持って行なったライブでした。そばにいてくれる人がいるっていう、拍手のあたたかさを感じたライブでしたね。あの時は「明け星」と「白銀」と「往け」が発売されたタイミングで。ミニアルバムも出したし、新曲がたくさんあったんですよね。でも、新曲って(ライブで)みんなと作っていくものじゃないですか。だから、なんというか、神社のお祓いをしているというか、そういう気持ちでした(笑)。みんなに「一緒に頑張ろうね!」って祈祷するつもりで歌うというか。

ーーまさに祈りと願い、そのメッセージが強いライブだったね。「Letters to ME」はその象徴的な楽曲であるようにも感じたし、実に感動的だったけれども。でも、コロナ禍が終わり、今となっては、どこか役割を終えたのかもしれないね。
LiSA:セットリストを組む時は、いつも自分の心と対話するところから始まるんです、今の自分は何を歌いたいのか。それはもちろん、過去の曲も含めて。あの時、その想いが最大の形で出せたのが「Letters to ME」だったんですよね。
ーーそうだね。
LiSA:歌える曲、歌うべき曲はたくさんあったけど、あの時のあの状況も含めて、その時に感じていたいろんな想いをそのまま歌わせてくれる曲が、すでに持っていた曲のなかにはなかった。
ーーそう、だから作るしかなかったんだよね。そう考えると、この時歌った「Letters to ME」の、この時の願いを込めて、届けていくという役割は、一旦終えたのかもしれないね。
LiSA:「Believe in myself」みたいな感覚なんですよね。「Believe in myself」を書いた時の私はもう成仏していて。だから、今は別のものとして歌っていて。
ーーなるほど。そういう意味でも、すごく意義深いツアー、ライブだったね。
LiSA:私、『LADYBUG』のセットがめっちゃ好きだったんです。今までも退廃的な世界を作ってきたけど、表現も含めてスチームパンクみたいなイメージで作って。上からネジみたいなものが降りてくるとか。無骨な大きいものが動いている、みたいな。『ハウルの動く城』みたいなイメージ。すごく好きでした。あ、でも、衣装の早替え場がステージの下にしかなくて、それがすごく大変で。私、一回出てこられなくなったんですよ。
スタッフ:センターステージで方向がわからなくなっちゃって、逆に出ちゃって。
LiSA:そう! ステージがぐるぐる回っていたからわからなくなっちゃって(笑)。「LiSAが帰ってこない!」って。
ーーははははは!
LiSA:あの時からじゃないですかね、(ライブ中に)髪型を変えるようになったのは。「エクステならつけられる!」って気づいて。それまでは髪型を変えるのが結構大変だったんです。下ろしてる髪をくくるまではできたけど、くくっている髪を下ろすと跡が付いちゃうし、直す時間もなくて。でも、『LADYBUG』は、“歌”を歌わなくちゃいけないタイミングだったし、(みんなも声が出せないから)目でも楽しんでもらわなくちゃいけなくて。集中力を切らさないための趣向を凝らして、ステージセットも動いてたし、髪型も含めた表現で楽しんでもらうしかなかった。そういう意味では、ステージでの自分の姿をここまで考えるようになったのは、『LADYBUG』からかも。