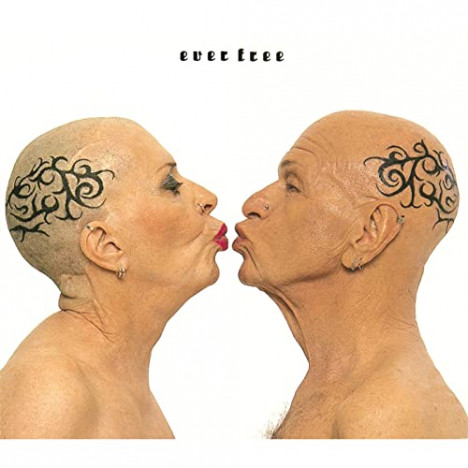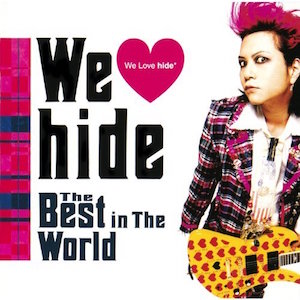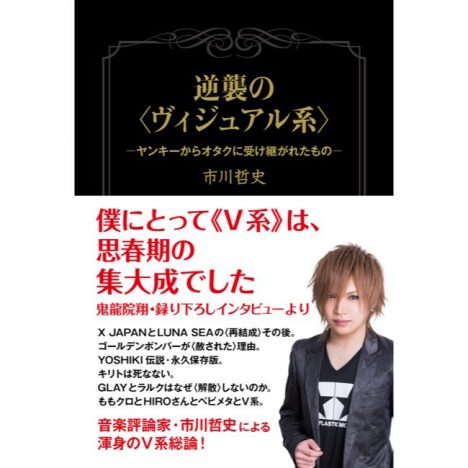hide、自由な発想で追い求めた“ロックからの逸脱” 現行ポップスにも通ずる音作り&自己プロデュースの斬新さ
現在「Z世代」と呼ばれるわれわれ若者世代であっても、日本に生まれ音楽の世界に分け入っていくなかで、必ずどこかにその残像を認めることになる存在がX JAPANのギタリスト HIDEであり、サイボーグ・ロック・スターのhideその人である(以下、hide)。
活動当時の世間の反応を肌感覚で確認する術は持たないが、少なくとも2010年代初頭から令和の今まで、SNSや動画サイトにおける、音楽/表現活動についての彼への評価で、最も多く目にした言葉は「(今でも)新しい」だ。もしくは「古くない」か。そこには思い出的なニュアンスでの「色褪せない」という意味ではない、後追い世代から見た、より冷静な楽曲へのジャッジが多く含まれている。もちろん、ステージングが垢抜けているとか、近年特にUSヒップホップシーンで流行っているゴスとスポーティなストリートファッションの掛け合わせをビジュアルに取り入れていることなど、視覚的な部分も大いにあるだろう。しかしそれ以上に、ソロキャリアにおける半身であり共同プロデューサーかつプログラマー兼マニピュレーターのI.N.A.をして「未来人」と言わしめるようなアプローチの数々が独自のタイムレス感を出しているのだ。そして驚くことにhideの仕掛けた時限爆弾は彼の死後25年近くを経てもなお、はじけ続けている。その試みをいくつか紹介しつつ、未起爆のダイナマイトに思いを馳せたい。
まず、hideが古びない最大の理由に、アナログとデジタルの転換点と活動期間が重なったことがある。高校時代に地元で結成した横須賀サーベルタイガーを解散させ、X JAPAN(当時のバンド名は「X」のみ)に加入したのが1987年2月のこと。CDがアナログレコードのシェアを上回ったのは1986年のことだった。さらに、CDを開発したフィリップス社が共同開発相手として指名したソニーがデジタル録音技術の感性に尽力し、1978年から民間への普及に向かっていく。加えてhideとしてのソロキャリアが幕を開けた1993年から一般家庭へのパソコン普及率がグッと上がりはじめ、時を同じくしてインターネットも裾野を急速に拡大させる。これらのテクノロジーはいまだに現役であるため、デジタル前/後での隔世の感は凄まじかったことだろう。特筆すべきはデジタルネイティブではないhideが、当時の発言や関係者の証言を参照する限り、この新しい波にノータイムで乗り上げた柔軟さだ。
2022年に至っても、ロックの世界はうっすら不寛容だ。カッチリした演奏やプロダクションはしばしば「機械っぽい」と敬遠され、聖域としての人力演奏が現存している。X JAPANにおいても「誰が演奏しているか」は非常に重要だったと思う。一方hideは、すべての音を素材として扱うことを厭わなかった。どう使ったっていいだとか、画一的な工業製品のように見ていただとかではなく、例えば一曲分として叩かれたドラムの音源は必ずそのまま使わなくてはいけないといった固定観念からするりと抜け出していたのだ。彼の先駆性を説明する上で、「自由」や「柔軟さ」は欠かせないキーワードだ。hideとI.N.A.はレコーディングのある時点では互いに険悪になるほどに徹底的なサウンドへのこだわりを持ちながら「ロック倫理」のようなものには縛られなかった。アティテュードや完成度への執着と、手法に関する制約を切り離して考えられるロックミュージシャンは、今の20代バンドマンを見渡してもそう多くはない。
例えば楽曲に使うスネアの音色を選定していく際に、ライブラリのスネアのカテゴリの中からではなく金属を叩く音を採用したり、想定したシチュエーションに合わせた音像にするために一度ミックスを済ませた音源をスピーカーで流して再度録音したものを使用するなど、セオリー無用の遊びが数多く語られている。『PSYENCE』(1996年)収録の「DAMAGE」では宮脇“JOE”知史と柳田英輝の演奏を編集し、無編集のものと混ぜ合わせた。次作『Ja, Zoo』(1998年)にもそれを応用し後々編集することを前提としてドラムを録音している。打ち込み音源ではなく人の手による演奏であるが、それを最小単位まで機械で切り刻み(この時用いられていたPro Toolsもいまだに世界中で使われているソフトだ)、再構築してしまう。hideは人間のグルーヴと機械のグルーヴが融け合った自身の音楽を、科学による強化人間になぞらえ「サイボーグ・ロック」として標榜した。『ROCKIN'ON JAPAN』においては生前最後となった1998年6月号収録のインタビューでの「ロックンロールをズタズタに切り裂いたりはするけど~」という発言は、ロック倫理やイメージとしての破壊とともに、曲作りのなかで物理的に音を細切れにするプロセスのことも指していたのかもしれない。