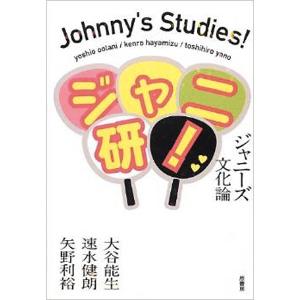戦後サブカル史におけるポピュラー音楽ーー円堂都司昭が「終末」と「再生」をキーワードに紐解く
「終末」と「再生」のループの粘り腰に期待
―それもまた一つの反復といえるのかもしれません。さて、戦後文化における一要素としてのサブカルチャーが果たした役割のようなものを、本書を書き終えた今、どのようにみていらっしゃいますか。
円堂:世界のあれこれを、個々人が受け止めるためのクッションみたいなものでしょうか。現実に立ち向かうための武器ってことになると、対抗文化、すなわちカウンターカルチャーになるので、私のイメージするサブカルチャーとは少し異なります。
『戦後サブカル年代記』と前後して近藤正高『タモリと戦後ニッポン』という本が出たのですけれど、これがとても面白い。音楽好きの人も読んでみるといいと思います。1945年8月22日に生まれたタモリの人生は、ちょうど戦後70年の歴史と重なる。この本は、彼の生涯を軸にして同時代の文化状況を語っていく。お笑いの人が主人公だから、タモリと戦後ニッポンとサブカルチャーといった内容になるわけですけれど、意外なほど私の本と話題にしたネタが被っていない。なぜかを考えてみると、タモリはジャズの人だというのがあって。昔、『抗議としてのジャズ』という音楽批評がありましたが、タモリはそういう観点からのジャズ好きではないんですよ。
―なるほど。彼の場合、カウンターカルチャー的なジャズの捉え方ではない。
円堂:むしろ彼は、「ナンセンスなもの」としてジャズを愛好してきた。若い頃、ジャズピアニストの山下洋輔周辺などとタモリが宴会芸に興じたことは伝説化していますが、彼は一貫して、意味のない音楽のほうが素晴らしいと言い続けてきた。本当は、そういう無意味さが、サブカルの芯の部分ではないか。デタラメ外国語を駆使したタモリの初期の芸「4カ国親善麻雀」は、国際的な緊張をギャグにしてナンセンスなものにしてしまう内容でした。私の本は「終末」がテーマだから、米ソの冷戦構造に対する反戦、反核といった気まじめな部分でのサブカルからの応答を書いています。とりあげた音楽も「戦争を知らない子供たち」のような反戦歌や忌野清志郎の反原発ソングとか、メッセージ性のあるものが多い。また、私の本では、SFの中から「終末」を描いた代表作として小松左京『日本沈没』を論じていますが、そのパロディ『日本以外全部沈没』を書いた筒井康隆は、タモリや山下洋輔に近しい人だった。
―確かに。小松左京的な観念性やシリアスさはタモリにはないですね。
円堂:だから、サブカルの全体像を知るには、『戦後サブカル年代記』と『タモリと戦後ニッポン』をあわせて読むのがいいのではないかと(笑)。
―『戦後サブカル年代記』で取り上げられているサブカル作品は、どちらかというと意味を求めるタイプですよね?
円堂:「終末」と「再生」というシリアスなテーマなので、そうならざるをえなかったんです。でも、意味を求めつつ……サブカルだからエンタメ化したり、斜に構えたりして意味がズレていく。小林よしのり『ゴーマニズム宣言』以降のサブカル化した政治語りもそう。最近、安保法制問題でSEALDsなどの国会前デモが盛り上がりをみせましたが、デモ前に高校生たちが「民衆の歌」を合唱したことが一部で話題になりました。これはミュージカル『レ・ミゼラブル』の1曲で、劇中では簡単なステップの振り付けもあるから、マイケル・ジャクソンの「ビート・イット」、「スリラー」みたいにフラッシュモブでも使われる曲なんですよね。
―ネタとして人気曲という共通点があると。
円堂:人気ミュージカルの名曲で、映画化されただけでなくネット動画のネタともなり、世界的に知られた歌を、ネットを介することでカジュアル化した社会運動がとりこむ。こういう形でも政治のサブカル化は進んでいる。一昨年に『ソーシャル化する音楽』という書名通りのテーマの本を出しましたが、社会運動も時代とともにソーシャル化している。私は基本的に、選挙での投票だけでなく国民の政治的意志表明のありかたが多様化し、カジュアル化するのは、よいことだと考えています。
-最後に、「終末」と「再生」のループは今後も続くのでしょうか。
円堂:音楽についていうと、私が洋楽ロックを本格的に聴き始めた70年代後半には、商業化し産業化したために既存の「ロックは死んだ」(セックス・ピストルズのジョニー・ロットン)といわれる一方、パンク、ニューウェイヴという次世代のロックが、インディーズを起点にして盛り上がっていました。疲労した既存のビジネスモデルではなく、制作・流通・楽しみ方などで別のスタイルを模索する音楽ムーブメントは、ハウス/テクノ、ヒップホップ、オルタナティブなど、後の時代にもありましたし、ゼロ年代以降の日本にみられたネット音楽隆盛もその一つでしょう。「終末」の宣告や予感と「再生」への希望は、たいてい一緒にやって来る。そして、CDの存在感は小さくなりつつありますが、幸いなことに音楽は今でも各地やネットで盛んに演奏され、相変わらず新しい曲も作られ続けています。こうした様々な環境変化への対応は、音楽以外の領域でも迫られるでしょうが、私は、悲観していません。「終末」と「再生」のループの粘り腰に期待したいと思います。