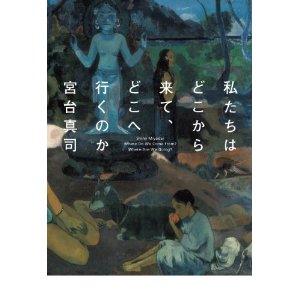Salyu『Android&Human Being』インタビュー
プロデューサー小林武史が語り尽くす、Salyu新作の全貌 なぜ“完全再現ライブ”に踏み切ったか?
■M.03「リスク」

ーー3曲目の「リスク」は、2曲目のサウンド的趣向を引き継ぎつつ、都市のギラギラとした欲望や人々のせわしない動きを連想しながら聴きました。
小林:「非常階段の下」では無機的に歌っていたSalyuが、ある種セクシャルに歌います。“デジタル娼婦”というくらいの佇まいで街にいて、夢と現実の交錯の中に入っていく。都市の灯りは夜の怖さを隠すが、だからこそ心のなかに闇を作ってしまう…そういう孤独感のようなものを表現したかったのかもしれません。いろんなリスクを冒して闇を埋めようとするんだけど、埋めきれない。そんな女心のようなものを描きたかったというか。
ーー夜のイメージの強い曲ですが、そうした“闇”や欲望のあり方、リスクと人間のありようを、音楽を作ることで肯定的に見るという面もありますか。
小林:そうですね、興味深いと思っています。アルバムを通じて、夢と現実のシームレスなところに入って行ったりする上で、この2曲によって(リスナーを)深いところに放り出したい、という思いはありました。歌についても、これだけ無機的な歌とセクシャルな歌が並ぶ振り幅が好きです。Salyuの歌はすごいな、とあらためて思いましたね。
■M.04「心の種」
ーー4曲目の「心の種」ではまたガラッと変わり、柔らかいポップソングの世界です。
小林:この曲をここに持ってきていることが、このアルバムで一番意欲的な部分です。続く「有刺鉄線」と合わせて、モノローグが続くんです。都市から離れて、自然の中にいる自分を有機的に捉えていく歌ですね。アレンジもそれに則した生の演奏で、非常にほっこりとしたキャッチーさを持ってきています。紙芝居のようなアナログ感ですが、今回のツアーにも参加しているギタリストの名越(由貴夫)くんや、ベーシストのキタダマキとドラムのあらきゆうこが、とてもピュアな演奏で楽曲を盛り上げてくれました。相当にアーティスティックな彼らが、“お遊戯”をしているような感覚で。
ーーライブでもここはひとつのハイライトになりそうでしょうか。
小林:そうですね。“ライト”という意味では、1~2曲目には“太陽”の存在が感じられない音作りになっています。あったとしても人工のサーチライトのようなもので、この曲でやっと、生命を作る太陽という存在をグッと感じることができる。植物の種は直接太陽光に当たらないのに、土の中でも太陽の存在を感じて芽を出すでしょう。都市での生活ではなかなかできませんが、太陽とともに生きていくのは、人間にとっても幸せなことだと思います。しかし、人はやっぱり夜が怖いから、人口の太陽を作ってしまった。僕たちの日本は、人工的な“太陽が燃える仕組み”からできた爆弾を落とされた、唯一の国でもありますから。
ーーここで光が入ることによって、ステージは劇的な転換場面となりそうです。
小林:そうなんです。もっとも大きく変えるところです。ボーカルについても、Salyuが真っ直ぐに歌うところに、太陽のような光を感じますね。
■M.05「有刺鉄線」
ーー次の「有刺鉄線」もバンドサウンドですが、一方で不穏な雰囲気もあります。つながっていながらも、「心の種」で描いた日向感とはまた違う局面に入っていきます。
小林:「心の種」の紙芝居的素直さに比べると、この曲はだいぶひねていて、自分の心を覗きながら物語が展開していきます。「有刺鉄線」というものは、人間が日常で目にするものの中でもっとも「嫌なもの」のひとつでしょう。人間の都合で置いた、他を寄せ付けないもっともドライで冷たい閉鎖的なものですよね。
けれど、植物はその有刺鉄線さえつたって生きようとする。僕はそれを実際に見て、物語にしようと考えました。大サビで<隔てようとする力と 生き抜こうとする力>というフレーズがありますが、その混在はこの世界のいろいろな部分に見受けられます。この主人公はたぶん、生きようとしているのか拒絶しようとしているのか、その力が混在している状態で都市の片隅で生きているんだと思いますが、ある段階でその状態を脱していく物語にしたかった。この曲は珍しく歌詞から考えていました。ちょっとしたお芝居を作るような感覚で作っていったんですが、なかなかうまくできたかな、と思います。
ーー歌詞からサウンドを生み出していくのはどんな作業でしたか?
小林:僕は映画音楽もやりますから、物語やシチュエーションから作るのはわりと得意だし、楽しかったですね。ただ、これがSalyuの歌にどう合わせるか、というところはすごく悩んだ部分です。メロディをオルタナティブにしすぎるより、日本人がグッと来る、わかりやすいメロディを重ねあわせていく――演劇的に見せた方がみんな感情移入してくれるのではないかと考えました。この曲のメロディやアレンジはエモーショナルな傾向の曲だと思いますが、主人公の心の動きは冷静で、ある種求道者のようなところがある。Salyuはそれに対して、一人の少女としてあまり強いキャラクターを作らないで歌っていて、逆に言うと、どんな人にでも起こりうるキャラクターを作ったんだと思います。そういう子に起こったひとつの物語でありささやかな思想や哲学のようなものなのかな。
ーーあえて日本的なメロディにしたと。
小林:もっと言うと、フォーキーなメロディですね。歌謡曲や、日本の流行歌に通じるような音階を使いました。日本の場合、よくあるようなロックやトランス感のある音楽には、すごくフォークメロディが多いんです。日本のフォークとトランス感はどこか一致するものがあるのか、組み合わせている人は多いですね。そこに何か漁民、農民のリアリティがあるんじゃないかな。
ーー作曲者として自然に出てくるのは、今おっしゃったようなフォークメロディですか。それとも、ビートルズ的なロック/ポップの流れにあるものですか。
小林:ビートルズ的なホーリーなメロディは確かにあります。ただ、自分で言うのものなんだけれど、幅は広いです。僕らの世代は戦後20年も経っていない中で、海外のロックやポップスがものすごく元気だった時代に育っていますから、そのあたりを大量に咀嚼しました。小さい頃にビートルズもアメリカンポップスもボブ・ディランも出てきましたし、サイモン&ガーファンクルもいました。バート・バカラックももういたわけだし、コード進行やメロディの宝庫の時代に育ったわけですよね。