サニーデイ・サービス『苺畑でつかまえて』× 豊田道倫『SHINE ALL AROUND』リリース対談
【新春放談】曽我部恵一×豊田道倫が語る20年の交友、そして2016年の音楽
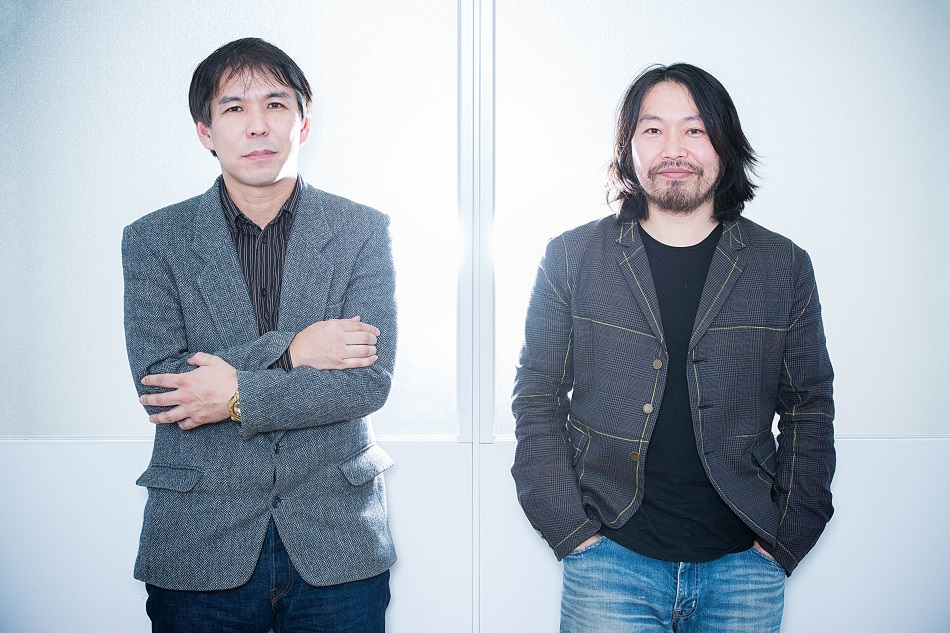
シンガーソングライターの豊田道倫がCDデビュー20周年記念アルバムとなる『SHINE ALL AROUND』を2015年12月30日に、曽我部恵一が率いるサニーデイ・サービスがシングル『苺畑でつかまえて』を2016年1月15日に、それぞれリリースする。1990年代より、時にライブで共演を果たすなど長く親交を続けてきたふたりは、互いの表現からどんな刺激を受け、今どんな音楽を生み出そうとするのか。90年代から現在までを振り返りつつ、それぞれの表現論や新作についてまで、たっぷりと語り合ってもらった。
「曽我部くんとは“地方から出てきた感覚”が近い気がしていた」(豊田)

ーーおふたりはこの20年間、それぞれ音楽を作り続けるなかで、互いのことをどんな風に意識していましたか。
曽我部:僕が豊田くんをすごいと思ったのは、96年ぐらいにMILK(恵比寿)で一緒にライブをやった時で、それ以来ずっと聴いてきました。すごくいい歌を歌う人だな、と思って。豊田くんが次に何をやるのかはいつも気にしていますね。最近はTwitterとかの発言もチェックしています。もう長くやっているので、先の心配はないかな(笑)。
豊田:僕らが始めたのは渋谷系が一気に出てきた時期で、中には地方出身のシンガーソングライターもいたけど、特に曽我部くんは“地方から出てきた感覚”が近い気がしていた。東京をひとつのゲームのように感じているところとか、抱いているロック感とか。サニーデイ・サービスの『MUGEN』とか『24時』のちょっと暗い感じは特に印象深かったけれど、あの感覚はなんだったんだろうね。いま、ああいう長いスタジオワークができる人もいないし。あれはやっぱり、若い時にしかできない、地べたを這いずり回りながらも何か掴む感じがあったのかな。それにしても、最近の曽我部くんの圧倒的なペースにはちょっとびっくりしてます(笑)。
曽我部:でもね、今年は何も出なかった。ライブ盤しか出なかった。2〜3年前くらいは、たしかにポンポン出していたね。
ーー多作で、これまで20年ほぼ休みなくやってきたというのは、ふたりの共通点のひとつかもしれません。
豊田:まぁ、そういう意識もないけどね。普通にやっていたら、1枚、また1枚とできていったというか。大体、作ろうと思って作れないからね、ふっとできる。でも、今回は作ろうと思って作ったら、失敗しちゃった(笑)。今年20周年だから、頑張ってやろうと思ったら、ちょっと空回りした感じ。
曽我部:それくらい“作ろう”っていう意識があったことにびっくり(笑)。でも、豊田くんは実はすごくしっかりしているよね。たとえば、ちゃんと年賀状をくれるとか、メールはすぐ返事するとか、お子さんにしっかりごはん作るとか。料理でも、野菜の煮物とか、そういうちゃんと栄養価の計算されたものを作るから、根はしっかりしている人なんだなぁと思う。そういうベースの上で、音楽で何をやろうかっていうのが豊田くんなんだと思う。僕の場合、私生活は割とズボラなところがあるので、そういうところが違うなって感じますね。
ーー曽我部さんはレーベル運営も含めて、コンスタントにアウトプットしているので、そういう面ではきちっとしている印象もありますが。
曽我部:でもそれは、周りの人の協力があって、自分はそれに乗っているだけだから。自分がリーダーシップを取っているわけではない。だから、僕からすると豊田くんはちゃんとしているなって思います。
豊田:僕はそんな、何も考えてないけれどね。
曽我部:豊田くんは何も考えてなくても、ベースがしっかりしてるし、それが全部に出ていますよ。どこか気品があるというか。ちょっと語弊があるけど、だからこそどんな音楽をやっても良いんですよね。僕は豊田くんにいつもそれを感じていて、必ず安心して聴けるところがあるんです。発言とかファッションも含めてね。ジャージっぽい時もあったけれど。
豊田:気品があるって言われるのは面白いな(笑)。たしかにベーシックなものはどっかにあるんでしょうね。曽我部くんは四国っていう、大阪からすると海外の人だから、少し違う感覚もあるのかも。ミュージシャンでいうと七尾旅人とか大森靖子とかも、本州の人とは違う独特の力を持っているよね。ちょっと怖いというか、動物的な感覚があるというか。
曽我部:たしかに四国出身はそういうところがあるかも。
「なにか決意があって、ずっと作ってるわけではない」(曽我部)

ーーいま、90年代の頃の音楽シーンを振り返って、大きかったと思う出来事は?
豊田:曽我部くんは当時、はっぴいえんどとかへの憧れを割とはっきりと言ったでしょ。それが、わーっとみんなに広まっていったのはデカかったよね。僕はその時、あんまりよくわかんなかったんだけどね。あの辺から、日本のロックをもう一度ちゃんと聴こうという雰囲気が作られたと思う。
ーーたしかに、90年代前半に10〜20代だった若者たちがこぞって、はっぴいえんどを聴くようになった。それは今に至るまで続いているように思います。
曽我部:最近ではもう、定番になってますよね。当時は、たとえばネオアコとか60年代のネオGSの人たちももうとっくにいたし、全部みんな開拓されてたから、自分たちのルーツというか、どういう風に自分たちを見せていくかっていうのはすごく意識してたんですよ。ヒップホップの人たちだったら、ファッションとかでやり方があるんだけど、ギターバンドは割とそういうのがないので、のっぺりして見えるかなぁと思って。それで、僕らははっぴいえんどとか、四畳半フォークとか言って、田舎から出てきたものですから、そのいなたさにアイデンティティを求めたんでしょうね。「四畳半フォークの今版です」って言っちゃおう、みたいなところはありました。
豊田:僕はその時、大阪にいたから、割とぐちゃぐちゃなシーンに参加していました。ノイズとかジャンクばっかりだったんだけど、でもポップスもすごく好きな自分がいて。自分はミクスチャーだと思っていましたね。だから、はっぴいえんどみたいな正統派のロックとはちょっと遠かった。大滝詠一さんのナイアガラは好きだったけど、はっぴいえんどは当時、自分には偏差値が高過ぎてよくわからなかった(笑)。
曽我部:僕ははちみつぱいの方がひょっとしたら、個人的には好きですね。鈴木慶一さんがやってた、ムーンライダースの前身のバンドで、あれが自分の青春って感じがするんですよ。呑んだくれて、朝方に撮った感じのジャケット写真とか、「なんか、青春ってこうだよなぁ」って思わせてくれます。
ーー90年代後半になると渋谷系のムーブメントも終息していって、だんだんと活動を抑えるバンドも出てきましたが、ふたりは2000年代に突入してからも意欲的に活動していますね。
曽我部:僕の場合、バンドが解散して、一人になってどうしようってところから、2000年が始まってるんですよ。最初は手探りだったんですけど、自分がレーベルを始めた2003〜2004年から、だんだんと軌道に乗った感じです。とにかく作っていないと、前に進めないような気がして、がむしゃらにやっていました。レーベルを始めたのは行きがかり上というか、メジャーも出してくれない感じだったし、レーベル移籍するっていう手もあったんですけど、契約金がどうこうという話も面倒だったので、じゃあ自分でやろうと思い立った感じです。
豊田:僕はただ、まだ東京に観光気分でいたから、すぐ帰ろうかなと思いながらもぐずぐずいる感じでした。1998年にたまたま<east west japan>とメジャー契約して、『実験の夜、発見の朝』をリリースして、翌年契約をやめちゃっているけど、そういうのは別に。でもレコーディングは好きだったから、それはやっていこうというのはずっとあったかな。
曽我部:『実験の夜、発見の朝』、新宿のヴァージンストアで買ったなぁ。まぁ、僕らはなにか決意があって、ずっと作ってるわけではないですね。
豊田:ないです。そうなんです。
曽我部:自主レーベル作品は2004年の『SING A SONG 』がはじめて?
豊田:そうです。大阪にそろそろ帰ろうと思って、未発表曲集を作った。
曽我部:あれだけ今までの作品とちょっと違いますもんね。その前の『実況の夜~スタジオライブ IN ラジオたんぱ』は?
豊田:<BUMBLEBEE>から。どこいっても、ほんと迷惑ばっかりかけて(笑)。ほんとに売れなかったなぁ、『実験の夜、発見の朝』とか。お金をいくらでも使っていいっていうから、すごいつぎ込んじゃったけど。いつも「これが最後」って思ってるのはほんとの話で、「なんかもうええんちゃう」みたいな感じではあるんですよ。




















