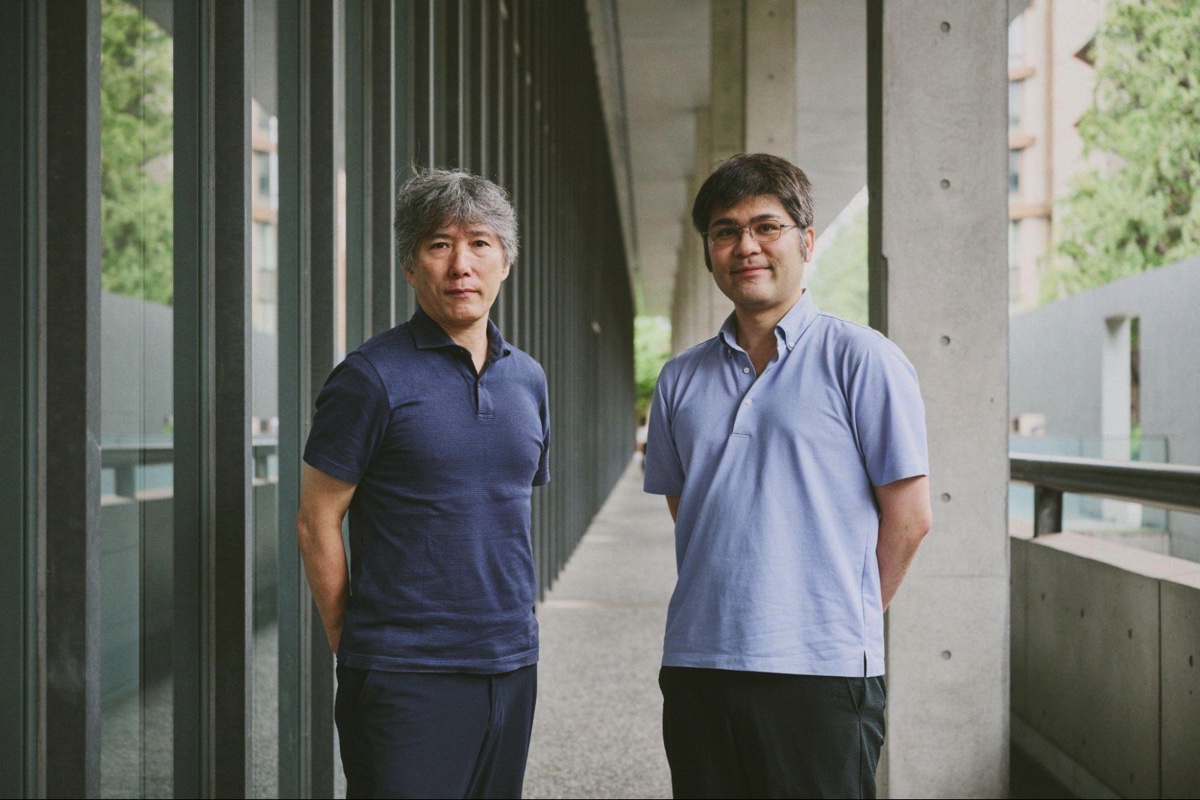コロナ禍から5年でわかった「都市とメタバースの過去・現在・未来」東大・小泉秀樹教授×KDDI・川本大功が語り合う“リアルな街との連動”が重要な理由

都市連動型メタバースという概念
――あらためてですが、「都市連動型メタバース」とはどのような概念なのでしょうか?
小泉:「都市連動型メタバース」は、リアルな都市空間と連動したメタバースを作る点ではデジタルツイン的なものですが、実はデジタルツインではありません。
デジタルツインとは、リアルで起きていることを再現するものです。それに対して都市連動型メタバースは、リアルの空間体験に近いものと、メタバース上であるからこそ新しく体験できるものを組み合わせたものです。「バーチャル渋谷」の取り組みは、都市的なものの疑似体験につながる点で、私たちはすごく歓迎しましたし、これがメタバース活用としてすごく大事だと直感しました。
一方で、メタバース、あるいはそれに類するオンラインツールやゲームの普及は、人々が外出しなくなる可能性を高めるかもしれません。
ポジティブな面では、遠距離通勤をしなくても働けるようになります。東京のような大きい都市では、ウォーカブルなエリアに住める人は経済的に限られているので、それを解消しながら人々の生活の質を高めるために、メタバース的なものを活用することが可能です。
実際に、オフィス需要もコロナの前後で変わりました。ICT系企業や広告代理店はほとんどオンライン出勤を推奨しているので、社員が居住地として選ぶ場所は、鎌倉や新潟など、いろいろなところが候補に挙がりました。彼らは自由に住む場所を選択しているわけです。
しかし、人に会いに行き、エンターテインメントを一緒に楽しむ――例えばクラブにみんなで行って盛り上がるといった行為も、メタバースで代替される可能性がありますし、部分的にはすでに代替されつつあります。おそらく、リアルの要素の9割くらいはメタバースに置き換えられると思います。これが進んでいくと、私たちの生活空間や都市に、大きなインパクトがもたらされるはずです。
――盲点でした。ついついメタバースを起点に考えがちですが、都市研究の視点に立てば、メタバースというある種のカウンターパートにより、リアルの街がどう変化していくかは、重要な観点ですね。
小泉:現状は、デバイスや通信環境に課題があるし、コストの兼ね合いから、まだ社会へ広く普及する段階ではありません。しかし、時代が進めば次なるブームが起こり、そのときにさらなる代替の動きが起こり得ます。そうやってサイバー的なものが社会の中に定着していくと、私のようなリアルの都市を考える身は、リアルな都市のあり方がどう変化していくのかを、ある種危惧しながら見ています。
どんな暮らし方をするのか。どんなライフスタイルをみんなで作り上げていくのか。この議論が先にあり、その中でメタバースをどう使うのか考えなければいけない。そのソリューションやトライアルが都市連動型メタバースであり、渋谷未来デザインとしても積極的に取り組むべきプロジェクトとして位置付けられたと認識しています。
川本:「バーチャル渋谷」が生まれたのは、渋谷未来デザインさんや渋谷区観光協会さんが、街を起点にどう拡張できるかをずっと考えていたのが大きいです。なので、都市連動型メタバースは「リアルを代替するもの」ではなく、「リアルを拡張するもの」だと明確に示しています。
当時のチームでよく言っていたのが「マントル理論」です。リアルは核であって、その周辺にあるのがデジタルだったり、サイバー的なものだったり、メタバースだったりする。だから、核はどうしてもリアルなんだよということを、チームとして共有していたんですよね。そこが多分、他のバーチャル側から来ている取り組みとの大きな差別化ポイントであり、視点の違いだったのかなと。
プレイス・アタッチメントを形成する媒体として
――実際、都市と連動してメタバースの取り組みを進めていくにあたって、自治体の方からはどのようなリアクションがあったのでしょうか。
小泉:渋谷の場合は分かりやすく、ハロウィンの人流集中の問題へのソリューションとして機能しました。ハロウィンを渋谷で楽しんでほしいけれども、三密はダメなので、「メタバース空間で楽しんでください」と伝えたんです。渋谷に愛着は持ちつつ、ハロウィンの人流を制御できる可能性がある。明確な補完関係の存在が、渋谷区が私たちに協力してくれた一番のポイントでした。
また、うちの学生たちは「バーチャル渋谷」以後生まれた「バーチャル◯◯」を全部リストアップして、実際にユーザーとして滞在し、どう利用されているのかを調査しました。このとき、実際にそこに滞在するユーザーにインタビューもしたそうですが、「その場でインタビューができる」ということ自体がメタバースのメリットですよね。
そしてインタビューの結果、面白いことが分かりました。やはり、利用者の属性として多いのは、一度はその街に行ったことがある人なんです。一方で、まだ訪れてはいないが、関心を持っている人も多い。実際、「バーチャル◯◯」を初めて訪れた人は、実際の街に行ってみたくなったという人が多かったんです。そして一度行ったことがある人も、もう一度行ってみたいと思ったという人が多かったんです。
こうして考えると、都市連動型メタバースは「プレイス・アタッチメント(場所への愛着)」を形成する、よい媒体になっているのかなと思います。
一方、「バーチャル渋谷」の場合は、都市連動型メタバースの取り組みそのものに関心を持つ人が多かったんです。だから、渋谷に行ったこともないし、渋谷に行く気もない。けれど、「バーチャル渋谷」を楽しみたい。そんなスタンスの人がかなりいました。
川本:実際、渋谷のスクランブル交差点周辺を再現した「バーチャル渋谷」は、最初のイベントでも、参加者みんなが「渋谷に行った感」を持っていましたね。ゲストの方も「この街角でスカウトされたんですよ」と言いながら、街の空間記憶を呼び起こして喋っていたのが、すごく面白かったです。空間記憶や都市のイメージが、現状の技術でも多分連動しているんだろうなと。
小泉:「バーチャル渋谷」のイベントでは、そのスクランブル交差点でコンサートも開催されましたよね。多分、渋谷の文脈をよく知らない人は、あの広場で実際にコンサートをやっていると思うかもしれません。でも、リアルの渋谷をよく知っている人たちにとっては、それは「あそこでやりたかったもの」で、ある意味では様々な意味で実現できない夢を、疑似体験していることになる……というのも面白いです。
川本:私自身も運営として関わりながら、いちユーザーとしてイベントを楽しんでいましたが、「渋谷のスクランブル交差点でライブを見て、有名人に会った」って記憶が、しっかりと残っているんですよ。
こうした体験も加味すると、都市連動型メタバースは、機能ではなく心理的に都市とのつながりを生み出す、新しいタッチポイントたり得るのかもしれませんね。
小泉:「アタッチメント」自体、心理学の用語ですからね。人が体験する以上、心理は重要な要素の一つになりますし、都市へのプレイス・アタッチメントは、都市づくりの重要なキーワードの一つです。
空間を作っても、そこに人が来なければ意味がないし、ポジティブな体験を得られなかった場合も意味がないんです。そして、ポジティブな体験をしたかどうかを示す、分かりやすい指標が「アタッチメントを持っているか」です。空間・都市へのポジティブなアタッチメントを、リアルとバーチャルが入り混じる体験からどう創出できるかが、今回の都市連動型メタバースの面白いポイントだと思います。
川本:いわゆるイマーシブコンテンツにおいて「没入感の高い状態」とはよく言われますが、これはただ単にVR/MR化すればいいわけではなく、ユーザーがそこでの体験を通して、「それがリアルかバーチャルかは重要ではない」と感じられることが、最も重要です。場所に根付く記憶やイメージを呼び起こすサービス・体験設計が、今後のカギになるはずです。
――ある場所に行く前に、メタバースを通じて接触することで愛着を持つ。逆転的ですが、「その場所に関する存在しない記憶」を作ることも可能ですよね。
小泉:予習を通して空間体験のイメージを醸成することで、現地を訪れたときに「本当にあるじゃん!」と思える、二重の喜びが作り出せますよね。そんな積み重ねができることも、重要なのかもしれないですね。
川本:以前、「バーチャル渋谷」ではバーチャルハロウィーンでの『名探偵コナン』のコラボイベントが実施されましたが、主人公のコナンくんとスクランブル交差点で会って一緒に写真を撮るなんて、現実では絶対ありえないですけど、あのイベントを体験した私の中では“存在する記憶”なんですよ(笑)。そのとき、バーチャルであるかどうかはどうでもいい。「渋谷のスクランブル交差点のイベント会場にいた」と感じられることが、なにより重要なんです。
リアルとメタバースの横断のカギになるもの
――プレイス・アタッチメントが都市連動型メタバースのコアになるとのことですが、今後の5年、10年と経過していくにあたって、どんな方向の発展があり得て、そこにどのような技術が必要になりそうでしょうか?
川本:Society5.0やWeb4.0といった議論で「リアルとバーチャルの融合」が気軽に言われがちですが、これを分解すると、「リアルとバーチャルをどう連動させるか」「それぞれの空間や環境を超えて、どうインタラクションさせるか」が挙げられます。
現状では、リアルとバーチャル、リアルとデジタルを横断する、インタラクションの手段が少ないです。要素は揃ってきたものの、まだまだ伸びしろが大きい領域です。今後は、2つの領域・空間・レイヤーの横断を実現するべく、イマーシブ/XR技術、空間コンピューティング、ロボティクス、IoTなどが、総合的に発展していくことがカギかなと思います。
小泉:ロケーションベースエンターテインメントやロケーションベースビジネスは、私たちの研究領域でもすごく注目されています。例えば、ナイアンティックの取り組みですね。けれども、その取り組みはグローバルで、楽しみ方は画一的です。
我々が考えているロケーションベースエンターテインメントのあり方は、川本さんが提示されたような、リアルなものにサイバーなものを個別に上乗せするものです。例えば渋谷の公園通りのイベントで、イベントに合わせたサービスがXRで上乗せされて、体験価値をより高めるもの。あるいは、XRエアレースや、リアルな活動の上にアニメキャラクターを重ねる、といったものです。
一方で、「バーチャル渋谷」はリアルな空間をバーチャルな世界へ、エンターテインメントとして消費できる空間として再構築したもの、つまりリアルなものをバーチャルに持ち込んだものです。その成果から、リアルとバーチャルを、双方的にどうつなげていくかも考えていけると思います。
例えば、渋谷公園通りで、雪が降った日にだけ、公園通りでバーチャルなスキーを体験できるとか。海外だったら、朝誰もいない時間帯に、YouTuberなどがゲリラ的にそういったことをすることがあります。こういったことを、本当は日本人もやりたいんですよ。行儀がいいので踏み切れないだけで(笑)。それがバーチャルに体験できるだけでも、相当面白いはずです。
実際、公園通りは歩行者がいろいろな楽しみ方ができる場所に変えた方がいい場所です。メタバースならば身体性をともなった体験ができるので、そこで得られた体験と評価を、リアルの空間活用へフィードバックしていく流れができるはずで、試していけると面白いものが生まれると思います。
ただ、これは私たち、街づくりの世界から見たフィードバック提案に過ぎず、実際には様々な循環があるはずです。だからこそ、現在取り組んでいるプロジェクトには、ユニバース(リアル)とメタバースを循環させて、つなげていく、といった意味を込めて、「インターバース」という言葉を与えています。
インターバース的なものが、リアルの空間・世界と、メタバース上の世界の相互連携の上でどんなことができるかは、現在考えている最中です。補完的なものなのか、レイヤーとして重なるものか、どんな関係性をデザインできるかが今後の重要な課題だと思います。
標準化とルールメイキングの重要性
川本:インターバース的なものや、ロケーションベースの体験は素敵なことですが、コンテンツや施設ごとに車輪の再発明が多々起きています。なので、技術の標準化も重要な課題です。バーチャルシティガイドラインでは「文明的相互運用性」と呼んでいますが、メタバースにUSB Type-Cのような標準規格が用意できるのか、アバターなどの活動体も標準化できるのか、といったことです。
過熱気味のブームが落ち着き、ライトユーザーやライトなビジネスパーソンが離れたいま、残った人々で腰を据えて考え、議論し、ルールを一定の共通理解として作り、明文化していくことも、ものすごく重要だと思います。こうしたプラットフォームを超えて、業界として共通化したルールを「文化的相互運用性」と呼んでいます。
――今後の揺り戻しのなかで、次にライトな人が来るときに「標準はこれです」と提示できれば、参入障壁はグッと下がる可能性がありますね。
川本:そうしておかないと、コンテンツの流通量も増えないんですよね。ロケーションベースは特に準備しておかないと、後でまたブームが来た時に技術的なハードルによって市場が広がらないんじゃないかと危惧しています。
また、権利の保護、ユーザーの保護といった観点や、ソフトロー/ハードローで連携する共同規制アプローチも、ガイドラインに盛り込まれています。その議論においても、価値観を含めて譲れないものと、状況によって柔軟に変えなきゃいけないものの切り分けが、すごく重要なので、「いま議論しているのはどっちなんだっけ」と明確に分けていく必要があります。混ぜて議論していると危険です。
――その旗振り役を、バーチャルシティコンソーシアムが担っていく、という理解でよいでしょうか。
川本:一定担える部分もあるかもしれませんが、業界でも役割分担がなんとなくでき始めているような気もします。国が動いている部分、私たち民間企業が動いている部分、産官学で横断して議論する部分などなど。そうした分担ができることもまた、バーチャルシティコンソーシアムのこれまでの活動が結果的に貢献出来ていたらいいな、とは思いますね。
ロボットが品出し、従業員はスマートグラスを着用……KDDIとローソンがAI活用で店舗業務を変える実証について発表
KDDIはローソンと協力してAIを活用した施策について実証していることを発表した。本記事では3つの実証を取り扱う。 AIとロボ…