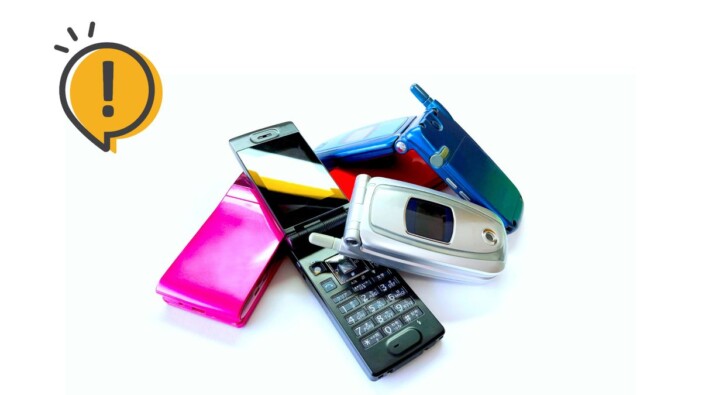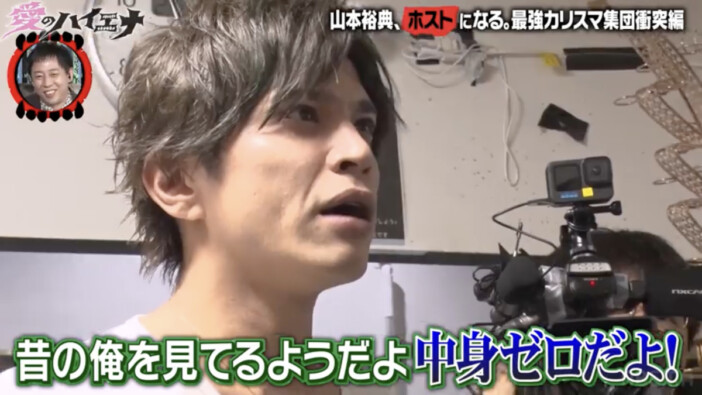渋谷慶一郎が“亡き妻の顔”を持つアンドロイドを作った理由 ウェイン・マクレガーとの共同プロジェクトなどを含めて話を聞いた

音楽家の渋谷慶一郎が6月18日、「アンドロイド・マリア」の全貌を正式に発表した。
これは渋谷が制作した最新のアンドロイドで、6月7〜8日に大阪で行われたPRADA MODE OSAKAでお披露目され大きな話題を呼んだばかり。また、6月10日に都内で行われた英国ロイヤル・バレエ団常任振付師で、ヴェネツィア・ビエンナーレにおけるダンス部門の芸術監督サー・ウェイン・マクレガーや建築家・妹島和世との新作舞台プロジェクト(2027年初演予定)にも出演が告知された。
アンドロイド・オペラを中心に約10年に渡って人型ロボットとの作品を発表してきた渋谷だが、自ら気鋭のアーティストやエンジニアを集めてゼロから全く新しいアンドロイドを作り上げたのは今回が初となる。しかしながら、どう見ても渋谷の亡き妻としか思えないビジュアルにしたのはなぜなのか。(小池直也)
彼女の死を目の当たりにしてから「彼女はどう思っているのだろう、どう感じているのだろう」と長い間、自問していた
――このタイミングで新しいアンドロイドを作ったきっかけは?
渋谷:2年くらい前から構想していました。これまでに何体かのアンドロイドと一緒に作品を作ってきたけど、もっと美しくて複雑かつ豊かな表現が可能なアンドロイドはないのかと。実は世界中のアンドロイドを製造する会社と交渉したりもしましたが、コンサートという特殊な運用を考えるとうまく条件が合うものがなく、仕方なく自分で作ってしまいました(笑)。
今まで使っていたアンドロイド(オルタ)は大阪万博で忙しいようだけど、その割に僕にオファーが来るので作って良かったなと思いました。

――どう見ても「アンドロイド・マリア」は亡くなられた前妻のマリアさんを基にしていると思うのですが……。これについては?
渋谷:アンドロイドを作るときに一番悩んだのが顔でした。よくあるのは、著名人とか世界一の美女をAIで合成してとかだけど、明らかにつまらない。で、アンドロイド・オペラ以前から紐解いて考えてみたら、僕の最初のオペラ『THE END』もマリアの死がきっかけだったし、それから一周してアンドロイドとして生を与えるというのは僕しかできないなとも思って。あとは「死はひとつではない」というのも『THE END』のときからテーマになっていたこととも一致したというのもあります。
――「死はひとつではない」というのは?
渋谷:自分の死は自分では決められない、これは当たり前だけど死んだら死にましたと自分では言えないですよね。そばにいた誰かがその人の死を受け入れて人に話したり、それが伝わっていくことで生と死の境界が構成されていくという実感があったんです。
僕は彼女の死を目の当たりにしてから「彼女はどう思っているのだろう、どう感じているのだろう」と長い間、自問していました。そしてそれを伝えられないのが死なんだなと時間をかけて理解しました。
生物学的な死という圧倒的な現実を起点に本人とは関係なく様々な死が共有されていき、それは同時に記憶という形で様々な生も存在し続ける。だからアンドロイドという形で全く新しく再生するというのは僕にとっては自然なことです。そして、自分が経験した現実とアンドロイドという未来を託す創造物が邂逅するような奇妙に創造的な経験をしているとも感じています。
――この「アンドロイド・マリア」はAIを搭載されているとのことですが、こちらは?
渋谷:当然、AIによる多言語での会話などは非常にスムーズに行えるし、性格というかパーソナリティーも与えています。AIの回答は平均的で模範的なものが今のところの典型なので、アンドロイド・マリアの性格は「綺麗なのに異様にロジカルでせっかち」みたいなのがいいかなと思って、最初は「誰を学習させる? イーロン・マスク?」とか冗談で言ってました。
でもアンドロイドのプログラムを担当しているコンピュータ音楽家の今井慎太郎さんやアーティストの岸裕真君から「ロジカルでせっかちなら渋谷さんがいいんじゃないですか?」と言われて、最初は拒否したんですが、AIの学習がしやすいとかいう現実的な利点に勝てず、顔はマリアで性格は僕に近づけるという気が狂った方向でスタートしました(笑)。
このプロジェクトの話を外人の友達からは「Are you fine?」と心配されたりしますけど(笑)、先日の大阪のお披露目にマリアの実のお兄さんが来てくれて「高校の頃の自分に似てる」と言って喜んでくれたりして、意外にそばにいる人間ほどその死と再生のような途方もないことを自然に受け入れて前に進めるんだなと思いました。
もうAIは当たり前なことしか言わないし、正解がどんどん出てくる世界だから、こういう偏った存在っていうのはやっぱり必要なんじゃないかって思います。予想もつかないことを言い出した方が面白いから。