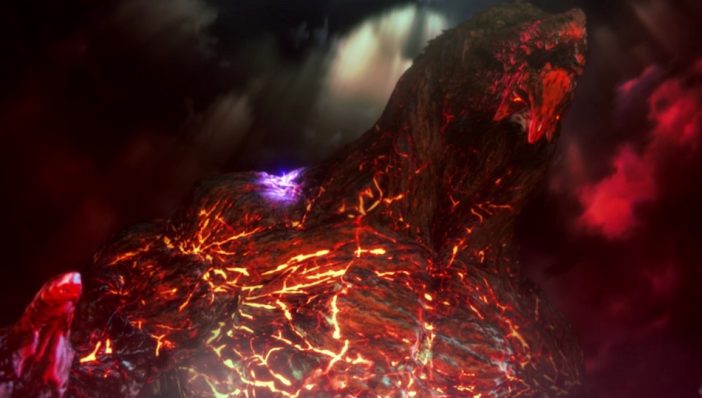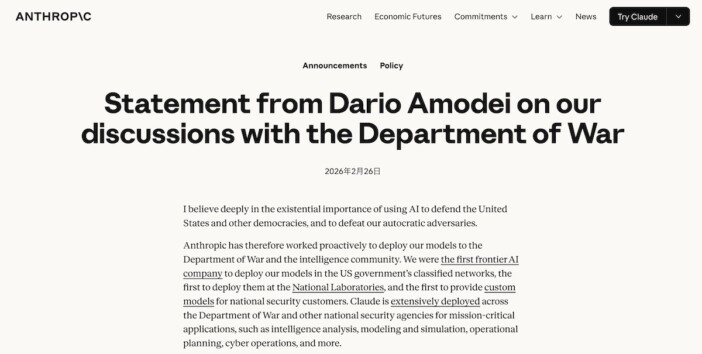『ニンジャバットマン』テクノロジー描写に見る、西洋世界と東洋世界の調和

日本の戦国時代にタイムスリップしたバットマンが、戦国武将となったジョーカー、ハーレイ・クインらと“戦(いくさ)”を繰り広げる。『バットマン』映画化権を持つワーナー・ブラザースが、日本のアニメ制作スタジオに依頼して生まれた、奇想天外なアイディアが発揮された映画が本作『ニンジャバットマン』だ。しかし、日本を舞台にしたというよりは、本作は日本アニメのなかにバットマンというキャラクターを放り込んだようなバランスの作品となった。
バットマンといえば、経済力を活かして開発した、バットモービルなどの乗り物、ブーメランとして使えるバットラングなどの武器、万能ベルトなどのガジェットや通信機器などを使うことで、スーパーパワーを持っていないという弱点を、テクノロジーによって補いながら戦うヒーローである。そんな文明の利器が、戦国時代ではうまく働かない。バットマンは不利な条件下で、大勢の凶悪なヴィラン(悪役)たちと、どう戦うのか。
ハイテンションな展開が見どころの『ニンジャバットマン』だが、ここでは、ここまで極端な日本的センスを感じる作品になった理由や、テクノロジーの描写を足がかりに、本作に奥行きのあるテーマが存在しているということを明らかにしていきたい。
アメリカ人が漠然と想像する、サムライやニンジャなど「かっこいい日本」のイメージを、日本人の側からさらに強調して提供するという『ニンジャバットマン』の作風は、日本のアニメスタジオ、GONZOが制作し、アメリカではサミュエル・L・ジャクソンが声優を務めたTVアニメ『アフロサムライ』(2007年)を想起させる。その原作漫画を描いた岡崎能士(おかざき・たかし)は、本作のキャラクターデザインを担当している。
監督は、TVアニメ『ポプテピピック』でも話題になった神風動画の代表、水崎淳平だ。本作を制作している神風動画は、日本では早くからCGを活用した作画による、実験性を感じる刺激的な映像で、ミュージック・ヴィデオやTVアニメのオープニング、エンディング映像、TVゲームにおけるアニメーションなど、アニメ業界の中で、「飛び道具」的な役割を果たしてきた。本作では、その持ち味を駆使し、クライマックスがいつまでも持続するような、派手なシーンを息切れせずに連打していく。大変な作業だが、それこそが、このスタジオの得意とするところなのだ。本作では、CGでありながらコミックの風合いを出す手法を使っているが、これは神風動画を代表する仕事の一つである、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのオープニング映像でも見られる、評価の高かった作風である。

さらに本作の破壊的なイメージを決定づけたのは、中島かずきの脚本であろう。劇団☆新感線での数々の舞台脚本、アニメでは『天元突破グレンラガン』(2007年)、『キルラキル』(2013年)など、熱血とケレンある、エクストリームな作風が持ち味である。これらアニメ作品が、いわゆる「ベタ」といわれる類型的な熱血展開を、ギャグになるまで極端に追求することで、どこかに冷めた批評性も存在するような娯楽作になっていたように、本作も自覚的に、バットマンやヴィランという存在を、熱血アニメの典型的世界のなかに置いてみることで発生する、違和感もしくは親和感を、物語を構築しながら楽しむ余裕を持っているように見える。
この座組から導き出されるものが、本作のような、ある意味ふざけているようにすら受け取れる、悪ノリ感である。しかしこれは、むしろそれぞれが真面目に、役割のなかで自分の能力を最大限発揮した結果だということがいえよう。

DCコミックスで連載されたコミック『バットマン』は、都市犯罪が急増していた1939年に発表された。両親を犯罪者に殺害され、一生を凶悪犯罪と戦うことに費やすことを望んだ男、ブルース・ウェインは、偶然に部屋に入ってきたコウモリをヒントに、まさにコウモリのような姿で都会の闇に潜み、悪を倒すダークヒーローとなった。このエピソードは、アメリカの作家、エドガー・アラン・ポーの哲学的な代表作『大烏(おおがらす)』に類似していることからも分かるように、自己の内面に迫っていくような哲学的テーマを、『バットマン』は初期から予感させていた。
フランク・ミラーなど、複数のアーティストによってシリーズが存続し、進化していくなかで、凶悪犯罪の狂気と戦うバットマンが、じつは狂気を持ったヴィランたちを反射する鏡像的な存在であるということも描かれた。『バットマン:アーカム・アサイラム』では、もはやサイコロジカル・ホラーとして描かれているように、読者をも狂気のなかに引き込んでいくという、コミックの限界を探るように奥深い地点へとフォーカスしていく作品も出てきた。
クリストファー・ノーラン監督の『ダークナイト』(2008年)は、このような深化していくコミックのテーマを引き継ぎ、これに同時多発テロ事件以降のアメリカの状況を重ね合わせるという、重層的構造を作り出した。このような、二面的な矛盾する狂気のテーマについては、本作『ニンジャバットマン』においては、ジョーカーが部分的に体現しているように見えるくらいで、ほぼ霧散してしまっているように感じる。だから本作のバットマンは、そういった意味では迷わないし、本来持っていた先進性を捨て去り、完全に勧善懲悪の古いヒーロー像へ戻ってしまったように思われる。その点において、本作に大きな不満を感じる、バットマンのファンや観客は多いだろう。
だが本作はむしろ、バットマンがスーパーパワーを持っていないヒーローという点に強く着目し、戦国日本という舞台のなかで、資産やテクノロジーによって補強されていた彼のアイデンティティを、一時失墜させるという方向にテーマを見出している。ここでブルース・ウェインが直面するのは、バットマン足らしめていた力を失ってなお、自分はバットマンでいられるのかという悩みである。同様のことが『ダークナイト ライジング』(2012年)でも描かれているように、それはやはりバットマンならではのテーマ性であることは間違いない。