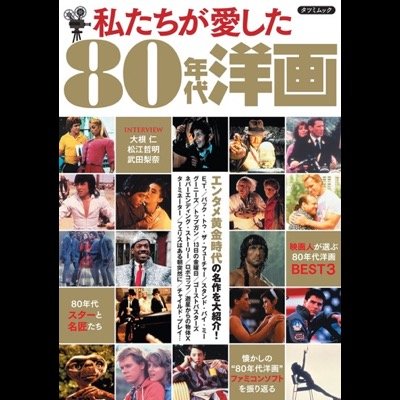シリーズの枠を超えたジャンルそのものに 『13日の金曜日』の“原点”としての存在価値

特集上映「コケティッシュゾーンVol.3」が、シネマート新宿で開催されている。これは、さまざまな事情により長らくスクリーンでかけられなかった作品が、それぞれ2週間限定上映されるという企画。『死霊のはらわた』(1981年)や『ヘアスプレー』(1988年)、『シリアル・ママ』(1994年)など、人気がありながらスパイスの効いたタイトルが上映されている。3月からは、問題作中の問題作『ソドムの市』(1975年)が上映される。
現在上映されているのは、『13日の金曜日』。ホラー映画の有名キャラクター「ジェイソン」を生み出し、多くの続編シリーズが製作された、まさに“原点”といえる第1作だ。ここでは、このタイミングで、本作『13日の金曜日』とはいったい何だったのか、そして、いまこの映画を観ることが何を意味するのかを考えてみたい。
『13日の金曜日』といえば、多くの人が思い浮かべるのが“ジェイソン”だ。ホッケーマスクを被って次々に連続殺人を犯していくキャラクターである。しかし、そのアイコニックな姿を見せるのは3作目からだ。この第1作では、あくまでキャンプ場の湖“クリスタル・レイク”で溺れ死んだ子どもという設定。たしかにここで若者たちが犠牲になっていく殺人事件は発生するものの、その実行犯として登場しているわけではない。
だが、そんな象徴的なキャラクターがほとんど現れずとも、この第1作は若者を中心に大きな支持を得ることとなった。インディーズの低予算作品ながら、すぐさま複数の大手映画会社が配給権をめぐって入札し、広く公開されることで大ヒットを成し遂げた。累計で、製作費55万ドルの100倍以上の売り上げを世界で達成しているのだ。一方で、この映画を嫌った多くの批評家は、観客の評判とは裏腹に酷評をぶつけた。
「批評家は何も分かってないじゃないか!」と、言いたいところだが、本作を鑑賞した観客なら分かるだろう。低予算映画だけあって、劇中の多くの映像はかなりチープであり、これ見よがしの流血や人体破壊表現、取ってつけたような“お色気”シーンなどなど、即物的な展開や演出の数々は、なかなか擁護できるようなものではない。

本作は、「最低映画賞」といわれる「ゴールデンラズベリー賞(ラジー賞)」の第1回の作品賞にもノミネートされている。ラジー賞は後々評価される作品にもケチをつけているため、作品の価値を測る指標としてはかなり弱いというのは前提だが、本作のヒットが“現象”として無視はできないものの、少なくとも一つの作品として高評価するのにハードルが高かった状況を示しているのは間違いない。
本作の“俗悪さ”そのものが、たしかに批判の的になった部分もある。とはいえ、必ずしも残忍な殺人描写が理由で嫌われたというわけではないだろう。それは、同様にエクストリームなホラー作品『悪魔のいけにえ』(1974年)や『ハロウィン』(1978年)の方が高評価を得ている事実が、あくまでクオリティの低さや奥行きのなさにより本作が軽視されていた理由だということを示している。
しかし、この明快さ、即物的な要素の数々があったからこそ、アメリカの若者に大ウケだったのもたしかだった。有名映画評論家のロジャー・エバートが、当時の劇場での様子を語っているが、劇場の観客たちが上映中に、フクロウの鳴き声の真似をしたり、女性の俳優が着替えをするシーンで「胸を出せ!」などと大声を上げたりするなど、当時のアメリカの映画館だとしても、なかなかカオティックな環境だったという。(※)
映像の安っぽさが、有利に転んだ面もある。丁寧にショーアップされた世界ではないからこそ、そこには大資本によって守られていないような、“本物らしいヤバさ”が感じられたのではないか。実際は大手が配給する作品ではあるのだが、文学性や哲学性、芸術性などではなく、単に刺激を求めていた若者たちは、そういった奥行きが希薄だからこそ、“これが俺たちの映画だ”という思いを抱いたのかもしれない。
もともと、ウェス・クレイヴン監督とともに凄惨な描写がさまざまある『鮮血の美学』(1972年)を完成させていたショーン・S・カニンガムは、『ハロウィン』をヒントに、培ってきたエクストリームな表現を、より娯楽的な見世物に変換することを思いついたという。
そこにはすでに、『鮮血の美学』が、じつはスウェーデンの巨匠・イングマール・ベルイマン監督の『処女の泉』(1960年)が下敷きにあるといった、芸術的野心はほぼ含まれてはいない。そうやって生まれた本作は、暴力表現を記号化したお化け屋敷のような様相を呈していたといえるのである。そして、そんな軽薄さこそが、観客が求めていたものだったのだ。