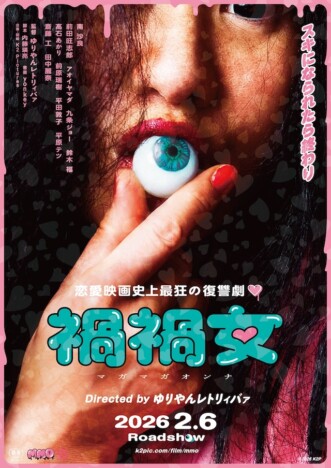荒井晴彦作品は誰かの“逃げ場所”になってくれる 『星と月は天の穴』の滑稽さと愛おしさ

リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう!」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は元『映画芸術』編集部の石井が『星と月は天の穴』をプッシュします。
『星と月は天の穴』

気がつけば12月。2025年もあと12日。映画・ドラマ・アニメと膨大な数の作品に日々接していると、1年の流れがどんどん早くなっている気がする。そんな中で、ふと自分のキャリアの原点を振り返るとき、どうしても切り離せない名前がある。脚本家であり、監督であり、そして私がかつて在籍した雑誌『映画芸術』の編集長でもある、荒井晴彦だ。
今の仕事をする上で「元・『映画芸術』編集部員」という肩書き、つまり「あの荒井晴彦と仕事をしていた」という事実は、一種のお守りのように私を助けてくれた場面が多々ある。「映芸にいたなら」「あの荒井さんに揉まれたのか」。そんな反応に守られ(ときには距離を置かれ)、この業界の末席で呼吸をしてきた。荒井さんが怖くてたまらないときもあったが、愚直なまでに“勉強”をし続ける姿勢や、作品と向き合う姿を間近で見ることができたことが、今の自分を支えてくれているのだとあらためて感じる。
なぜ、荒井晴彦という作家に惹かれ、その“場所”に身を置こうとしたのか。それは映画が私にとって単なる娯楽ではなく、切実な“逃げ場所”であった事実に突き当たる。
いい大学に入り、いい会社に入り、誰かと出会って家族を作って、家を建てて……。“成功”とされるレールから一度外れてしまった自分にとって、「ここで生きるしかない」「ここで生きていい」と思わせてくれたのが、映画であり、荒井晴彦の書く言葉と世界だった。映画とは、キラキラした夢を見せてくれるだけの場所ではない。社会的には“敗者”とされる人間や、誰にも言えないコンプレックスを抱えた人間が、誰に咎められることもなく逃げ込める場所になり得るのだと。
荒井さんの脚本作で描かれていたのは、一貫して「男の弱さと女の強さ」であり、「嫉妬という感情の無様さ」だった。ともすれば汚く醜く、しかし別の角度から見れば極めて人間臭く、潔癖ですらある。そんな“性”のリアルを、荒井作品は肯定も否定もせず、ただそこに在るものとして映し出していた。あの頃の私にとって、荒井さんの映画は、社会の“正しさ”から逃げ込み、自分の弱さを肯定できる唯一の聖域だったのだ。

荒井さんの監督第5作目となる『星と月は天の穴』もまた、そんな自分の弱さに寄り添ってくれる一作だった。近年、荒井さんの監督作が続いているのも、コンプライアンスや道徳的正しさが優先されがちな現代において、かつて私のような人間を救ってくれた「個人のための映画」、あるいは「逃げ場所としての映画」が失われつつあることへの、荒井さんなりの抵抗であり、“映画”を残そうとする執念のように思えてならない。
本作の原作は、吉行淳之介が1966年に発表した同名小説。当時18歳だった荒井青年は、この小説を読み、主人公の男の心情に強烈なシンパシーを抱いたという。「18歳だった。彼女もいないし、女の子の手を握ったのは高校の文化祭のオクラホマミキサーの時だけだった」と荒井さん自身が語るように、彼もまた、女性という存在を前に立ちすくむ一人の青年だった。それから半世紀以上の時を経て、長年の念願だったこの企画を実現させた。

物語の舞台は、学生運動の熱気が残る1969年。主人公の矢添克二(綾野剛)は、妻に逃げられて10年が経つ40代の小説家。彼は離婚の傷を引きずりながら、馴染みの娼婦・千枝子(田中麗奈)と体を重ねることで心の穴を埋めようとしている。しかし、彼が恋愛に踏み込めない本当の理由は、誰にも言えない身体的なコンプレックスにある。そんな矢添の前に現れるのが、20歳以上も年下の大学生・紀子(咲耶)だ。無邪気に、しかし残酷なほど大胆に距離を詰めてくる彼女に、矢添は戸惑い、恐れ、そして惹かれていく。