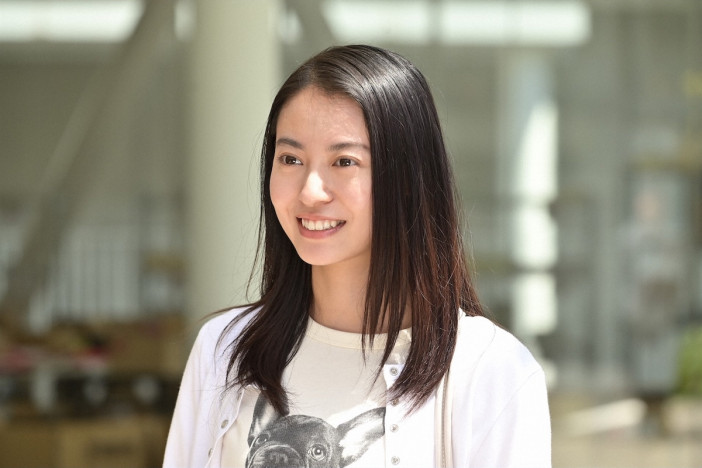『PLASTIC』宮崎大祐監督の特別さは“偶然性”にあり? 小川あん×藤江琢磨インタビュー

俊英・宮崎大祐監督の新作『PLASTIC』が公開された。幻のアーティスト“エクスネ・ケディ”の1974年LIVE音源アルバム『StrollingPlanet‘74』をモチーフにした青春映画である本作は、70年代に世界を席巻する音楽を発信するも、瞬く間に解散してしまった幻のアーティスト“エクスネ”の大ファンである2人の主人公・イブキとジュンが、2018年に名古屋で出会い、恋に落ちた瞬間から、4年後に東京で行われるエクスネ・ケディ再結成ライブ当日に至るまでを音楽とともに描かれていく。
イブキとジュンを演じるのは、小川あんと藤江琢磨。小川は以前から宮崎大祐という映画作家の存在を気にかけていたが、出会いとしては、友人の柳英里紗に『VIDEOPHOBIA』の上映に誘われ、上映後の打ち上げで宮崎監督と少し話す機会があったのだという。
宮崎大祐は、レオス・カラックス監督の東京ロケの短編『メルド』(2008年)に美術アシスタントとして参加後、黒沢清監督『トウキョウソナタ』(2008年)などで助監督を務め、『夜が終わる場所』(2012年)で監督デビュー。『大和(カリフォルニア)』(2018年)、『TOURISM』(2019年)、『VIDEOPHOBIA』(2020年)と発表し、国内外で注目される存在である。
「『VIDEOPHOBIA』で精神がぐらつくようなダークな映像空間を構築した宮崎さんに出演依頼をいただいた時に『青春映画?』と驚いたんです。でもその中に独特の駆け抜けるようなリズム感と、後半はわざとバランスを崩したような仕掛けがほどこされていて、宮崎さん節を感じながら脚本を読みました」(小川あん)

「僕の場合は最初にSNSでご連絡をいただいて、別の映画で声だけの出演で参加したあと、なぜか道でばったり会うことが重なって。ある日、宮崎さんのインスタライブを聴いていたらやっぱり、“道で偶然会うことが重要なきっかけになる”とおっしゃっていました。宮崎作品じたいにも偶然が溢れているので、偶然性がお好きなのでしょうね。だから動きから始めたり、撮りたい画が先行したりするのではないでしょうか。そこで起きることに耳を澄ませるというか。偶然性の余白が広く取られています」(藤江琢磨)
「宮崎さんは登場人物の直接的な内面の描写にあまり興味がないんじゃないかな。宮崎さん固有のイメージとセンス、音や表情といったディテール、さらにそれを超えてくる偶発的な何かを、たぶん好んで撮ろうとしているんだと感じました」(小川あん)
宮崎大祐の映画の多くは、登場人物が音楽との関わりを切り結ぶ。『PLASTIC』では、エクスネ・ケディがリリースしたとされる1974年のライブ音源アルバム『Strolling Planet ‘74』の魅力に取り憑かれた高校生のイブキ(小川あん)とジュン(藤江琢磨)の二人が、エクスネ・ケディへの傾倒によって結びつき、恋に落ちる。しかしこの映画では、二人の関係性は断絶の不安とともに寄る辺なく漂流する。対照的に、二人の心の芯には音楽の魔力が貫通し、消滅することがない。
「エクスネ・ケディは幻のバンドなので私たちも見たことがないし、情報も少ないという中で、実在を信じて追いかけ続けている男女の物語です。逆にそうだからこそ、おたがいに想像力を共有しながら強く惹かれ合う。実際に目にした以上のもの、未知なるものに出会う。たとえば宇宙人に会った人どうしが話すより、宇宙人をどうしても見たいと渇望する者どうしの関係性の方がもっと情熱的に繋がるのではないでしょうか」(小川あん)
「登場人物が音楽を聴くシーンはとても重要だったので、シーンを演じる前にエクスネ・ケディをめちゃくちゃ聴き込んでから本番に臨みましたね」(藤江琢磨)

藤江琢磨が演じるジュンはエクスネ・ケディに触発されてバンド活動を始める。転校した高校の部室で2回、バイト先の店で1回、ジュンはおもむろにギター演奏を披露し、すばらしいノイズを響かせる。しかしジュンは口でこそ「バンド、バンド」とさかんに言うわりには、1回たりとも仲間どうしで音楽の快楽を共有することがなく、「お前とはもうやらないよ」とバンド仲間から突きつけられるシーンさえも存在しないのである。
エクスネ・ケディへの傾倒がジュンとイブキを結びつけたのだとしても、ジュンは音楽との関わりによってむしろ孤立を深めていくように見える。自分がいま出そうとするこの一音一音が誰にも届かないのではないかという不安、しかし数万年後には宇宙のどこかで誰かに感知されるかもしれないという空想――この精神性はやはり孤立とともにあるのではないか。

「ひとつひとつのシーンはまだ客観的に見えてはいませんが、いま尋ねて下さった問いは腑に落ちます。その孤立性は完成した映画になって初めて見えてくるものですね。演じている時はバンド活動をがんばっている青年だと思って演じてきたし、停滞しがちな音楽活動の中でなんとか返り咲きたい一心でもがいている役なわけです。でもいま、ジュンの青春をいろいろと振り返ってみると、ある悲しみのようなものが込み上げてきました」(藤江琢磨)