ヴィム・ヴェンダースは「遅れてきたヌーヴェルヴァーグ」? 宇野維正×森直人が語り合う

アメリカン・ニューシネマとの接続

森:ちなみに僕、それぞれの作品の日本公開のタイミングを、ちょっと調べてきたんですけど、『まわり道』と『さすらい』は、ほぼリアルタイムで日本公開されていて、『パリ、テキサス』も日本公開されている。で、1988年の4月に『ベルリン・天使の詩』が日本公開されて、これが結果的に30週間のロングランを記録して。それを受けて、その年の11月に『都会のアリス』が上映されるんですけど、これが実は日本初公開だったんですよね。
宇野:あ、そうだったっけ? 当時普通にリバイバルだと思って観た記憶が。1974年の作品だよね。
森:そう。で、1989年の6月に『東京画』(1985年)が公開、10月に『まわり道』のリバイバル、11月に『さすらい』のリバイバルがあって……これが全部、フランス映画社のBOWシリーズで公開されたという。
ーーなるほど。そこで過去作が出そろうというか、ひと通り日本で観られるようになったと。
森:もちろん、我々世代よりも年長のハードなシネフィルの方々は、それ以前から何らかの方法で観ていたと思うんですけど、日本の劇場公開という意味では、この順番になるみたいです。
宇野:まあ、いかに『ベルリン・天使の詩』のヒットが大きかったかってことだよね。で、前にも言ったけど、そのヒットの大きな理由は、ピーター・フォークにあったという(笑)。

ーー当時の日本では、『刑事コロンボ』の人として、一般的にも有名だった(笑)。
宇野:そうそう。あの掴みはすごかったんだよ。「あ、知ってる人が出てきた」っていう(笑)。あの映画の中でさ、ドイツの子どもたちが、ピーター・フォークに向かって「コロンボ、コロンボ」って言うじゃない? それを見て安心したというか、当時の日本人はみんなテレビでコロンボを観ていたけど、コロンボの国際的な評価とかは全然知らなかったわけですよ。けど、あれを見て、「あ、ドイツでもコロンボって人気あるんだ」って知ったという(笑)。
ーー(笑)。
宇野:それってさ、まさにアメリカとの距離感の話であって。アメリカにあこがれる外国ならではの距離感というか、日本もちょっとそういうところがあるじゃない? だから、あれを見た日本人が、「あ、ドイツも一緒なんだ」って感じになるというか、そういう感覚がちょっとあったんだと思う。
森:なるほどなあ。確かに、対アメリカ的な意味で、日本とドイツの位相が同じっていうのは納得できます。特にヴェンダースのアメリカ映画や文化、ロックンロールへの憧れや距離感って、日本のアメリカ好きにめっちゃ近いですよね。
宇野:で、なおかつ、ヴェンダース自身がすごく親日家で、小津安二郎と山本耀司のドキュメンタリー(『東京画』と『都市とモードのビデオノート』(1989年))を続けて撮ったりして……それは、愛されるよね(笑)。

森:相性ばっちりですね。ヴェンダース自身も実際に来日したりして、「あ、日本の人たちとすごく気が合う」みたいな感じだったんじゃないかな。居心地がいいと言うか。「俺、日本人なのかな?」みたいな(笑)。
宇野:だからこそ、90年代にその反動がきちゃったというか、消費され尽くしちゃったようなところがあったのかもしれない。
ーーなるほど。で、少し話を戻すと……『ベルリン・天使の詩』以前のヴェンダース作品って、アメリカン・ニューシネマと接続するところがちょっとありましたよね?
森:確かに。アメリカン・ニューシネマの後期と、バトンリレーするような雰囲気はありましたよね。
宇野:まあ、『アメリカの友人』(1977年)とか『パリ、テキサス』は、まさにそれがテーマというか、それもやっぱり「アメリカに対する距離感」なんだよね。
森:そうですね。フランシス・フォード・コッポラに招かれてアメリカで撮った『ハメット』(1982年)の苦い経験をもとに『ことの次第』(1982年)を撮ったり……そう考えると、『アメリカの友人』っていうタイトルは、ホント象徴的で、ヴェンダース自身が「アメリカの友人」だっていう自己言及宣言ですよ(笑)。で、その映画に、デニス・ホッパーやニコラス・レイ、サミュエル・フラーといった、ヴェンダースのアメリカの友人たちが大勢出演しているという。しかも主演のデニス・ホッパーが、映画の中でロジャー・マッギン(ザ・バーズ)の「イージー・ライダーのバラード」(ホッパーが1969年に監督・出演したニューシネマの名作『イージー・ライダー』(1969年)に使用された楽曲)を口ずさんだりしますからね!
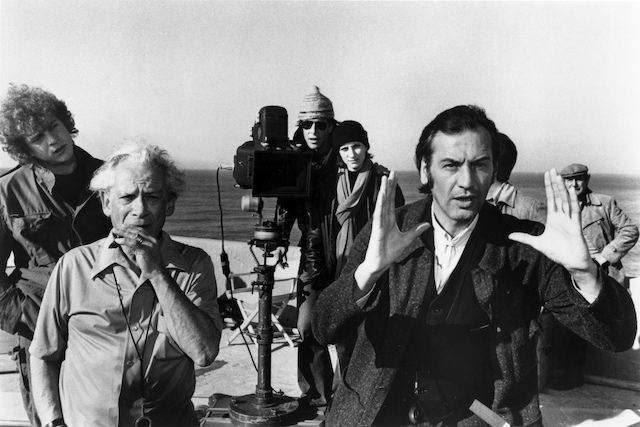
ーーその繋がりというか、ヴェンダースならではの国際的な交友関係って、何なんでしょうね。ドキュメンタリーも含めて、ヴェンダースの映画には本当に驚くほど多くの有名人たちが出演していて……。
宇野:それはやっぱり、「外国人だから」っていうのもあるんじゃない? だからこそ、アメリカの映画人はもちろん、小津の関係者や山本耀司にもアプローチできたという。
森:旅というモチーフとも繋がるんですけど、ある種、常に「外部」にいて、そこから各所へのアクセスを続けるのがヴェンダースってことですかね。それはドイツっていう地理性も大きいのかも。誤解を招く言い方かもしれないけど、ドイツって、映画的に言ったら、ちょっと「辺境」だっていう見方は可能だと思うんですよ。ハリウッド帝国を有するアメリカでもなければ、リュミエール兄弟がいたフランスでもない。日本ですら黒澤明や小津安二郎みたいな、世界的な影響力を持つシネアストたちが早い時期にいましたからね。戦前のドイツ表現主義というのは、前衛芸術全般の運動ですし、フリッツ・ラングや、あるいはエルンスト・ルビッチ、マックス・オフュルス、ダグラス・サークらもハリウッドに渡ったわけですからね。ドイツにおいて映画作家たちが大きく注目されたのは、やはりヴェンダースを含めた1970年代の「ニュージャーマンシネマ」……ヘルツォークやファスビンダーからだと思うんですよ。だから映画的にはちょっと後進の場所にいるっていう思いが、多分ヴェンダースの中には結構強い気がするんですよね。だからこそ、自分の映画の中で、やたら先行の映画や映画史に対するメタレベル的な言及が多くなる。『都会のアリス』でも、撮影中の期間にジョン・フォード監督が亡くなっちゃって(1973年8月31日)、映像の中で訃報が示されますから。
宇野:というか、「遅れてきた」って感じなんだろうね。それこそ、ヌーヴェルヴァーグに対して言うんだったら。
森:ズバリ、そうですね。ヴェンダースって1945年生まれでしょ? だから、フランスのヌーヴェルヴァーグの人たちより、ちょうどひと回り年少だし……世代的にも場所的にも「遅れてきたヌーヴェルヴァーグ」っていう意識が、ヴェンダースには実際強かったんじゃないかなと思います。

宇野:で、それがやっぱり、同じくフランスとは時間差のある日本で熱狂的に支持されたっていうのは、すごくよくわかる話じゃない?
森:日本も「アメリカの友人」ですもんね、言わば。
ーーそういう日本との「親和性」みたいなものがあったと。
森:それはホントそう思う。だからアメリカ映画やロックンロールを参照しても、フランスほど尖った斜め目線の批評性が働くことはなく(笑)、比較的素直じゃないですか。平たく言うと、「できればアメリカ人に生まれたかった」という心性ですよね。めっちゃ日本っぽい(笑)。それが、映画史に対する嫌味のないオマージュとかリスペクトという形で、自身の作品にもピュアに出ている。


















