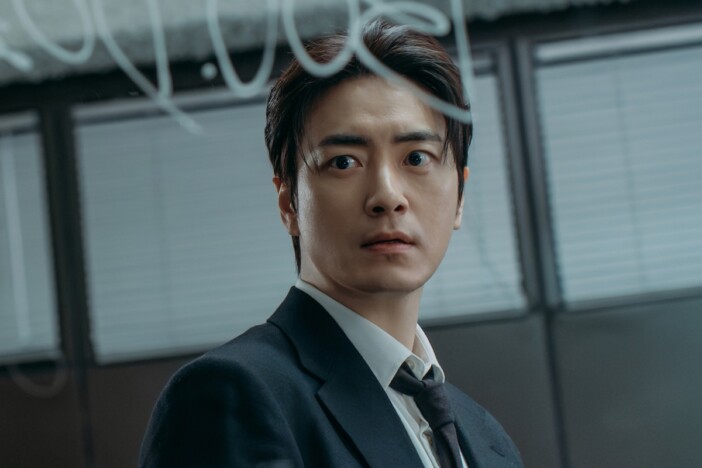『THE LAST OF US』後半の“冬編”へ 強調される西部劇の側面

ジョエル(ペドロ・パスカル)とエリー(ベラ・ラムジー)がカンザスシティを後にして3カ月。季節は移ろい、第6話で物語は後半の“冬編”へと突入する。原作ゲームで2人がワイオミングに到着したのは秋のこと。だがロケーションが映えるのは断然、冬景色の方だ。雪を頂いた山々と馬が織り成すランドスケープに、『THE LAST OF US』の西部劇としての側面が強調される。冒頭、2人が道を尋ねる先住民族の老夫婦は都市からも居留区からも締め出されたが、感染者の影もないこの地域の生活は素朴で、彼らにはどこかユーモラスな雰囲気すら漂う。今回、アクションゲームからアクションをオミットしたクレイグ・メイジンは、大部分にドラマオリジナルの脚色を施しながら、それでいて(やや駆け足な部分も含め)原作の語りのリズムからは少しも外れておらず、アメリカの辺境にいまを生きる人の在り方を描いている。
原作ではジョエルが弟トミー(ガブリエル・ルナ)の暮らすジャクソンに立ち寄ることはなく、町の実態が描かれたのは続編『PART II』の冒頭部だった。近隣のダムから電力を得てインフラを整備し、砦のような高い壁で周囲を覆ったこの集落で人々はパンデミック以前の平穏な生活を送っている。自給自足、資源は全て共有財産。おそらく互いの技能を提供しあう相互扶助社会が成立している(夜には映画上映会という文化的な営みも催されている)。ジョエルは思わず「共産主義か?」と口をつくが、後にエリーとこんなやり取りをしている。
「昔はみんなあの町みたいな暮らしを?」
「いや、そうするには国が大きすぎた。当時は2種類の人がいた。全てを所有したい人と、誰にも所有させたくない人だ」
2000年代以後、都市と地方という分断が深刻化していった今、人里離れた辺境にこそ平和と共存があるとするアイロニーはエピソード終盤、ジョエルとエリーがコロラド大学に到着するとさらに際立つ。ファイアフライの拠点があるとされたキャンパスには人間どころか感染者の姿もなく、逃げ出した実験用の猿が走り回るだけだ。本エピソードの監督はヤスミラ・ジュバニッチ。ベルリン映画祭で金熊賞を受賞した『サラエボの花』や、アカデミー国際長編映画賞にノミネートされた『アイダよ、何処へ?』など、祖国ボスニア・ヘルツェゴヴィナで90年代初頭に起こった内戦を描き続けてきた作家である。巨大な廃墟には戦争という人類文明の崩壊を目の当たりにしてきた彼女ならではの真に迫った怖さがある。