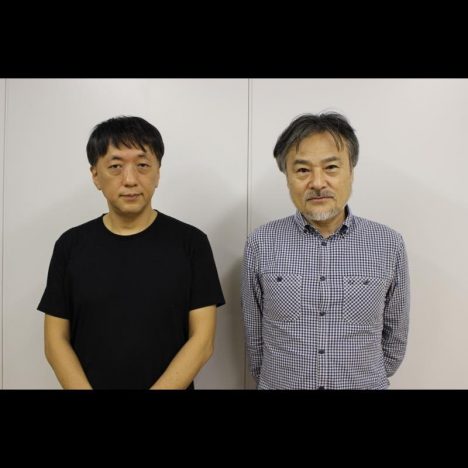宮台真司の月刊映画時評 特別編
宮台真司×黒沢清監督『スパイの妻』対談:<閉ざされ>から<開かれ>へと向かう“黒沢流”の反復

「記憶」から「記録」へ ー「フィルムというモノ」へのフェティシズムー

宮台:もう一つお伺いしたいことがあります。本作では、神戸の上流階級の人物が主人公です。だから、何1つ不自由のない、お手伝いのいるお屋敷での生活が描かれます。頓馬な人たちがーーまぁウヨ豚(ネトウヨ)のことですがーー「なんでこんな余裕のある上流の人間を描くんだ」と反発するでしょう。実際アメリカでも、リベラルは「俺には余裕がある」という自己提示に過ぎないんだという議論が、ここ30年ぐらい続いています。リベラルの裕福さ、あるいは裕福なリベラルを描くことに、危惧はありませんでしたか?
黒沢:ありました。極度に貧しいという人はこれまで登場させたことがありますが、いわゆる“お金持ち”を出したのは初めてでした。ただよく考えてみると、それは何に対しての危惧なんだろうと。これはフィクションですし、階級差がテーマの作品でもない。題材にした人たちが、たまたま上流階級だったというぐらいで、あまりそれ以上考えることはしませんでした。僕があまりネット上の言説を把握していないというのもありますが……。

宮台:大半はゴミの垂れ流しなので見ない方がいいです。僕は、先ほど述べたような言いがかりがもし生じるようなら、それを全面的に粉砕するために、完全にArmed(武装された状態)です(笑)。少し開陳すると、戦間期研究や戦時期研究では「陸軍的なもの」と「海軍的なもの」というコードが用いられてきました。カオスを愛でる戦間期前期は「海軍的なもの=都市的なもの」で、統合を愛でる戦間期後期は「陸軍的なもの=農村的な劣等感」。僕の母方曾祖父は戦間期の浅草六区に芝居小屋と映画館を5つ所有するカブキ者だったので、上海租界地で生まれ育った母を通じてこのコードに馴染んできました。
御存知のように、陸軍エリートには貧しい階級の出身者が多く、海軍エリートはその逆で上流階級の出身者が多い。出身階級とリベラルの度合いに相関があることは昔から知られています。実際、大内兵衛や大内力といった初期マルクス主義者は豪農出身です。これは「見たくない事実」でしょうが「見なければならない事実」です。それを前提に本作を観ると、人々は余裕がなくて不安だから「まとも」という名の狂気に駆られていくのだ、という当たり前の現実が描かれています。陸軍的/海軍的は、語弊が生じることを恐れるポリコレ的な流れゆえに積極的に語られなくなりましたが、重要なポイントです。

川端康成と江戸川乱歩の認識では、戦間期前期の光と闇の織り成す綾に満ちた浅草の「大正ロマン」を楽しめるのは、明智小五郎のような探偵=都会人であって、そうした渾沌の享楽から見放された地方出身者のあからさまな劣等感が、闇を消去した銀座の「昭和モダン」を駆動し、それがやがて全体主義につながっていくのだということになります。母や祖母からの宣べ伝えの「生々しさ」もあって、ほほ正しいだろうと確信しています。
だからこそ、泰治の存在が気になるのです。彼の出身階級は物語としては描かれてはいませんが、映像が直接に語っています。泰治にとっては、優作と聡子という夫婦の生活が本当に「輝く光」です。泰治が聡子に惚れていることを示唆するモチーフがありますが、そこにあるのも、ある種の階級的なハレーションです。劣等感による階級的な憧れが、自分の劣等感を「見たくない」ので、恋愛感情として粉飾決算されるのです。泰治の存在の御蔭で、豊かさが描かれることの意味が明らかになっていると感じます。

他方、言葉による粉飾決算に関連した話ですが、この10年の映画の国際的流れには、モノとしての「記録」に語らせるモチーフが頻出します。「記録」には、化石のように人が介在しない表象と、日記やメモみたいに人が介在する表象があります。いま話題のクリストファー・ノーラン監督『TENET テネット』も、「記憶」を消去された存在が、時間の逆行を通じて「記録」に戻る運動を示します。商業映画デビュー作『メメント』も同じ運動が全体を覆い尽くし、人が介在する「記録」への全面的疑いに帰着して行くのでした。
本作にも、近年一流の映画監督の方々が描いてきたモチーフと全く同じものがあります。最近はデジタルが主流だから、若干の語弊があるのを承知で申しますが、映画はフィルムというモノがベースです。ドキュメンタリーならぬフィクションであれ、撮影した現場の「記録」そのものです。文書も「記録」ですが、モノが幾重にも介在するフィルムのほうが、嘘をつくのが下手クソです。別の言い方をすれば、フォレンジック(鑑識)に弱い。
黒沢:その通りです。
宮台:僕は、ノーラン作品とも共通する「フィルムというモノ」に対するフェティシズムをーーゆえに映写という「フィルムのハンドリング」へのフェティシズムをーー、黒沢作品に感じてきました。そこには、モノとしての「記録」こそが、御都合主義的な「記憶」へと<閉ざされた>者たちにとっての、<開かれ>の契機になるんじゃないかと、という楽天的感覚ーー川端康成のフィルム体験的な視座を支える感覚ーーがあります。
黒沢監督の作品は、冒頭に申し上げた「壁・窓・扉を背景に、前景に人が集まる画面」が典型ですが、脆弱な記憶をベースにショボイ営みに淫する人間たちを、観客のフィルム体験を通じて相対化させます。そこで僕らは、人によって語られているのか、壁や窓によって語られているのか、よく分からなくなるような「未規定な感覚」を抱くのですね。それはちょっとした眩暈(めまい)です。
30分のインタビューで、実に残念ながら最後の質問になってしまうのですが(笑)、『ダゲレオタイプの女』でも現れた、フィルムというモノへのフェティッシュな感覚は、本作においてどのような機能を果たしていると思われますか?
黒沢:物語では、主人公・聡子がフィルムに映写されたものを観ることによって、またはフィルムで撮影した映画に出演することによって、どんどん違う人間に変わっていく契機として使われています。
宮台:これまでも使われてきました。『LOFT ロフト』や『CURE』もまさにそうです。本当に一貫しています。それは、黒沢作品を体験することで、観客が違う人間に変わるかもしれないという事実の、隠喩的な反復です。この自己言及が黒沢作品の真骨頂です。
黒沢:単純になにかを映写するという行為が好きなんです(笑)。
宮台:映写する営みが始まった瞬間に何かワクワクさせられてしまうという事実ですね。
黒沢:そうなんです。当たり前ですが、映写したら、そこになにかが映し出されるわけです。それまで1つの閉ざされた部屋だと思っていたものが、突如スクリーンという<向こう側>が出現することで、<こちら側>と<向こう側>の2つに割れる。映画のあの驚くべき特性には、何度向き合っても舌を巻きます。映画ほど露骨かつ作為的にもう1つの世界を開示させる、鮮やかな手はないと思うんです。今回はとりわけそれが何度かいろんな手段で、物語の契機となるシーンで出てきて、最後には劇変のきっかけにまでなるわけです。もちろんそれらは脚本に書かれていたことですが、いつも以上に、映写したものを観るという行為で、どれだけドラマや人が変化するか、挑戦したように感じます。
宮台:本当にそう思います。暗闇でフィルムが映写され、日常に異次元が闖入することで、あっさりと微睡から覚醒してしまう、という黒沢監督の楽天的なモチーフが、みごとに結晶化しています。歌舞伎で言えば「成田屋!」と声をかけたくなるような(笑)。本日はありがとうございました。僕もその楽天性につらなっていきたいです。
黒沢:こちらこそありがとうございました。ここまで詳細に観ていただいて、嬉しいです。
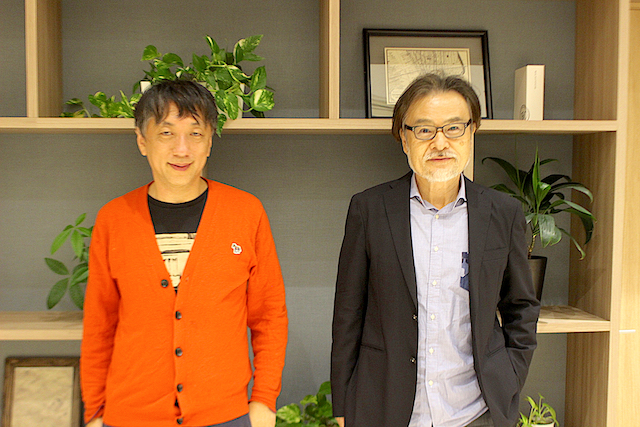
■公開情報
『スパイの妻』
新宿ピカデリーほかにて公開中
出演:蒼井優、高橋一生、坂東龍汰、恒松祐里、みのすけ、玄理、東出昌大、笹野高史ほか
監督:黒沢清
脚本:濱口竜介、野原位、黒沢清
音楽:長岡亮介
制作著作:NHK、NHK エンタープライズ、Incline,、C&I エンタテインメント
制作プロダクション:C&I エンタテインメント
配給:ビターズ・エンド
配給協力:『スパイの妻』プロモーションパートナーズ
2020/日本/115分/1:1.85
公式サイト:wos.bitters.co.jp