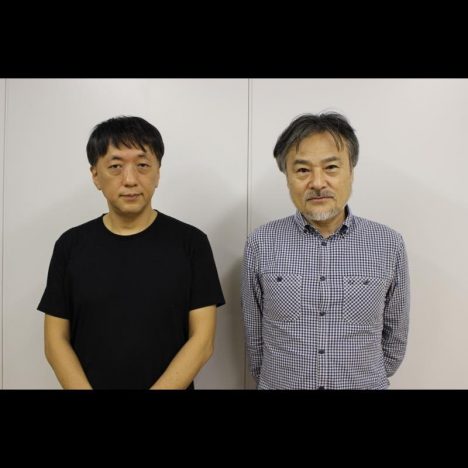宮台真司の月刊映画時評 特別編
宮台真司×黒沢清監督『スパイの妻』対談:<閉ざされ>から<開かれ>へと向かう“黒沢流”の反復

『スパイの妻』にある、「覚醒の連鎖」
宮台:なるほど。僕が「アニメが抱える過剰コントロール問題」と呼ぶものです。実写と違い、アニメでは、敢えて意識しない限り、統制不可能なノイズが映り込みません。実写とアニメの違いは、ロケとセットの違いに平行移動できます。「コレ、なんかいいぞ」と現場で覚醒して取り込めるものを、セル画やCGやセットで「ゼロから構成」するのはとても難しい。だから、黒沢監督のおっしゃることは、とてもよく理解できます。
話を戻すと、今回は「微睡からの覚醒」という契機が連鎖しています。覚醒者が次なる覚醒者を生み出す、という、これまた黒沢流モチーフです。まず、大陸に渡った夫・優作が満州で何かを目撃する。目撃によって覚醒した夫は、妻・聡子から見ると最初は異形の存在だったのが、やがて妻も夫に感染したかのようにして覚醒する。この「覚醒の連鎖」があまりにも感動的なのです。

というのも、本作が、巷では「愛の映画」ーー「愛ゆえに覚醒した女の物語」ーーなどと言われながら、そうした御都合主義的な妄想の一切を、映像においても物語においても否定するものになっているからです。聡子が「アメリカへ渡りましょう」と優作に呼びかけるときに目がキラキラと輝く、ある種「異様なシーン」ーー僕には彼女が妖怪のように見えました(笑)ーーが典型です。ここにあるのは、「愛ゆえに」ではなく、「<世界>(あらゆる全体)との関わり方ゆえに」です。
当たり前ですが、聡子が「愛ゆえに」優作の世界観に連なる、などという絵空事は、単なる中二病の夢であって、現実には神経症の症状としてしかあり得ません。実際には「フィルムという記録を通じて」、聡子が優作の世界観に連なることで初めて、今までになかった新しい愛の地平に到るのですね。そして、聡子が優作の世界観に連なれたことで初めて、どんなに遠くにいてもーーラストシーンに関わるモチーフですがーーつながっている感覚を抱けるようになるのです。間違いなく、これだけが現実にあり得ることです。

ただし、僕が性愛のフィールドワークやワークショップを1980年代半ばからしてきて思うことは、今やそのような関係ーー世界観に連なることで新しい地平に到れるような愛ーーはどこにもなくなったということです。だから「愛ゆえに覚醒した女の物語」などという極端な妄言がまかり通ります。妄言を口にする昨今の男女たちは、等身大へと閉ざされていて、マッチングアプリで表示しあう「身過ぎ世過ぎの損得勘定」や、喋り方や食べ方を含めた「ショボイ性癖」の中でしか対面できず、出会えず、セックスもできません。
その意味で、本作は現代において稀有になった関係を描きます。「覚醒の連鎖」と言いましたが、「聡子の覚醒」は「世界観への覚醒であるがゆえに、新しい愛への覚醒でもある」というものです。そうした関係は、今や現実の社会から蒸発しています。それはなぜか。人の存在形式が間違っているからです……という具合に、この映画は今の現実に対する批評を構成しています。最終的に「人の存在形式の決定的な誤り」に到るのは黒沢流ですが、従来の作品より一段迂回して「恋愛を描く」ので勘違いが生じやすいのでしょう。
黒沢:鋭いご指摘ですね。しかしまずお断りしておくと、この脚本の元々は僕が書いたものではなくて、濱口竜介と野原位という、僕の元・教え子によるものです。僕はこれまで、男女関係を彼らが書いてきたようには深く追求してきませんでした。ただ、これは映画ができた後に濱口たちと話して分かってきたことなんですが、彼らが当初書いた脚本では、聡子を突き動かしている動機は「夫に女がいる」というただの嫉妬心を発端としている。それはある意味、増村保造的作風とも言えます。確かに濱口は、聡子が単なる嫉妬を発端として、どんどん自分自身が変化する過程を見事に書いていました。しかし、僕は脚本を読んだとき、増村的にしたいとは思わなかった。というか、僕には増村的に映画を作れないと思ったんです。

実際に完成した本作も、「夫に女がいる」という嫉妬心がきっかけの一つにはなっていますが、僕はもう少し軽やかに、ある種の運動ーー映写機を回すとか、倉庫に忍び込むとか、自ら市電に乗って憲兵の幼なじみに会いに行くとかーーそういった彼女なりの動き、彼女の自発的な行動によって、どんどん変容させていきたかった。そして宮台さんがおっしゃる通り、「アメリカへ渡りましょう、私たち2人で」という、気が狂ったかとすら思うようなセリフをあの場面で言う。あれは賭けだったんですよ。この場面で、彼女はこんなにうれしそうに目を輝かせて大丈夫なのかという不安もあった。でも、彼女があのような結果に至るように運動させることで、帰着させました。濱口たちが書いたものを、僕が無理矢理運動させたことでできたキャラクターが聡子なのかなと振り返ってみて思います。

宮台:それがまさに、<閉ざされ>から<開かれ>へと向かう運動の玉突きです。その運動の過程で、自分は夫を見くびっていたという風に、夫の存在形式にーー世界観にーー覚醒するところが、感動的かつ批評的なのですね。作中では、ストア派の時代以降2300年間も繰り返されてきた「ナショナリストvsコスモポリタン」という図式が出てきます。夫の存在形式に感染した妻は、ナショナリストからコスモポリタンへと<開かれ>ます。
「精神の平穏」を目標とするストア派の命題を今日的にパラフレーズすると、ナショナリストとは、「日本すげえ」「中国こそが敵」とほざきつつも、その実態は、中国人どころか日本人の友達さえほとんどいない「不安にさいなまれた輩」が、言葉にへばりついて不安を埋め合わせるだけの神経症(笑)。同じ神経症の症状が性愛に現れます。それが、黒沢監督が<開かれ>への運動の出発点だったに過ぎないとされた妻・聡子の嫉妬です。
ぶっちゃけ、日本スゲエ系の妄想的ナショナリストは例外なく粘着系ソクバッキーです(笑)。例えば、日本スゲエの始まりは1997年の「新しい歴史教科書をつくる会」でしたが、数多の本で書いたように、性的退却の始まりは1996年の秋からです。ストーカーやセクハラという日本語の元年も1996年です。繰り返すと、妻・聡子は、日本スゲエ系のショボイ妄想的ナショナリズムの外へと<開かれる>ことで、夫をショボイ存在だと見くびっているがゆえの嫉妬から外へと<開かれた>わけです。そこも辛辣で批評的です。

今まで何度かある黒沢監督との対談で申し上げてきたように、たとえ黒沢監督が自覚しておられなくても、ある運動の形式が「フィルムを見ている我々の体験」として反復されるとき、運動の形式を制御しているコードーー命令文ーーに、黒沢的無意識が表れるのだと思っています。今回もそのコードは、言葉によって粉飾された関係の中に<閉ざされた>状態から、粉飾決算の外へと<開かれ>よ、という形式です。今回は、観客の脳が今日的文脈を参照せざるを得ないので、その運動形式が自動的に類い稀れな批評性を帯びます。
単に「コスモポリタンであることが倫理的だ」という主張なら、ゴダールが言う意味で「映画の政治性に鈍感な、単なる政治映画」です。今回の作品は、<閉ざされ>によるみすぼらしさから、<開かれ>による力の充溢へ、という存在形式の運動を反復的に示します。逆説的ですが、存在形式の運動を示す映像のほうが、コスモポリタニズムや普遍主義の正しさを唱う政治映画よりも、辛辣です。パラフレーズすれば、存在形式の運動が変われば、イデオロギーの変化は後からついてきます。ゴダール的なるものの真髄ですね。

黒沢:最初の脚本を読んだとき、聡子の「それでは売国奴ではないですか」というセリフに「僕はコスモポリタンだ」と優作が答える場面があって、「主人公にこれを言わせるのか」という逡巡がありました。濱口たちにも何度か確認しました。そのようなセリフを言うことによって、登場人物が、我々の想像以上に、政治的イデオロギーに囚われてしまうのではないかと思ったんです。「それでも言わせたい」という濱口たちからの要望もあり、結果的に俳優たちの演技に任せようということになりましたが。さらっとしたトーンで言ってしまえば、気にはならないだろうと信じた結果です。宮台さんがおっしゃるように、主人公たちが政治的な枠から抜け出せていると見えたのなら、よかったです。
宮台:実際、とてもうまくいっていました。黒沢監督がおっしゃった聡子のシーンも、家の壁を背景にして、引きの画面でしゃべっているので、ちょっとコメディを観るような軽やかさを感じられます。映像の解釈をコントロールしてしまう間違った呪文というよりも、映像的な運動の分泌物に過ぎないという感じでしょうか。
黒沢:ほっとしています。心配していたんですよ。