少女の通過儀礼から無我の境地までも描く 『若おかみは小学生!』がもたらす極上の映画体験
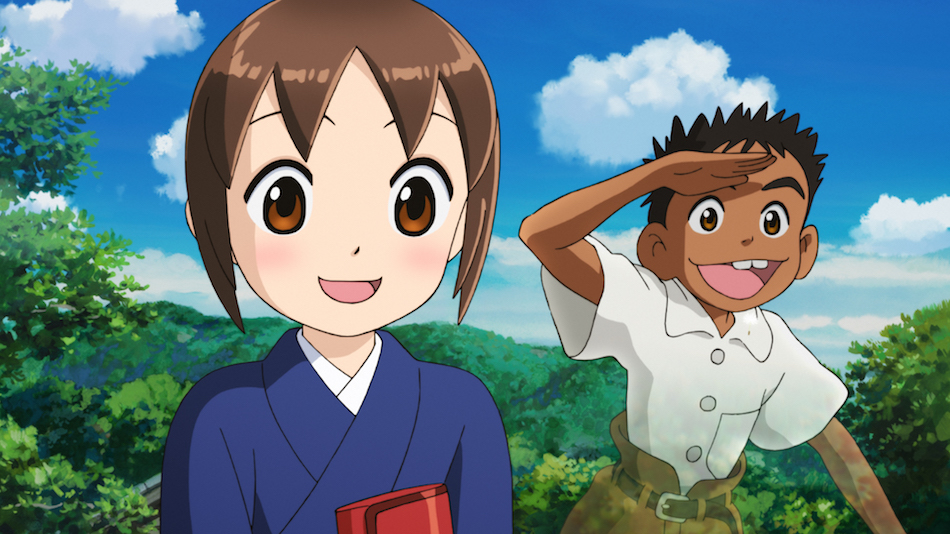
万物に生命があり死は偏在している
本作は死が身近な物語だ。主人公おっこの両親が事故で亡くなるシーンから始まり、おっこは幽霊とコミュニケーションが取れる。近しい者の死は誰にとっても大きな喪失だが、おっこはそれを喪失だと受け止めきれていない。なまじ幽霊とも生きているように会話できるせいもあってか、両親もまだ生きているのではという錯覚を持っている。
おっこの周囲も、おっこの心の内側も、生と死の境が曖昧になっているのは本作の特異な点だ。そして死の匂いが色濃い作品にもかかわらず、重たさを感じさせない。

どうしてこんな描写が可能なのかといろいろ考えてみたのだが、二度目の鑑賞で本作にまつわる死の存在は、おっこの両親や幽霊たちだけではないことに気づいた。おっこが温泉で死んでいる蛾をすくい取る時に、ウリ坊が「手ぐらい合わせとき」とおっこを促すシーンがある。他にも終盤でおっこがお客様のために厨房に春の湯牛の肉を運んできた時、仲居のエツ子さんがさりげなく肉に手を合わせていたりする。
このさりげない描写が実はとても重要なのではないかと筆者には思えた。死は大きな喪失だが、実はそこかしこにある。牛肉にも虫にも生命があり、それは我々の生活のいたるところで失われている。
作品に死の重さが感じられないからと言って、それは生命を軽く見積もるということではない。万物の生命に価値があると考えるからこそ、蛾の死骸にも、食材にも手を合わせるのだ。「ピンフリ」こと真月が旅館の庭のライトアップのセッティングをする際、草木の眠る時間を考慮する台詞があるのも、万物に生命があることを認識させるのに一役買っている。小学生にしてそのことに気づいている真月はすごすぎる。尊敬しかない。
死は悲しいけれど特別なことではない。だからこそ、死の匂いが色濃いにもかかわらずこの映画は「悲しすぎない」のではないだろうか。このことは、おっこが両親の死を受け入れ、成長するための遠景としても非常にうまく機能していて、物語と世界観が絶妙に噛み合っている。万物に命が宿るとする考えは、アニメーションが技術として追求してきたものであり、宮崎駿作品の中心的思想でもあり、日本の神道の信仰のあり方でもある。




















