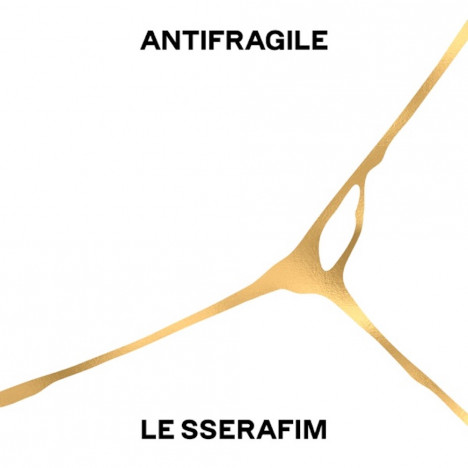連載『音楽とダンスの境界線を歩く』第2回:ラッパーとダンサーの“垣根”から生まれた新潮流 90年代R&Bに至る軌跡
2008年に指導要領の改訂で中学校保健体育にてダンスが必修化し、2018年にブエノスアイレスでの『ユースオリンピック競技大会』でブレイキン(=ブレイクダンス)が種目に採用され、2020年にプロダンスリーグ『D.LEAGUE』が発足。記憶に新しい『パリ 2024 オリンピック』(パリ五輪/2024年)にてブレイキンが採用される。その間、恋ダンス(2016年/TBS系ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』より)や、きつねダンス(2022年/ファイターズガールによるチアダンス)、「パプリカ」のダンス(2018年/Foorin「パプリカ」の振り付け)にバブリーダンス(2017年/大阪府立登美丘高等学校ダンス部の演目)といったカジュアルな踊りが若者を中心にSNSで拡散されバイラルヒットとなった。
空前絶後という枕が一ミリも大仰ではないダンスブームの今日、その歴史を音楽サイドから覗いたとき、どんな風景が広がっているのか。本連載『音楽とダンスの境界線を歩く』を通して、時代を三分割して綴ってみる。
連載『音楽とダンスの境界線を歩く』第1回:ストリートダンスのルーツ探訪 ブレイキンが国内外で覇権を握るまで
ダンスブームの昨今、その歴史を音楽サイドから覗いたとき、どんな風景が広がっているのか。ライター 若杉実が時代を三分割して綴ってい…
路上のダンス天国
ストリートカルチャーからアイドルまで、代々木のホコ天(歩行者天国)は芸能の肥沃地だった。ローラースケーターもローラー族もBボーイもバンドマンもスケーターも、そしてアイドルの卵も共存する夢の時間は80年代中盤、最高潮に達する。芸能事務所のスカウトマンたちも金の卵を探しに、日曜のホコ天に足繁く通った。
その象徴ともいうべき人物に、詰襟にマナジリを上げた沖田浩之(TBS系ドラマ『3年B組金八先生』松浦悟役)を思い出す人は少なくない。デビュー前に所属していた竹の子族がホコ天文化を全国に流布させたという意味でも理に叶う。それもリアルに路上で踊る現象を早々に生み出していたことを踏まえれば、日本のストリートダンスの歴史として検証する価値はあるだろう。事実、竹の子族には沖田のように芸能界デビューする者以外にも、ダンスプロデューサーの夏まゆみ(モーニング娘。など多数のアーティストの振り付けを担当)や、Blind Breakers(Be Bop Crew東京支部)にてSAMと合流するOHJI(安藤旺嗣)もいた。
それでも、竹の子族への注目は風俗の一場面にとどまり、ダンス側の視点から読み解く機会に恵まれていたとは言い難い。彼らの踊るステップダンスがそうした興味の埒外と見なされてきたからである。ステップダンスの一部、とりわけ上半身の振りは後年パラパラにも応用されるが、結果的にダンサーを刺激するようなダンスではなかった。夏やOHJIがダンサーという人生を将来選ぶのだから話が矛盾してしまうが、当時の彼らが未成年だったことには留意しておいたほうがいい。
裏を返せば、年齢制限のない“青空ディスコ”が若者たちにとって首尾よく働いていたことになる。名前の由来とされる原宿の「ブティック竹の子」の軒先にたむろし踊り始めることから彼らの1ページが幕開けしたが、合法的な環境を求め辿り着いた先にホコ天があった。広義的に見れば現代のトー横(キッズ)との共通点を浅慮にも指摘したくなるが、原宿と新宿の文化・時代的背景など相違は自明だろう。あるいは仮に、トー横キッズとの共通点に不良性を指摘するとしても、同質であるとは言えない。法の一線を越える云々といった副次的要素はともかく、しかしそのような意味でもホコ天のダンサーに不良性はあっても、不良とまでは言い切れない“なにか”があった。
ダンスの不良性
その“なにか”について。やや迂回しながら答えを探す。例えばほとんど語られていない事実に、Be Bop Crewと『ビー・バップ・ハイスクール』の興味深い関係があるのをご存じだろうか。ジャズ用語(BE BOP)をどちらも冠しながら、かたやダンス、かたやヤンキー漫画という相容れない双方を見えない糸で繋ぐのは、デビュー前の、きうちかずひろ。漫画の作者は学生時代に地元・福岡のディスコで踊る彼らに憧れ、自身のデビュー作に敬意を込めアレンジ、命名していた。
川端のアーケードを闊歩すれば視線を独り占めする。“踊れるヤンキー”体質でもあったという当時のBe Bop Crewとはいえ、それは漫画の主人公 ヒロシやトオルとはあきらかに異質なもの。あえて指摘するなら彼らの舎弟 ノブオに相当するだろうか。きうち自身が分身のように設定したとされるキャラからもそう類推される。つまりワイルドだがワルにまでは成り切れない後輩思いのヤンキーの性。それをマイルドヤンキーと現代用語に変換してもいいが、彼らの血がたぎるとき、飛び出しナイフの代わりにダンスの技が飛び出すのがダンサーたる嗜み。つまり不良未満の“なにか”の正体である。
ダンス人口が増え発表する機会も増えプロ化の道も開けた現在と異なり、ホコ天全盛期は前例も肖者(あやかりもの)も情報もないに等しかった。裏を返せば参入障壁が低く、わずかながらの情報さえ入手できれば第一目標は達成できたも同然だった。つまり不良未満でも、身体能力より嗅覚、情強こそが雌雄を決する。他者との差別化に意識的であることを踏まえれば、マイルドヤンキーあらため、おしゃれヤンキーと呼んだほうがいいかもしれない。
そのため技術もその進歩もゆるやか。ブルーオーシャンと言えば耳あたりはいいが、ヒップホップそのものが定着していないなか、ブレイキンの労力対効果は乏しすぎた。体力勝負の反面、齢を重ねるとロックやポップはグロテスクに映る。一部にそういう風潮があり、パワームーブ(床技)一択の時期が迫り、技巧のハードルが三たび生じ、人口も減るなど悪循環に入る。それが80年代末のこと。わずか数年の三日天下だった。
ダンサーからラッパーへ
ただしカルチャーとしてのヒップホップに一縷の望みを抱かせる事象も生まれた。上記のようにBボーイが淘汰されるなか、ラッパーへの鞍替えが著しくなる。とりわけ東京B-BOYSを率いてホコ天デビューを早々に飾ったCRAZY-Aがマイクを握る決断をしたことは、のちに『B BOY PARK』(1997〜2017年)のオーガナイザーへと栄進するだけに感慨深い。彼(ら)と気脈を通じホコ天を沸かしたFunky Rock Crewの(MC) BELLとMYSTIC MOVERSのCAKE-Kもラップユニット B-FRESHにて合流。ダンスの技からリリックの技へと武器の種類を変えていく。
ダンスの停滞がもたらした皮肉な流れだが、その源泉には1986年年末、Run-D.M.C.(+WHODINI)が金字塔「My Adidas」を携え初来日した影響も少なからずある(もしくは前年公開されたラッパー主役の映画『Krush Groove』)。大手が招聘するラップグループのライブは前例がなく、よって神戸・東京・名古屋の3公演となり、後日その模様がテレビ放映されるという、今にして奇跡的ともいえる事象が起こった。このとき前座だったのがTINY PANX(高木完+藤原ヒロシ)に、いとうせいこう、President BPM(近田春夫)。つまり限定的・外形的ではあったが、ラップのシーンは国内で芽吹いていた。

ただし、ブレイキンからラップへの変移をすべてのBボーイが無条件に歓迎したとも言い切れない。とりわけホコ天組は、Run-D.M.C.の前座だった三者への対立構図をみずから描くようなスタンスを見せた。TINY PANXを中心にMAJOR FORCEが後年興されることからも、日本のヒップホップ史において“◯◯◯ vs MAJOR FORCE”といった構図が記号化されている。この対立軸を読み解けば、“Bボーイ vs 非Bボーイ”の本質があぶり出されるのではないか。つまり本テーマである“ダンスと音楽の分岐点”のいくつか考えられるうちのひとつと見ていい。
ミュージシャン(近田、高木)、エディター(いとう)、トレンドセッター(藤原)という肩書きで固められたMAJOR FORCEの強みは、電波・紙媒体を押さえていたことに尽きる。そしてその成果のひとつがRun-D.M.C.の前座という大舞台だった。
かたやメディアとほぼ無縁だったBボーイが彼らにジェラシーをおぼえたのは否めないだろうが、恨み節とはイージーに片づけられない背景があることまで読まなければならない。
ヒップホップのヒエラルキー
たとえば現行のシーンからは想像できないだろうが、ヒップホップが輸入されたとき、その四種の神器であるブレイキン、DJ、ラップ、グラフィティのヒエラルキーは、そのままBボーイ→DJ→ラッパー→グラフィティアーティストという順だった。ZeebraやMummy-D、ZINGIのMC仁義&G.M-KAZ(元つくば万博専属ダンスユニット RUSH)などが最初にブレイキンを体験しており、DJにおいてはDJ KRUSHやDJ Ta-Shiなども同様。本国ならジャーメイン・デュプリがWHODINI、STEZOがEPMDといったように、下積み時代にラッパーのバックダンサーをしていた。
身体ひとつでできるという利点もあるにはあるが、“見たことがない(ダンス)”というインパクトが、新しい文化=ヒップホップの概念と合致しやすかったからだろう。
そして以上のことがヒエラルキーに反映される理由のひとつに、“誰よりも早くヒップホップを体現した”ことへの証明がある。“オレが最初にやったゲーム”とでも呼んでおくが、このマウント取りが小さなコップの世界で大きな役割を果たすのは、流行運動の原理を否定するものではないから。よってMAJOR FORCE(および周辺)がダンスを通過せず、ラップにリーチした道筋に小言を並べたくなるBボーイの心情に一定の理解はできる。
付言しておくと、藤原はホコ天のような世界にこそ踏み込まなかったものの、MELON(中西俊夫ほか)のライブやSTUDIO Vのファッションショーにてブレイクダンスを踊ったことが仲間から明かされているように(※1)、Bボーイイズムを部分的ながら体現してはいる。あるいは直後のTHRASHERブームに先がけスケボーに血道を上げるなど、いわゆる“文化系”以外の顔も持っていた。
藤原に触れたついでに注目したいことがもうひとつ。BPM RECORDSが始動した翌年の1987年、TINY PANXらが審査員を務めた『VESTAX ALL JAPAN OPEN DJ BATTLE vol.1』が開催された。ターンテーブリストとしてのDJコンテストはおそらく日本初だが、本命として出場していたDJ KRUSHを抑え表彰台に立ったのは、会社員時代のECD。出来レースとの風説も一部であったものの、まだ劣勢だったラッパーを押し上げ、四大要素のパワーバランスをシャッフルさせる契機となる。ラップのコンテストは前年に『Fine』誌が主催していたが(A.K.I.らによるKRUSH GROOVEが優勝)、フリースタイルバトルが定着した今日、DJの大会でラッパーの首にメダルをかけさせた意義は大きい。皮肉にもそれは音を発する側と、踊る側とに分断するチャイムにもなった。