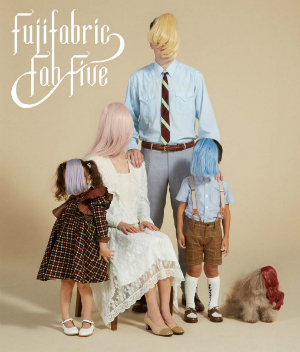フジファブリック 志村正彦の詩はいつでも“あの頃”に引き戻すーー衝動をもった作家性を振り返る
〈路地裏の僕〉(「陽炎」)、〈ほろ苦い僕〉(「TEENAGER」)といった言葉も出てくるが、それは彼にとって昔を懐かしむための郷愁というよりも、その時点の自分まで綿々と続いているものであり、いつでも“あの頃”と“今”を自在に行き来させてしまうのが、志村正彦が生み出した作品の持つ魔力なのだろう。都合よく美化された過去の記憶ではなく、大人から見たらもはや意味不明なほどの少年ならではの衝動性や、「美しい」とか「儚い」とか明確に言語化され絡め取られてしまう以前の「あれが好き・これが好き・これはなんかいやだ」という幼い頃の記憶の断片みたいなものが、彼の詩には端々まで詰まっている。
情景描写とサウンドメイクでバシッと設定を想像させつつも、細かすぎて完全に忘れてしまっているような情緒のしっぽともいうようなものをむんぎゅと掴まえて徹底的にグツグツ煮詰めた先にポンと出てきた言葉。そういうものが、志村正彦が綴っていた詩なのだと思う。それは、ファンの間で“四季シリーズ”とも呼ばれ、フジファブリックが持つ叙情性を決定的なものにした「桜の季節」「陽炎」「赤黄色の金木犀」「銀河」といった楽曲群からでもよくわかる。
「自分は学年一、本を読んでいたと思うし、図書委員だった」と前述のインタビューでも志村は話しているのだが、そういうことを踏まえてあらためて四季シリーズの楽曲など聴くと「季節の移り変わりとか、あんた最近しっかり感じ取れているんですか」と問い詰められているような気分にすらなるというものだ。また、彼の詩に出てくる女の子は、強くて、無敵感があって、しかし同時に“エロ”的なものとは全く別枠の妄想の産物でもあったりする。いろいろと急展開を見せつつ広がり続ける志村正彦の思考世界は、今やフジファブリックの代表曲として誰もが知るようになった「若者のすべて」や初期の名曲「茜色の夕日」を聴いただけでは到底理解することもできないような“ネトネトワールド”が表裏一体に存在している。
今回あらためて彼の詩作品を読み直し、そして実際に曲をかけながら歌詞としての言葉たちもまたとらえ直し、そうすることで何度でも新しい発見が立ち上がってくるという経験をした。フジファブリックの3人が、今また志村正彦のいた時代の映像作品や詩集を率先して世に出そうとしてくれるということは、つまり、今だからこそまたあらためて伝わるものが明確になってきたということなのだろうし、彼ら自身もそれをしっかりととらえ直しつつ、この先も伝え続ける命(めい)を引き受けてくれているのだとわかりありがたい。志村正彦の姿は現世に不在であるが、発信し続けているものたちに今あらためて触れてみることを多くの方におすすめしたい。
■鈴木 絵美里
1981年東京都生まれ、神奈川県育ち。東京外国語大学卒。
ディレクター・編集者として広告代理店、出版社にて10年間勤務の後、2015年より独立。現在はWEB、紙、イベントを軸としたコンテンツの企画・ディレクションおよび執筆に携わる。音楽、映画、舞台、テレビ、ラジオなどエンタテイメントを広く愛好。