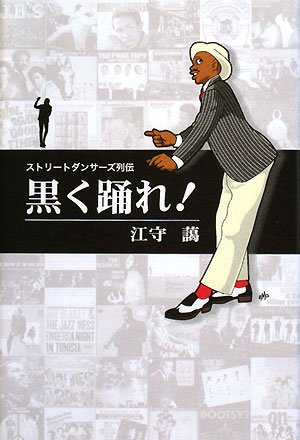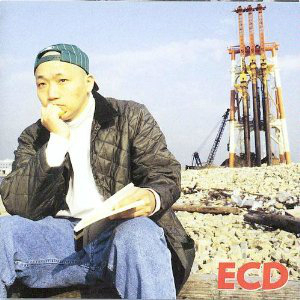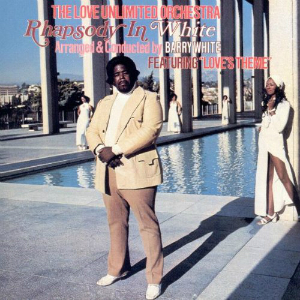『Major Force be with you -30th anniversary- 』レポート
<Major Force>は音楽的に何をしてきたのか? 荏開津広が“嵐の夜”のアニバーサリーを振り返る

故・中西俊夫、工藤昌之、高木完、屋敷豪太、そして藤原ヒロシが1988年に設立したダンスミュージックレーベル<Major Force>、その30周年を祝うイベント『Major Force be with you -30th anniversary-』が、9月30日に都市型音楽フェス『Red Bull Music Festival Tokyo 2018』の一環として開催された。

<Major Force>が、ダンスミュージックレーベルという存在を超えた、2010年代後半のグローバルなユースカルチャーの原点だということは、Red Bullがこのショウケースに際して制作したショートドキュメンタリーにおいても強調されていた(参考動画)。それが事実であるなら、この9月の終わりにやって来た嵐の夜は、<Major Force>が音楽的に何をしてきたのかを要約して聞かせてくれた、実に最初の機会ではなかったか。それはレーベルの持っていた音楽的に豊かな可能性を十二分に示しながらも、<Major Force>が設立された時期から衰退し失われつつあった、ロックへの2時間弱に渡る別離の歌のようでもあった。
ロックはまだ絶滅していないにも関わらず、別離の歌だというのは、<Major Force>の設立メンバーが(おそらく藤原ヒロシと屋敷豪太を除いて)優れて東京のロック的な感性の持ち主であり、その流れに属していたか、もしくは大きな影響を受けてそのキャリアを開始したと想像できるからだ。しかし、<Major Force>は明らかにロックレーベルではなかった。
発表されていた参加メンバーは、K.U.D.O(工藤昌之)、高木完、屋敷豪太、藤原ヒロシ、森俊二、クニ杉本、田村玄一、momo、大西ツル、TOMOHIKO a.k.a HEAVYLOOPER、EGO-WRAPPIN’、立花ハジメ、島武実、ORCHIDSなど。バンド全体の統率をする高木完のリラックスしたオーディエンスへ向けての呼びかけと、ステージ上のメンバー間での会話を挟みつつ、15曲の間にメンバーが次々と入れ替わるという体裁でステージは進んでいった。その間、高木完が着ていたのは、中西俊夫がデザインしたMELONのガーゼシャツだと気が付いた人も多かっただろう。

その夜のセットリストは、<Major Force>における中西俊夫のラッパーとしてのアバターとも言うべきユニット・TYCOON TO$Hの「Copy 88」で始まり、彼のいた日本で最も重要なポストパンクバンドのひとつ、Plasticsのヒット曲「Top Secret Man」のスレンテン(レゲエのリディムのひとつ)を使ったカバーで終わった。中西俊夫は短すぎるPlasticsの活動を終えたのち、「ピテカントロプス・エレクトス」というクラブ/サロン空間にて、サイトスペシフィックな体験に重きをおいたバンド・MELONとしての活動を始めたのだが、その彼がなぜTYCOON TO$Hになったのか。TYCOON TO$H自体の活動期間も短かったこともあり、この日のイベントまで正直なところ、わかっていなかった。中西はただ流行を取り入れただけだったのか? だが、この夜、高木完がガーゼシャツを着て、TYCOON TO$Hの「Copy88」と「Action」をラップしているのを見て、その理由がようやくわかった気がした。
ラップ/ヒップホップは、言葉が重要な最後のダンスミュージックの形式で、ダンスを導管としてツイスト以前のロックンロールと直結する。ワーキングクラスの10代が束の間の自由を謳歌するダンスであったツイストは、ジュークボックスがあれば十分に楽しめる音楽で、豪奢なオーケストラボックスとは無縁だ。そのかわり、新しいテクノロジーを必要とするのだ。サーフロックにクラフトワークの方法論を導入したことをキャリアの出発点とした中西は、その言葉とサウンドの行き着く先として、詩を伴い生まれたダンスミュージックであるヒップホップを、ロックの次の形式だと捉えていたのだ。
東京ならではのロック的感性は、そのまま高木完が披露した「フッドラム東京」のパフォーマンスからも感じられた。時折、耳に飛び込んでくる〈頭脳警察〉や〈キャピタリズム〉という単語からは、ヒップホップにビートニクの憂いを重ね合わせようと模索していたことが伺える。さらに、次の「恋のフォーミラ」のパフォーマンスには、キャロル〜クールス〜近田春夫、もしくは1970年代後期の東京のアンダーグラウンドなグラムロックにも通じる美学が見えた。
当時、<Major Force>の全貌なるものがわかりにくかったのは、この夜のステージの光景にも明らかだったように、ヒップホップなのにバンドだったり、あるいはバンドなのにメンバーが次々と入れ変わっていったりと、音楽的には決して整理されていなかったからであろう。しかし、同時にそのスタイルは現在進行形のサウンドを多方面にリリースしていく魅力にも繋がっていた。異なる4方向を指すアロウをデザインしたレーベルロゴのようにーー。
それでも “アイドルラップ”だったORCHIDSのオリジナルMC2人に替わって、2人の新たな女性MCを迎えた「I Will Call You」のパフォーマンス辺りから、オリジナルメンバーの共通点が、カウンターからアイドルまで、1968年前後〜1970年代までに提出されたポップカルチャーにおける創造的エネルギーにあったことが了解されてくる。
そして田村玄一に加え、Natural Calamityより森俊二とクニ杉本という卓越したプレイヤーを迎えたGroup Of Godsのパフォーマンスの素晴らしさといったら! 一方で、聞き手を心地よく陶酔させながらも、その時間感覚を刺激するビートをたたき出す、屋敷豪太という世界的にも希有なドラマーのプレイを堪能したオーディエンスも少なくなかっただろう。

従来の楽器や編成とまったく異なった地点から音楽を創造することを可能にした、ヒップホップというアパラタスを手に入れたK.U.D.O.や高木完に、彼ら自身がファンだったいうPlasticsの中西俊夫らの手によるハイコンセプトな楽曲群。それを無味乾燥に(従来の編成で)再現するのではなく、唯一無二のものとして現実化する優れたプレイヤーたちが<Major Force>の中核として目の前に現れたのが『Major Force be with you -30th anniversary- 』の中盤までだ。